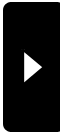2015年05月31日
伝統養蚕業 3
今は電話注文にて蚕種は宅急便で来ますが養蚕が盛んであったころは地区に明治後期から戦前ごろまで養種製造所が県から免許證を受けて営業していた。微粒子病が流行したヨーロッパに蚕種を輸出した事もあったという。愛知県は蚕種製造量では明治19年は全国16位からメンデル遺伝法則の応用し一代交雑種製法を行い大正7年には長野県に次ぎ2位になった。蚕という動物にメンデル遺伝法則を応用する品種改良は素晴らしいことです。
蚕が蛹になる前に雄雌を別にして繭つくりをさせて雄蛾雌蛾を交配産卵さた。雌雄鑑別手が繭つくり前の5令幼虫の背中をつまむと腹部に白い米粒点が現れるのを1.2秒で判別、女性5.6人で朝6時から夕方5時頃まで、5,6日泊り込みで判別した。
蚕紙に卵、写真の白いのは孵化した跡です

昔は卵を均一に卵散していた

旧東郷村養蚕組合が使用していた卵散機

上の漏斗(じょうご)から蚕卵を落すと均等に卵は散る、ブリキ板の形に注目です。

保護紙を被せる、

蚕種冷蔵庫に春の桑葉が育つごろまで保管する。
下写真は掃き立(孵化)してから17日めの蚕

大きく育っています。
蚕が蛹になる前に雄雌を別にして繭つくりをさせて雄蛾雌蛾を交配産卵さた。雌雄鑑別手が繭つくり前の5令幼虫の背中をつまむと腹部に白い米粒点が現れるのを1.2秒で判別、女性5.6人で朝6時から夕方5時頃まで、5,6日泊り込みで判別した。
蚕紙に卵、写真の白いのは孵化した跡です
昔は卵を均一に卵散していた
旧東郷村養蚕組合が使用していた卵散機
上の漏斗(じょうご)から蚕卵を落すと均等に卵は散る、ブリキ板の形に注目です。
保護紙を被せる、
蚕種冷蔵庫に春の桑葉が育つごろまで保管する。
下写真は掃き立(孵化)してから17日めの蚕
大きく育っています。
2015年05月30日
長篠設楽原の戦い・見聞録 117
天正3年5月21日連吾川を挟み対峙した設楽原の戦いにおいて織田徳川連合軍は「鉄砲千挺」か「鉄砲三千挺」を使用したかの「筆跡」調査を岐阜工業高校の報道・放送部が調査したと中日新聞夕刊に載っていた。

三の文字を「信長公記」の中に270文字あった、太田自筆に似ているものは42個、似てない文字は228個だったと記している。
織田信長の家臣・太田牛一が書いた「信長公記」に「三」の文字が後書きのようにあることから本人が追加記したか、誰かが書いたか、が問題になっている。

長篠設楽原の戦い・見聞録 66 にも記載しましたが「火縄銃三千挺の三段撃ち」はあったか否か、歴史学者がいろいろ書いている。
三の文字を「信長公記」の中に270文字あった、太田自筆に似ているものは42個、似てない文字は228個だったと記している。
織田信長の家臣・太田牛一が書いた「信長公記」に「三」の文字が後書きのようにあることから本人が追加記したか、誰かが書いたか、が問題になっている。
長篠設楽原の戦い・見聞録 66 にも記載しましたが「火縄銃三千挺の三段撃ち」はあったか否か、歴史学者がいろいろ書いている。
2014/05/30
屏風図の合戦ー16 この長篠設楽原の戦いで織田徳川連合軍が火縄銃を何丁用意していたか?三千丁の銃の三段撃ちがあったのか?と多くの歴史研究者が資料を集めて各自の見解を書いています。 まず、問題の火縄銃の数、一千丁か三千丁かのきっかけは信長の家臣、太田牛一が書いた「信長公記・しんちょうこうき」…
2015年05月28日
今日の茶臼山芝桜
午前10時ごろ思い付きで茶臼山芝桜を見に出かけた。高原道路も駐車場も空いてスムーズに到着。
リフトの真下がご覧のよう


正面は

北側は最盛期を過ぎています

正面が残念なことになっています。

ヤギさんと遊んできた。
リフトの真下がご覧のよう
正面は
北側は最盛期を過ぎています
正面が残念なことになっています。
ヤギさんと遊んできた。
2015年05月28日
手乗り蝶・旅たちのつづき
旅立ったアゲハ蝶が1時間して戻って来たんです。
部屋にいて庭に蝶が舞っているのを見まして出てみると
プランターにアゲハが休憩中?です

指を出すと登ってきます



いつまでも観察して居られません

ビワの葉にとまらせて擱き1時間後には姿は消えていました。
部屋にいて庭に蝶が舞っているのを見まして出てみると
プランターにアゲハが休憩中?です
指を出すと登ってきます
いつまでも観察して居られません
ビワの葉にとまらせて擱き1時間後には姿は消えていました。
2015年05月27日
伝統養蚕業 2
全国の養蚕家が減少し平成23年は621軒でしたが今では約500軒と推測されるなか、新城市では定年後、養蚕を始めた方を入れて2軒が養蚕をしている。
養蚕は時代とともに変わっています、今は行われているか、新城市出沢の海野さん宅を訪れた。
絹糸の繭を作る蚕になる卵は何処に保管されているのか?養蚕業が盛んであった時は地域に養蚕組合があり蛹から種をとるため蚕蛾を交尾⇒産卵⇒春まで冷蔵保管⇒蚕種冷蔵庫は池から氷を切りだしていた所もあったようです。また、風穴、山の洞穴などで冷蔵保存した。
現在は長野県の会社に連絡すると宅急便にて到着する

箱の中は下の写真の台紙に胚たった1ミリ程の孵化した蚕が1シート2万匹が保護粘床、保護玉(種紙)に守られている。

白い粒は胚たった蚕の殻、冷蔵保存の卵は気温を24℃にすると孵化する。
保育器にて保温し

2.3時間後に細切した桑葉を与える

卵種紙(框・かまち製だった)から蚕を外す、極小な蚕、鳥羽を使う。

細かい桑葉を与え

保育器へ入れる

5月9日の蚕

これから脱皮を繰り返し成長していく。
つづく
養蚕は時代とともに変わっています、今は行われているか、新城市出沢の海野さん宅を訪れた。
絹糸の繭を作る蚕になる卵は何処に保管されているのか?養蚕業が盛んであった時は地域に養蚕組合があり蛹から種をとるため蚕蛾を交尾⇒産卵⇒春まで冷蔵保管⇒蚕種冷蔵庫は池から氷を切りだしていた所もあったようです。また、風穴、山の洞穴などで冷蔵保存した。
現在は長野県の会社に連絡すると宅急便にて到着する
箱の中は下の写真の台紙に胚たった1ミリ程の孵化した蚕が1シート2万匹が保護粘床、保護玉(種紙)に守られている。
白い粒は胚たった蚕の殻、冷蔵保存の卵は気温を24℃にすると孵化する。
保育器にて保温し
2.3時間後に細切した桑葉を与える
卵種紙(框・かまち製だった)から蚕を外す、極小な蚕、鳥羽を使う。
細かい桑葉を与え
保育器へ入れる
5月9日の蚕
これから脱皮を繰り返し成長していく。
つづく
2015年05月26日
旅立ちです
甘夏の枝を切った時に蝶の蛹(さなぎ)が付いていましたのでバケツに入れて7~10日、今朝、羽化し旅立ました。

アゲハ蝶のようです。
昨日夕方、蚕同様に蛹を透かして見ると体が黄色くなっている。

明日朝辺りに羽化かと思い、今日朝6時に見ると

上写真のごとし(6時6分)
後は羽根が伸び乾いて飛び立つのを待つ


7時17分ほゞ羽は整う

羽が乾燥したか、8時15分飛び立つ体勢になり

即、旅たちました。
私もボチボチ旅たちの仕度を・・・
アゲハ蝶のようです。
昨日夕方、蚕同様に蛹を透かして見ると体が黄色くなっている。
明日朝辺りに羽化かと思い、今日朝6時に見ると
上写真のごとし(6時6分)
後は羽根が伸び乾いて飛び立つのを待つ
7時17分ほゞ羽は整う
羽が乾燥したか、8時15分飛び立つ体勢になり
即、旅たちました。
私もボチボチ旅たちの仕度を・・・
2015年05月25日
2015年05月24日
2015年05月22日
2015年05月21日
天敵の隣りで
長野県根羽村、道路脇の防火水槽にモリアオカエルの卵塊を見つけまして


新城より早い産卵?、今年が早いのかな?
水槽に浮いているHS上には

天敵、ヤマカガシ が日向ボッコ中です。
立派なヤマカガシですね。
新城より早い産卵?、今年が早いのかな?
水槽に浮いているHS上には
天敵、ヤマカガシ が日向ボッコ中です。
立派なヤマカガシですね。
2015年05月20日
郵便ポスト 俺は待ってるぜ!
新聞に時々紹介される郵便ポスト
設楽ダム建設により移転し昨年閉区式をした八橋地区
県道10号線沿い、民家のないバス停近くに投函を待っているポスト

(昨日、Am撮影、霧に覆われている知生山)
変わらないのは地区のシンボル知生山(860.3m)と
郵便ポストですね。
きっと皆さんからの投函を待っていると思います。

近くの電線に「ホホジロ」が囀っていました。
郵便ホスト
設楽ダム建設により移転し昨年閉区式をした八橋地区
県道10号線沿い、民家のないバス停近くに投函を待っているポスト
(昨日、Am撮影、霧に覆われている知生山)
変わらないのは地区のシンボル知生山(860.3m)と
郵便ポストですね。
きっと皆さんからの投函を待っていると思います。
近くの電線に「ホホジロ」が囀っていました。
郵便ホスト
2015年05月20日
大杉のパワーいただきまして・・
長野県下伊那郡根羽村「月瀬の大杉」国天然記念物からパワーをいただきによりました。

5.6回訪れるますが都度、感激パワーをいただいています。
樹齢1800年 目通り幹廻り14m
樹高 40m
大事変起きる前に「前兆として大枝が折れる」と云う。
近くを通る国道沿いに駐車場が昨年完成し吊橋を渡り観賞できます。


大杉を見上げると枝が折れていますね
いつ折れたのでしょうか。
月瀬の大杉 駐車場
5.6回訪れるますが都度、感激パワーをいただいています。
樹齢1800年 目通り幹廻り14m
樹高 40m
大事変起きる前に「前兆として大枝が折れる」と云う。
近くを通る国道沿いに駐車場が昨年完成し吊橋を渡り観賞できます。
大杉を見上げると枝が折れていますね
いつ折れたのでしょうか。
月瀬の大杉 駐車場
2015年05月19日
2015年05月19日
2015年05月18日
伊那街道を歩く 55
根羽村新井橋~ゴハンギョの道標
距離 1.48㎞ 時間 46分
桧原川の①新井橋脇に山道から②下り右折し県道10号線をしばらく歩く、平坦な道になり足も軽快になる。

250m程歩いた左に③「田島露頭」看板がある、桧原川を見下ろす所だが露頭、玄武岩がハッキリ見えない。

対岸を見る、桧原川左岸にも古道があり伊那街道として新井橋辺りで桧原川を渡っていたと言う。

県道の右に石碑があり④右折し民家の間を街道は行く


約100mほどの民家の間

途中にある馬頭観音

⑤道路に出たところに石碑?と井戸?らしいものがある、渇きを潤した清水が出ていたか。左折して

県道に出て右折し約100m、左にある⑥畦道を桧原川方向へ街道を歩く


⑦下道を右折し

歩くと右手に⑧石碑群がある

⑨県道へ出て左折する、街道は直進していたとも考えられる。

小戸名川に架かる⑩平瀬橋を渡り左折し

街並みを約200m歩くと右に⑪石碑群が祀られている。



根羽の街並み

更に100mほど歩くと本来の飯田街道と交差する右角に⑫道標がある、伊那街道が飯田街道と繋がる地点だ。ここで伊那街道は終わる。

「ゴハンギョの道標」と云っている、「通行の時に判子を押した」と云われ「御半行」と書くようです。

御上の伝達、高札があった所の道標、⑬根羽村役場は国道沿いにある
道標には
此方 なごやみち(表)
此方 ぜんこう寺みち(右)
此方 ほうらい寺みち(左)
明和八年(1771)
御用商人・石原藤兵衛と組頭五郎兵衛により建てられた。
高さ1m 幅30㎝ 花崗岩

豊川市小坂井町から歩いた日数14日間、山道に入った冬季は積雪凍結のため1月中句から3月初句まで休み、予定日が雨天で延期もあり最終完歩日が5月初句までになった。3年前に探索した「実録・伊那街道」が今回役たちスムーズな行動ができたことは間違いない。
伊那街道が在った、歩いた、で終わるのでなく先人たちが険しい山道を一歩々歩いた重要な生活の道だったことや歴史的にも戦国時代は武田軍の侵攻退却、信玄の病に臥し甲斐へ帰る途中亡くなったとも云われる道であることを思いながら歩いた。こんな険しい山道を中馬が往来したのか?と疑う街道もあったが馬の安全供養を願う馬頭観音、郷を護る塞の神、道祖神、庚申、行者様、三界萬霊塔、秋葉山関係碑その他多くの石仏碑にも出逢った。病自然災害も神頼み時代、私たちの祖先の生きていた時代を想うと生きるために如何に苦労して来たか改めて考えさせる伊那街道歩きだった。
今後も伊那街道関連記載事は追加記載したいと思う。
(知生峠強盗殺人事件は後日記載する)
距離 1.48㎞ 時間 46分
桧原川の①新井橋脇に山道から②下り右折し県道10号線をしばらく歩く、平坦な道になり足も軽快になる。
250m程歩いた左に③「田島露頭」看板がある、桧原川を見下ろす所だが露頭、玄武岩がハッキリ見えない。
対岸を見る、桧原川左岸にも古道があり伊那街道として新井橋辺りで桧原川を渡っていたと言う。
県道の右に石碑があり④右折し民家の間を街道は行く
約100mほどの民家の間
途中にある馬頭観音
⑤道路に出たところに石碑?と井戸?らしいものがある、渇きを潤した清水が出ていたか。左折して
県道に出て右折し約100m、左にある⑥畦道を桧原川方向へ街道を歩く
⑦下道を右折し
歩くと右手に⑧石碑群がある
⑨県道へ出て左折する、街道は直進していたとも考えられる。
小戸名川に架かる⑩平瀬橋を渡り左折し
街並みを約200m歩くと右に⑪石碑群が祀られている。
根羽の街並み
更に100mほど歩くと本来の飯田街道と交差する右角に⑫道標がある、伊那街道が飯田街道と繋がる地点だ。ここで伊那街道は終わる。
「ゴハンギョの道標」と云っている、「通行の時に判子を押した」と云われ「御半行」と書くようです。
御上の伝達、高札があった所の道標、⑬根羽村役場は国道沿いにある
道標には
此方 なごやみち(表)
此方 ぜんこう寺みち(右)
此方 ほうらい寺みち(左)
明和八年(1771)
御用商人・石原藤兵衛と組頭五郎兵衛により建てられた。
高さ1m 幅30㎝ 花崗岩
豊川市小坂井町から歩いた日数14日間、山道に入った冬季は積雪凍結のため1月中句から3月初句まで休み、予定日が雨天で延期もあり最終完歩日が5月初句までになった。3年前に探索した「実録・伊那街道」が今回役たちスムーズな行動ができたことは間違いない。
伊那街道が在った、歩いた、で終わるのでなく先人たちが険しい山道を一歩々歩いた重要な生活の道だったことや歴史的にも戦国時代は武田軍の侵攻退却、信玄の病に臥し甲斐へ帰る途中亡くなったとも云われる道であることを思いながら歩いた。こんな険しい山道を中馬が往来したのか?と疑う街道もあったが馬の安全供養を願う馬頭観音、郷を護る塞の神、道祖神、庚申、行者様、三界萬霊塔、秋葉山関係碑その他多くの石仏碑にも出逢った。病自然災害も神頼み時代、私たちの祖先の生きていた時代を想うと生きるために如何に苦労して来たか改めて考えさせる伊那街道歩きだった。
今後も伊那街道関連記載事は追加記載したいと思う。
(知生峠強盗殺人事件は後日記載する)
2015年05月17日
伊那街道を歩く 54
根羽村桧原川森林作業橋~新井橋
距離 約1.33㎞ 時間 1時間28分
森林作業橋から下流の新井橋へ向かう
県道10号線A作業橋近くに祀られている馬頭観音、天明8年(1788)と読める

県道から桧原川に架かる作業橋を渡り伊那街道へ


歩き出して10分、道脇に発電所水路が倒木の下に見える、大正9年(1920)7月27日根羽水力電気(株)資本金10万円で設立した桧原川発電所の導水路。
同11年11月3日営業、1軒1灯13~30ワット、根羽村・平谷村・上下津具村へ配電。需要増し矢作電気・伊那電気から供給受け営業したが水車メタルが故障し火災、洪水により水路崩壊、発電少なく暗い、料金回収不足により昭和10年4月伊那電気に譲渡、昭和17年3月で運転して停止、同21年廃止した。

水を落下管口


当時の写真(頂いた資料から)

周りには木々はない、右に橋があるが橋脚は桧原川に残っている。
伐採木が街道をふさぐ

草木が生い茂る

約40分歩いた所、岩の上に馬頭観音が祀られている

明治と刻まれているようだ

石積みがある、畑か、耕地だったようです

樹木の中を伊那街道は根羽へ

又も間伐材が街道を被う

スタートから1時間10分、石橋のような?

明るくなった、整備された水路がある。田んぼへの水路だ。

街道は水路を渡り30m行くと沢にでる、橋がなく深く進めない

沢伝いに登り用水路から沢の反対へ


街道を下ると民家脇に

県道10号線に出る。

桧原川に架かるB新井橋は新旧あり旧橋の橋脚が奇麗なアーチ形をしている

川原に降りて見ると新旧の新井橋橋脚が観賞できる

Cは烏帽子岩(えぼしいわ)
森林作業用橋~新井橋

伊那街道もあと少しで完歩です。
桧原川新井橋
つづく
距離 約1.33㎞ 時間 1時間28分
森林作業橋から下流の新井橋へ向かう
県道10号線A作業橋近くに祀られている馬頭観音、天明8年(1788)と読める
県道から桧原川に架かる作業橋を渡り伊那街道へ
歩き出して10分、道脇に発電所水路が倒木の下に見える、大正9年(1920)7月27日根羽水力電気(株)資本金10万円で設立した桧原川発電所の導水路。
同11年11月3日営業、1軒1灯13~30ワット、根羽村・平谷村・上下津具村へ配電。需要増し矢作電気・伊那電気から供給受け営業したが水車メタルが故障し火災、洪水により水路崩壊、発電少なく暗い、料金回収不足により昭和10年4月伊那電気に譲渡、昭和17年3月で運転して停止、同21年廃止した。
水を落下管口


当時の写真(頂いた資料から)

周りには木々はない、右に橋があるが橋脚は桧原川に残っている。
伐採木が街道をふさぐ
草木が生い茂る
約40分歩いた所、岩の上に馬頭観音が祀られている
明治と刻まれているようだ
石積みがある、畑か、耕地だったようです
樹木の中を伊那街道は根羽へ
又も間伐材が街道を被う
スタートから1時間10分、石橋のような?
明るくなった、整備された水路がある。田んぼへの水路だ。
街道は水路を渡り30m行くと沢にでる、橋がなく深く進めない
沢伝いに登り用水路から沢の反対へ
街道を下ると民家脇に
県道10号線に出る。
桧原川に架かるB新井橋は新旧あり旧橋の橋脚が奇麗なアーチ形をしている
川原に降りて見ると新旧の新井橋橋脚が観賞できる

Cは烏帽子岩(えぼしいわ)
森林作業用橋~新井橋
伊那街道もあと少しで完歩です。
桧原川新井橋
つづく
2015年05月16日
伊那街道を歩く 53
根羽村桧原川・中之橋~森林作業橋
距離 約1.4㎞ 1時間25分
これからしばらく山道になる
①中之橋右岸袂を入る

右上は造成地、歩きやすい

造成石積間に石碑が祀られている②「三界萬霊塔」

三界は食欲・物欲・性欲とか過去・現在・未来とか云います、また欲界色界無色界とよく判りません。
歩き出して250m、沢に出る、③丸太橋があるが渡ると落下しそう、沢に降りて渡る。

笹の茂った街道を過ぎ、街道は上がるが右の④桧原川右岸に道はあるか下りて見るがない。戻り進むと右上に大岩、下を歩く。

街道道筋が残っている

岩上に馬頭観音が祀られている。

⑤沢を数ヵ所渡るが全て渡り難いものばかりだ

歩き出して1時間20分、前方が明るくなる

足元に⑥水路跡がある、前回に見た発電所水路だ、近くに桧原川を渡り県道へ出る⑦林業作業橋がある。

川岸を見ると赤い鉄骨橋があった。


県道10号線にでた所

県道から歩いて来た所を見るが何処だかまったく解らない、ただ桧原川右岸の少し高い所を歩いて来たくらいだ。

作業橋上流、県道脇に⑧「釜ヶ入りの甌穴」がある、ホットホールと「黒体竜王」が対岸、右岸にあるが橋がなく渡れない。

歩いて来た伊那街道からここに下りる案内道には気づかなっかた、今はないか。

祭の時は橋を架けるようだ、穴に石を投げ込むと竜王が怒り黒雲、大雨を降らす。



下流の烏帽子岩の所に「白体竜王」が祀られていると説明がある。
伊那街道では一番難所が根羽村内である、街道の崩壊数ヵ所あり、沢も多い、この難所もあと少し歩くと県道に出る。
歩いた所

桧原川中之橋
つづく
距離 約1.4㎞ 1時間25分
これからしばらく山道になる
①中之橋右岸袂を入る
右上は造成地、歩きやすい
造成石積間に石碑が祀られている②「三界萬霊塔」
三界は食欲・物欲・性欲とか過去・現在・未来とか云います、また欲界色界無色界とよく判りません。
歩き出して250m、沢に出る、③丸太橋があるが渡ると落下しそう、沢に降りて渡る。
笹の茂った街道を過ぎ、街道は上がるが右の④桧原川右岸に道はあるか下りて見るがない。戻り進むと右上に大岩、下を歩く。
街道道筋が残っている
岩上に馬頭観音が祀られている。
⑤沢を数ヵ所渡るが全て渡り難いものばかりだ
歩き出して1時間20分、前方が明るくなる
足元に⑥水路跡がある、前回に見た発電所水路だ、近くに桧原川を渡り県道へ出る⑦林業作業橋がある。
川岸を見ると赤い鉄骨橋があった。
県道10号線にでた所
県道から歩いて来た所を見るが何処だかまったく解らない、ただ桧原川右岸の少し高い所を歩いて来たくらいだ。
作業橋上流、県道脇に⑧「釜ヶ入りの甌穴」がある、ホットホールと「黒体竜王」が対岸、右岸にあるが橋がなく渡れない。
歩いて来た伊那街道からここに下りる案内道には気づかなっかた、今はないか。
祭の時は橋を架けるようだ、穴に石を投げ込むと竜王が怒り黒雲、大雨を降らす。
下流の烏帽子岩の所に「白体竜王」が祀られていると説明がある。
伊那街道では一番難所が根羽村内である、街道の崩壊数ヵ所あり、沢も多い、この難所もあと少し歩くと県道に出る。
歩いた所
桧原川中之橋
つづく
2015年05月15日
伊那街道を歩く 52
設楽町津具・①折元峠~県境~長野県根羽村・桧原川⑩中之橋 約4.9㎞ 1時間50分
峠にはお茶屋さんと営林署の建物があったと上津具で偶然会った渡辺さんの話、渡辺さんは昭和2年生まれ、お祖父さんが茶屋を営みそこから津具小学校へ坂道を6年生まで通った。写真左側に沢、古道と石組がある。

茶臼山高原道路 設楽町西納庫・国道257号線と豊根村・茶臼山高原を結ぶ道路は昭和56年全線開通し観光道路の役目を充分果たしている。

左に②「つぐ高原グリーンパーク」がある。オートキャンプ場、バンガローテニスコート天文台、宿泊施設などがあり、今は「道の駅」が併設されている。

元はスケート場があった所です。昭和27年に冬季寒冷地を利用した天然氷、公認400mのリンクがありウインタースポーツの拠点だった。


冬季でも気温上昇すると滑走不になる事もあり昭和40年に人工パイピングを内リンクに設置、90日営業、5万1千人入場した。しかし47年に閉鎖した。足袋に下駄スケートで滑走した事を思い出す。
道の駅から県道を約500m根羽村へ歩くと③左に入る道が街道である。、

県道から約300m小さな橋、愛知長野県境の④国界橋である。昔で云う三河信州の国境である。

遠回りして長野県道10号線に出る、愛知県も県道10号線であり両県で統一したのか?
眼前に大きなナラの木がある。村指定⑤「離山の大ナラ」樹齢約250年、 樹高14.5m、下に馬頭観音などが祀られている。


離山地区、県道が直線、街道は県道側にあったようですがハッキリしない。

街道脇に祀られている石碑



右カーブした所に木造二階建ての⑥「桧原分教場跡」がある。明治21年に「根羽学校派出場」として開校、明治35年に分教所に、昭和36年本校に統合された。

分教場跡から約600m桧原橋の手前右に⑦「秋葉山大権現文字碑がある。文化2年(1802)建立、高さ72㎝

⑧桧原橋を渡り右折すると根羽のゴルフ場である。

伊那街道は石碑の後にあったようで道跡がある

写真の県道左側に道痕あり

桧原地区、街道は右折して山手を通っていたようだが地元の方はよく判らないという。

右折すると⑨石仏がある、移転したようだ。

県道脇にあった石仏

左を流れていた桧原川を県道は⑩中之橋で越すが伊那街道は橋手前を⑪右折し県道と別れ山道へとつづく。

これから桧原川の右岸を街道は根羽村の飯田街道・国道153号線へ向っている。3年前この先、探索に3日かかった。今回は順調に歩く事ができるか。
歩い道

根羽村村誌に豊橋街道(伊那街道)の改修について記載してある。
明治9年(1876)6月、太政官達第60号により3等県道になった。
明治24年の「荷物及通行旅人調」によると年間通行量、荷物5万3010駄、旅人1万787人とある。単純に荷物が1駄30貫約112.4㌔とすると597.4㌧になり1日145駄、旅人は約30人である。この数は届けでた数だから実際はこれより多いと思わおれる。
街道の改修を村として郡県に願届けたが不採決されている。26年、愛知県側の上津具村・村松村長から根羽村・石原村長へ書簡にて「26年6月から折元峠を越え根羽村離山の信三国境に向かって工事は捗っている、貴村はいかになっているか」と催促をしている。当時は荷車、馬車の通れる広い所で2.5間幅(約4.5m)の坂、曲りの多い道路だった。
つづく
峠にはお茶屋さんと営林署の建物があったと上津具で偶然会った渡辺さんの話、渡辺さんは昭和2年生まれ、お祖父さんが茶屋を営みそこから津具小学校へ坂道を6年生まで通った。写真左側に沢、古道と石組がある。
茶臼山高原道路 設楽町西納庫・国道257号線と豊根村・茶臼山高原を結ぶ道路は昭和56年全線開通し観光道路の役目を充分果たしている。
左に②「つぐ高原グリーンパーク」がある。オートキャンプ場、バンガローテニスコート天文台、宿泊施設などがあり、今は「道の駅」が併設されている。
元はスケート場があった所です。昭和27年に冬季寒冷地を利用した天然氷、公認400mのリンクがありウインタースポーツの拠点だった。


冬季でも気温上昇すると滑走不になる事もあり昭和40年に人工パイピングを内リンクに設置、90日営業、5万1千人入場した。しかし47年に閉鎖した。足袋に下駄スケートで滑走した事を思い出す。
道の駅から県道を約500m根羽村へ歩くと③左に入る道が街道である。、
県道から約300m小さな橋、愛知長野県境の④国界橋である。昔で云う三河信州の国境である。
遠回りして長野県道10号線に出る、愛知県も県道10号線であり両県で統一したのか?
眼前に大きなナラの木がある。村指定⑤「離山の大ナラ」樹齢約250年、 樹高14.5m、下に馬頭観音などが祀られている。
離山地区、県道が直線、街道は県道側にあったようですがハッキリしない。
街道脇に祀られている石碑
右カーブした所に木造二階建ての⑥「桧原分教場跡」がある。明治21年に「根羽学校派出場」として開校、明治35年に分教所に、昭和36年本校に統合された。
分教場跡から約600m桧原橋の手前右に⑦「秋葉山大権現文字碑がある。文化2年(1802)建立、高さ72㎝
⑧桧原橋を渡り右折すると根羽のゴルフ場である。
伊那街道は石碑の後にあったようで道跡がある
写真の県道左側に道痕あり
桧原地区、街道は右折して山手を通っていたようだが地元の方はよく判らないという。
右折すると⑨石仏がある、移転したようだ。
県道脇にあった石仏
左を流れていた桧原川を県道は⑩中之橋で越すが伊那街道は橋手前を⑪右折し県道と別れ山道へとつづく。
これから桧原川の右岸を街道は根羽村の飯田街道・国道153号線へ向っている。3年前この先、探索に3日かかった。今回は順調に歩く事ができるか。
歩い道
根羽村村誌に豊橋街道(伊那街道)の改修について記載してある。
明治9年(1876)6月、太政官達第60号により3等県道になった。
明治24年の「荷物及通行旅人調」によると年間通行量、荷物5万3010駄、旅人1万787人とある。単純に荷物が1駄30貫約112.4㌔とすると597.4㌧になり1日145駄、旅人は約30人である。この数は届けでた数だから実際はこれより多いと思わおれる。
街道の改修を村として郡県に願届けたが不採決されている。26年、愛知県側の上津具村・村松村長から根羽村・石原村長へ書簡にて「26年6月から折元峠を越え根羽村離山の信三国境に向かって工事は捗っている、貴村はいかになっているか」と催促をしている。当時は荷車、馬車の通れる広い所で2.5間幅(約4.5m)の坂、曲りの多い道路だった。
つづく
2015年05月14日
2015年05月13日
伊那街道を歩く 50
設楽町津具・信玄橋~行人原行者様
奥三河には武田信玄に縁の地名伝説が多数あります。
武田軍は元亀2年(1571)奥三河へ侵攻、同3年10月上洛軍を進め三方ヶ原で徳川織田軍に大勝し明くる年、野田城を攻めるが信玄病重くなり引上げる時、津具を通り陣を置いたとも云われている。
津具には金を採掘した信玄抗跡、信玄塚、その一つが①信玄橋である。
信玄橋から約70m、石仏群が左にある②信玄塚だ。
中央高いのが「徳住名号塔」 高さ206㌢、文政9年(1826)建立、独特文字で「南無阿弥陀仏」と名号が刻まれ下に徳住・村中とある。

徳住は幡豆生まれ、行者・徳本の弟子であり吉野山中で修業し布教廻った。

街道は県道から左に入り歩く。入口に③道標がある。
至 折元峠 旧道 21丁(約2.3㎞) 新道 1里7丁(約5㎞)
旧道とは伊那街道 新道は明治25年に開通した今の県道10号線、現距離は約4.2㎞です。

右手に軒先が長く突き出た民家がある④「せいが造り」という。養蚕時、濡れた桑を乾燥するスペースだという。津具では明治5年(1872)ごろから野桑葉で飼育したようです。桑木蚕種を買い付け明治20年代になると盛んになる。

右に森があり奥に⑤本堂寺があり多数の石仏が祀られている。


本堂寺横に郷倉がある。飢餓に備え食料を貯蔵した。

馬頭観世音、馬頭観音は街道山道脇に建てられ馬の息災と倒れた馬の霊を弔う物。観音様の頭部に馬頭を刻むものと平板に刻んだ物がある。

行人原のツガ 2代目だそうです、樹高25m以上

右小高い所に⑥「行者」様が祀られている。
相模の順阿(じゅんな)行者が足を病み寿命短いを悟り21日絶食し天命全うしたと云う。
この辺りを行人原という。


道標
奥三河には武田信玄に縁の地名伝説が多数あります。
武田軍は元亀2年(1571)奥三河へ侵攻、同3年10月上洛軍を進め三方ヶ原で徳川織田軍に大勝し明くる年、野田城を攻めるが信玄病重くなり引上げる時、津具を通り陣を置いたとも云われている。
津具には金を採掘した信玄抗跡、信玄塚、その一つが①信玄橋である。
信玄橋から約70m、石仏群が左にある②信玄塚だ。
中央高いのが「徳住名号塔」 高さ206㌢、文政9年(1826)建立、独特文字で「南無阿弥陀仏」と名号が刻まれ下に徳住・村中とある。
徳住は幡豆生まれ、行者・徳本の弟子であり吉野山中で修業し布教廻った。
街道は県道から左に入り歩く。入口に③道標がある。
至 折元峠 旧道 21丁(約2.3㎞) 新道 1里7丁(約5㎞)
旧道とは伊那街道 新道は明治25年に開通した今の県道10号線、現距離は約4.2㎞です。
右手に軒先が長く突き出た民家がある④「せいが造り」という。養蚕時、濡れた桑を乾燥するスペースだという。津具では明治5年(1872)ごろから野桑葉で飼育したようです。桑木蚕種を買い付け明治20年代になると盛んになる。
右に森があり奥に⑤本堂寺があり多数の石仏が祀られている。
本堂寺横に郷倉がある。飢餓に備え食料を貯蔵した。
馬頭観世音、馬頭観音は街道山道脇に建てられ馬の息災と倒れた馬の霊を弔う物。観音様の頭部に馬頭を刻むものと平板に刻んだ物がある。
行人原のツガ 2代目だそうです、樹高25m以上
右小高い所に⑥「行者」様が祀られている。
相模の順阿(じゅんな)行者が足を病み寿命短いを悟り21日絶食し天命全うしたと云う。
この辺りを行人原という。
道標