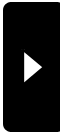2025年03月31日
千葉県の一鍬田
30日の朝、NHKテレビ、Ⅾearにっぽん「町が空港になる前に」千葉・多古町
が放送されていた。
その中に飛行場拡大で一鍬田と言う地名が消えると言っていた。
新城市の一鍬田と同じ地名に思わず魅入った。
下総国(しもうさのくに)多古藩があって、この事が書かれたものを読んだ気がするが、何処で何を読んだか分からない。
新城市の一鍬田へ行ってみたが手掛かりはなかった。

<一鍬田公民館>バス停
もしかしたら新城市の一鍬田から移封して故郷を忍んで一鍬田地名を付けたかも知れない。
桜淵公園の桜も咲いてきましたね。

が放送されていた。
その中に飛行場拡大で一鍬田と言う地名が消えると言っていた。
新城市の一鍬田と同じ地名に思わず魅入った。
下総国(しもうさのくに)多古藩があって、この事が書かれたものを読んだ気がするが、何処で何を読んだか分からない。
新城市の一鍬田へ行ってみたが手掛かりはなかった。
<一鍬田公民館>バス停
もしかしたら新城市の一鍬田から移封して故郷を忍んで一鍬田地名を付けたかも知れない。
桜淵公園の桜も咲いてきましたね。
2025年02月25日
記事、彦根城から
24日の中日新聞記事に「庭」玄宮園が記載されていた。
2017年頃に3回は訪れた気がするが定かでない。
駐車場に車を停めて3.4時間後に戻ると駐車場係りの方が「お宅の車に衝突した方がいる」と言う。
車を見ると右Fフエンダーが凹んでいる、相手連絡先のメモを頂いた事を思い出した。
<2017年12月玄宮園>

彦根城は徳川家康が西国の前線基地として7か国12大名に命じ築城した
天守は大津城から移築
西の丸三重櫓は小谷城から
天秤櫓は長濱城から太鼓門は佐和山城からそれぞれ移築したという。
豊臣方滅亡を家康は計画していた事から急いで彦根城を完成させたかったが井伊直政は鉄砲傷が元で死去。
キャラクターの「ひこにゃん」の事

彦根井伊家当主・直孝は武蔵国世田谷村でにわか雨に遭い広徳院の大木の下で雨宿りをしていると手招きをする白猫がいた。
近寄って行った直後に大木に落雷した。
直孝の命を救った白猫がマスコットキャラクターになったそうです。
2017年頃に3回は訪れた気がするが定かでない。
駐車場に車を停めて3.4時間後に戻ると駐車場係りの方が「お宅の車に衝突した方がいる」と言う。
車を見ると右Fフエンダーが凹んでいる、相手連絡先のメモを頂いた事を思い出した。
<2017年12月玄宮園>

彦根城は徳川家康が西国の前線基地として7か国12大名に命じ築城した
天守は大津城から移築
西の丸三重櫓は小谷城から
天秤櫓は長濱城から太鼓門は佐和山城からそれぞれ移築したという。
豊臣方滅亡を家康は計画していた事から急いで彦根城を完成させたかったが井伊直政は鉄砲傷が元で死去。
キャラクターの「ひこにゃん」の事

彦根井伊家当主・直孝は武蔵国世田谷村でにわか雨に遭い広徳院の大木の下で雨宿りをしていると手招きをする白猫がいた。
近寄って行った直後に大木に落雷した。
直孝の命を救った白猫がマスコットキャラクターになったそうです。
2025年01月08日
佐八様墓がまだあるじゃん
設楽ダム建設によって多くの遺構が撤去されています。
また、移転される重要な遺構もあります、地元が残したいと言っても相手がある事ですからね。
磐城の国平藩安藤家の菜地だった向林村に廃藩置県によって磐城藩は消滅、藩士は帰郷せず残った者もいた。
その一人が山本佐八様だった。
彼は向林村の寺に住み子供に読み書き算盤を教えて亡くなった。
佐八様の墓

この墓も重要な地元の遺構であり移転する事になって撤去したと思っていたが未だに建っている。
早急に移転を願いたい、残土に埋められそうだ。
また、移転される重要な遺構もあります、地元が残したいと言っても相手がある事ですからね。
磐城の国平藩安藤家の菜地だった向林村に廃藩置県によって磐城藩は消滅、藩士は帰郷せず残った者もいた。
その一人が山本佐八様だった。
彼は向林村の寺に住み子供に読み書き算盤を教えて亡くなった。
佐八様の墓
この墓も重要な地元の遺構であり移転する事になって撤去したと思っていたが未だに建っている。
早急に移転を願いたい、残土に埋められそうだ。
2025年01月04日
初詣とオープンマイク田峯
初詣は田峯観音ーと言う事で行ってきた。


廻り舞台の所にこんな貼紙、ホスターがありました
オープンマイクだみね とあります

自分の好きな事を話して、踊って?歌って、漫才、落語、手品も好いらしい?
面白そうですね。
私なら「000の食べ方」(笑)
廻り舞台の所にこんな貼紙、ホスターがありました
オープンマイクだみね とあります
自分の好きな事を話して、踊って?歌って、漫才、落語、手品も好いらしい?
面白そうですね。
私なら「000の食べ方」(笑)

2025年01月02日
夷則軒?
嶋田陣屋の門が夷則軒に移転と聞き行く

ここって新城市稲木と豊栄の境辺りですね。
横に石仏があるから寺でしょう。

広い庭のよな境内?
そしてセンダンの木が隅にある

センダンは有毒という、、昔は虫除けに使われたyと聞いたことがある。
無雨量が続いて36日目になり候
ここって新城市稲木と豊栄の境辺りですね。
横に石仏があるから寺でしょう。
広い庭のよな境内?
そしてセンダンの木が隅にある
センダンは有毒という、、昔は虫除けに使われたyと聞いたことがある。
無雨量が続いて36日目になり候
2025年01月01日
新年にあたって
新年おめでとうございます
昨年はあなたにとって
如何なとしでしたか
今年もよろしく
お願いもうします
「勝頼退却の道」を発行して、多くの問い合わせをいただきありがとうございました。
案内した方からお礼の絵葉書を頂きました

新年早々ですが
しばらく「別荘」へ行くことになりました~
暫くして無事「帰還」で来ましたら
また、宜しくお願いします。
昨年はあなたにとって
如何なとしでしたか
今年もよろしく
お願いもうします
「勝頼退却の道」を発行して、多くの問い合わせをいただきありがとうございました。
案内した方からお礼の絵葉書を頂きました
新年早々ですが
しばらく「別荘」へ行くことになりました~
暫くして無事「帰還」で来ましたら
また、宜しくお願いします。
2024年12月31日
2024年もあとわずか
2024年度も数時間ですね、年々一年が早く過ぎる気がしますが私だけではないようです。
今年は「勝頼退却の道」冊子の件で遠方からもTEL頂き感謝しています。
また、博物館の方から
「今年最後のホームラン」と感謝の言葉を頂いたのが「磯丸不明石碑」発見でした

移転設置場所は決まっていますがダム建設が絡んでいますので移転完了は7~10年先になりそうです。
来年の事は?
一年、生きて頑張りますが・・・
ありがとうございました。
今年は「勝頼退却の道」冊子の件で遠方からもTEL頂き感謝しています。
また、博物館の方から
「今年最後のホームラン」と感謝の言葉を頂いたのが「磯丸不明石碑」発見でした
移転設置場所は決まっていますがダム建設が絡んでいますので移転完了は7~10年先になりそうです。
来年の事は?
一年、生きて頑張りますが・・・
ありがとうございました。
タグ :磯丸碑
2024年12月30日
再度探訪 野田
久しぶり可成り前にUPした新城市野田の島田陣屋跡を廻ったんです。
新しく豊川に架かった野田大橋工事で削られましたが・・・

今「しまむら」が建っている所に溜池がありましたね、チョット残っている?
嶋田氏は旧鳳来町の嶋田が出身だとか。
代官所が遠江の中泉代官所に併合され旗本嶋田氏(2千石)が陣屋を設置(1625年)から明治元年(1868年)まで11代242年間務めたという。
この石垣は平成の野田城大橋設置時に発掘し出て来た石で石垣を復元した。
屋舗図を見ると玄関門はこの辺りにあったようです、米倉などはこの中に

津島神社内の敷石2個は陣屋出入り口の敷石という。

陣屋の門は後で
津嶋神社

中市場清水場 大分伐採されました~

旅人の水飲み場、洗濯場として使用した
近くには渡船場が有って一鍬田へ渡っていた。
新しく豊川に架かった野田大橋工事で削られましたが・・・
今「しまむら」が建っている所に溜池がありましたね、チョット残っている?
嶋田氏は旧鳳来町の嶋田が出身だとか。
代官所が遠江の中泉代官所に併合され旗本嶋田氏(2千石)が陣屋を設置(1625年)から明治元年(1868年)まで11代242年間務めたという。
この石垣は平成の野田城大橋設置時に発掘し出て来た石で石垣を復元した。
屋舗図を見ると玄関門はこの辺りにあったようです、米倉などはこの中に
津島神社内の敷石2個は陣屋出入り口の敷石という。
陣屋の門は後で
津嶋神社
中市場清水場 大分伐採されました~
旅人の水飲み場、洗濯場として使用した
近くには渡船場が有って一鍬田へ渡っていた。
タグ :嶋田陣屋跡
2024年12月28日
不明の糟谷磯丸碑
発見できた「糟谷磯丸歌碑」
大きさは簡単に測定したのですが
土台約25cm 碑が67cm 計高さ92cm

土台幅 前80㎝ 奥域65㎝
次回はもうちょっと正確に測定してきます。
それにしても雨量がないもんで凄く乾燥していますね。
先月、11月26日に50mm降ってから32日間測定雨量0mmです。
インフルエンザが凄く流行しているそうですよ。
予防注射は23日に打っていますがどうでしょうか。
大きさは簡単に測定したのですが
土台約25cm 碑が67cm 計高さ92cm
土台幅 前80㎝ 奥域65㎝
次回はもうちょっと正確に測定してきます。
それにしても雨量がないもんで凄く乾燥していますね。
先月、11月26日に50mm降ってから32日間測定雨量0mmです。
インフルエンザが凄く流行しているそうですよ。
予防注射は23日に打っていますがどうでしょうか。
2024年12月27日
糟谷磯丸歌碑 見つかる
糟谷磯丸さんの田枯村(設楽町八橋)で読んだ歌碑が設樂ダム建設により沈没するため移転したはずが不明になった。結局処分をお願いした石工店にそのままあった。
表面は読めたが裏面を磨きましたが

まだ、磨き不足かよく読めない
白線に文字を書いた方の名前がある
宿泊先の今の主人と近くの歌愛好家の2名の名前は読めた。
設楽町へ連絡したところ
保存する方向で八橋の桜所に造成する公園に設置する事に、、、
公園完成はは10年先になります。私は生きていませんね~。
表面は読めたが裏面を磨きましたが
まだ、磨き不足かよく読めない
白線に文字を書いた方の名前がある
宿泊先の今の主人と近くの歌愛好家の2名の名前は読めた。
設楽町へ連絡したところ
保存する方向で八橋の桜所に造成する公園に設置する事に、、、
公園完成はは10年先になります。私は生きていませんね~。
2024年12月21日
磯丸の石碑の経緯
新城市副川で見つけた磯丸の石碑、なぜここに在るのか?状況が分かって来ました。
<石碑の裏側 昭和は分かりますが・・>

この近くの石工さん資材置き場、処分を頼まれ引き揚げて来たが磯丸さんの碑、処分しては勿体無いと思い置いていた。
「誰かが何か言ってくるだろうと思っていた」と店主
この磯丸さんの石碑のは設樂ダム建設によって移転を余儀なくされ処分を依頼され今は資材置き場に・・・・
これも何かの縁、何とかシナイと、ですよね。
約10年前に通りかかって「磯丸」の刻み文字を見て、今回は「田かれ村」の文字を読んでしまったから 「なにこれ?」になってしまった。
生まれ育った郷里の磯丸石碑、個人が建てた「磯丸石碑」。
磯丸は旅籠をしていたM家に泊ったようです。
Mさんは何処へ移転したか?尋ねないと。
<石碑の裏側 昭和は分かりますが・・>
この近くの石工さん資材置き場、処分を頼まれ引き揚げて来たが磯丸さんの碑、処分しては勿体無いと思い置いていた。
「誰かが何か言ってくるだろうと思っていた」と店主
この磯丸さんの石碑のは設樂ダム建設によって移転を余儀なくされ処分を依頼され今は資材置き場に・・・・
これも何かの縁、何とかシナイと、ですよね。
約10年前に通りかかって「磯丸」の刻み文字を見て、今回は「田かれ村」の文字を読んでしまったから 「なにこれ?」になってしまった。
生まれ育った郷里の磯丸石碑、個人が建てた「磯丸石碑」。
磯丸は旅籠をしていたM家に泊ったようです。
Mさんは何処へ移転したか?尋ねないと。
2024年12月18日
古伊那街道を探索
伊那街道の旧伊那街道、即ち江戸時代の初期古街道が民家の上にあって地元の方は古老から「大切にせよと」と言われていたという。私も伊那街道を(音羽町~根羽村)一往復しているが江戸時代末期の街道だったから古伊那街道に興味を持ち、ちょっと歩いてみたいと思っていた。
新城市副川、先日の長者で邪魔した地区へ行き古道を尋ねる。
砂防ダムの近くと聞き行く。見上げると棚山高原の西になるのか岩壁が落ちて来そうな地形だ。
<砂防ダムへ登る林道、車は無理、歩く>

<100m位登ったろうか石仏が岩の上に、道脇にあったここに集めたと言う>

古道はどこ?見渡すが砂防ダム建設で掘って地形が変化しているな~
沢に架かる橋から見渡すと上流に鳥居が見える、鳥居に来る元の道は砂防工事で消えている。
今は工事後の道で沢に沿ってあるが元は沢の左岸から右岸に渡りお参りしていたな、と思う。
古伊那街道は少し下がった民家辺りの上を通っていた?と推測し林道を上がって見下ろし痕跡を探すと・・あれか・・・・

(反対側、西を探索)
砂防ダムのある沢の一本西側の沢方向へ行くと民家があった。
古道を伺うと少し高い所にあると言う。 この先は地形から旧道は里に下がっているな。
続く
新城市副川、先日の長者で邪魔した地区へ行き古道を尋ねる。
砂防ダムの近くと聞き行く。見上げると棚山高原の西になるのか岩壁が落ちて来そうな地形だ。
<砂防ダムへ登る林道、車は無理、歩く>
<100m位登ったろうか石仏が岩の上に、道脇にあったここに集めたと言う>
古道はどこ?見渡すが砂防ダム建設で掘って地形が変化しているな~
沢に架かる橋から見渡すと上流に鳥居が見える、鳥居に来る元の道は砂防工事で消えている。
今は工事後の道で沢に沿ってあるが元は沢の左岸から右岸に渡りお参りしていたな、と思う。
古伊那街道は少し下がった民家辺りの上を通っていた?と推測し林道を上がって見下ろし痕跡を探すと・・あれか・・・・
(反対側、西を探索)
砂防ダムのある沢の一本西側の沢方向へ行くと民家があった。
古道を伺うと少し高い所にあると言う。 この先は地形から旧道は里に下がっているな。
続く
2024年12月17日
磯丸の碑がある?
伊那街道を探索していた時に道端に建っていたと記憶して脇道に入った所を捜して3回目にやっと見つけました。石柱と思っていた記憶と違い立派な石碑だった。
新城市副川地内旧道の脇に在ったのではなく石材店の置き場にある。
それは糟谷磯丸歌碑で、なぜここに在るのか?

石碑は預かっている?
文化十四年三月十五日 田かれ村
しなのや弥平方に旅の枕をむすふとて
よめる
秋ならは鹿のなき音もきかましを
春の田かれの里そ淋しき
磯丸
と読めるが、、、、、、
田枯村は設楽町八橋の旧村名前か?
なぜここに在るのでしょうか。
新城市副川地内旧道の脇に在ったのではなく石材店の置き場にある。
それは糟谷磯丸歌碑で、なぜここに在るのか?
石碑は預かっている?
文化十四年三月十五日 田かれ村
しなのや弥平方に旅の枕をむすふとて
よめる
秋ならは鹿のなき音もきかましを
春の田かれの里そ淋しき
磯丸
と読めるが、、、、、、
田枯村は設楽町八橋の旧村名前か?
なぜここに在るのでしょうか。
2024年12月16日
チョット寄っただけ
待ち合わせ時間を間違えて早く行ってしまったので時間調整に近くの[釜屋建物]をチョット」だけ見る。
新城市桜淵公園内の「釜屋」(かまや)建物、と言う、この建て方は豊川、天竜川流域にみられるそうです。
<左棟が母屋、右が釜屋、牛馬を飼う建物>

母屋と釜戸(くど)仕事場馬屋が別棟になっている建物を合体したっ建物。
私の実家も土間にはジャガイモ、サツマイモの保存用芋床が別々に蓋に厚板が敷いてあり、脱穀作業場できる広さがあった、牛も同じ土間の反対側に飼っていた。

実家の事ですが、土間内から見上げると馬屋などは継ぎ足しの建物である事がわかった。
この建物は約180~200年前の建物と説明文にあった。
内部の見学は連絡しないと戸が開きますん
新城市桜淵公園内の「釜屋」(かまや)建物、と言う、この建て方は豊川、天竜川流域にみられるそうです。
<左棟が母屋、右が釜屋、牛馬を飼う建物>
母屋と釜戸(くど)仕事場馬屋が別棟になっている建物を合体したっ建物。
私の実家も土間にはジャガイモ、サツマイモの保存用芋床が別々に蓋に厚板が敷いてあり、脱穀作業場できる広さがあった、牛も同じ土間の反対側に飼っていた。
実家の事ですが、土間内から見上げると馬屋などは継ぎ足しの建物である事がわかった。
この建物は約180~200年前の建物と説明文にあった。
内部の見学は連絡しないと戸が開きますん
2024年12月15日
JAの文化講座の続き
JA愛知東の講座続編です。
沈下橋の写真です
アニメで話題になって聖地j巡りになっている沈下橋に近く通過

蔦の滝(つたのたき)安山岩の岩床に滝ができた

旧田口線の駅はこの滝の上だった事から「滝上」の名前になった。
滝の横には「柱状節理」岩が横たわって」いた

四谷の千枚田 棚田百選にもなっている、今は400枚

上まで登ると言うので車で行った

明治37年(1904年)田植えが終わったころに20日の連続雨が降り上流谷間から山津波が発生し民家10棟11人多くの田畑を飲み込んだ大災害が発生した。
棚田は1296枚あったが現在は400枚。
春にはコノハズクの鳴き声が谷間に渡るという。
沈下橋の写真です
アニメで話題になって聖地j巡りになっている沈下橋に近く通過

蔦の滝(つたのたき)安山岩の岩床に滝ができた
旧田口線の駅はこの滝の上だった事から「滝上」の名前になった。
滝の横には「柱状節理」岩が横たわって」いた
四谷の千枚田 棚田百選にもなっている、今は400枚
上まで登ると言うので車で行った
明治37年(1904年)田植えが終わったころに20日の連続雨が降り上流谷間から山津波が発生し民家10棟11人多くの田畑を飲み込んだ大災害が発生した。
棚田は1296枚あったが現在は400枚。
春にはコノハズクの鳴き声が谷間に渡るという。
2024年12月12日
仇討ち、渋谷金王丸
新城市玖老勢に金王(こんのう)と言う地区があります。
あの渋谷金王丸を祀った祠がある。
地区には渋谷家が数軒ある、訪ねた方が渋谷さんで「久しぶりに渋谷金王丸を尋ねる方に逢った」と話「あそこ」と教えて頂く。
平治の乱(1159年)源義朝と平清盛の戦い、義朝は戦い敗れ京から東国への敗走中、知多の野間内海の長田忠致(ただむね)宅に泊る。
長田は後で平氏の仕返しを恐れ入浴中を襲い殺す。長田は恩賞を当てに平清盛に首を届けると清盛は源氏家臣の長田が源氏に反逆した事を激怒し長田に追手を出した。

一方主君を討たれた源義朝家臣の渋谷金王丸は長田を追って殺生禁止の鳳来寺まで来たが寺に逃げ込み手が出ない。出て来たならばらば討とうと山麓に住み機会を伺ったが願叶わずこの地で没したという。
最上段の祠

義朝は頼朝の父親である事は知っていることでしょう。
伝説地は各所にありますね。
あの渋谷金王丸を祀った祠がある。
地区には渋谷家が数軒ある、訪ねた方が渋谷さんで「久しぶりに渋谷金王丸を尋ねる方に逢った」と話「あそこ」と教えて頂く。
平治の乱(1159年)源義朝と平清盛の戦い、義朝は戦い敗れ京から東国への敗走中、知多の野間内海の長田忠致(ただむね)宅に泊る。
長田は後で平氏の仕返しを恐れ入浴中を襲い殺す。長田は恩賞を当てに平清盛に首を届けると清盛は源氏家臣の長田が源氏に反逆した事を激怒し長田に追手を出した。
一方主君を討たれた源義朝家臣の渋谷金王丸は長田を追って殺生禁止の鳳来寺まで来たが寺に逃げ込み手が出ない。出て来たならばらば討とうと山麓に住み機会を伺ったが願叶わずこの地で没したという。
最上段の祠
義朝は頼朝の父親である事は知っていることでしょう。
伝説地は各所にありますね。
2024年12月11日
持仏長者を尋ねて
新城市副川地区、持仏長者なる者は?
道路脇の民家に飛込伺うと知らないという。「字持仏前」の住所だから何か知る人がいてもと道路上の家を尋ねると「ここで一番古い家と言いながら態態(わざわざ)戸口まで案内して頂く。
持仏長者の屋敷は?と切り出すと「家の裏です、と案内して頂く。
<屋敷跡、綺麗だ、井戸もある>

屋舗北山手にお寺が約90年前にはあった聞く、名前は忘れたという>桃渓庵か小林寺か?
高い所に寺が在り少し離れた所に寺墓がある。
粗末な五輪塔は百姓が祀った落武者の墓か?

前方の林内にお寺があったという

長者は小林家といって言いのか、分家の末裔か。
一族の繁栄を願う仏像絵画彫刻像などを先祖供養、お堂を屋敷内に建てて祀った。
自力で仏像を持ち祀る事は財力ないと出来ませんね。
長者宅は火災で焼失したと云います。
信州から来た飯田市の小林城の武士だった、また近江源氏の出で織田家の家臣だったが武者修行中に双瀬に留まったとも云う。
そうそう、戦国時代までの伊那街道はここの上を通っていたと云う。
この事が伊那街道探索時の疑問(2015年ごろの)に繋がる。
道路脇の民家に飛込伺うと知らないという。「字持仏前」の住所だから何か知る人がいてもと道路上の家を尋ねると「ここで一番古い家と言いながら態態(わざわざ)戸口まで案内して頂く。
持仏長者の屋敷は?と切り出すと「家の裏です、と案内して頂く。
<屋敷跡、綺麗だ、井戸もある>
屋舗北山手にお寺が約90年前にはあった聞く、名前は忘れたという>桃渓庵か小林寺か?
高い所に寺が在り少し離れた所に寺墓がある。
粗末な五輪塔は百姓が祀った落武者の墓か?
前方の林内にお寺があったという
長者は小林家といって言いのか、分家の末裔か。
一族の繁栄を願う仏像絵画彫刻像などを先祖供養、お堂を屋敷内に建てて祀った。
自力で仏像を持ち祀る事は財力ないと出来ませんね。
長者宅は火災で焼失したと云います。
信州から来た飯田市の小林城の武士だった、また近江源氏の出で織田家の家臣だったが武者修行中に双瀬に留まったとも云う。
そうそう、戦国時代までの伊那街道はここの上を通っていたと云う。
この事が伊那街道探索時の疑問(2015年ごろの)に繋がる。
2024年12月10日
便福長者
平安時代から室町時代のに豪族であって傲慢な生活をしていたようです。
新城市玖老勢の長者は便福(びんぷく)長者と言われていたそうです。便福とは貴族のしていた耳髪形だそうです。
新城市玖老勢の鳳来こども園の北に字便福と言う地名あり。
髪形の便福は貴族系の者がしたから貴族系の長者だったか?
<今は畑か防網み覆われて中には入れません>

<園よりに通路があるがいつの時代のものか?>

長者になった者は地方へ下った貴族か都から落ち来た者か定かではないが腕力が物言った事は今の時代も同じ気がする。
いつの時代に栄えたかはっきりしない、名前も不明、決定的証拠なき伝説長者です。
新城市玖老勢の長者は便福(びんぷく)長者と言われていたそうです。便福とは貴族のしていた耳髪形だそうです。
新城市玖老勢の鳳来こども園の北に字便福と言う地名あり。
髪形の便福は貴族系の者がしたから貴族系の長者だったか?
<今は畑か防網み覆われて中には入れません>
<園よりに通路があるがいつの時代のものか?>
長者になった者は地方へ下った貴族か都から落ち来た者か定かではないが腕力が物言った事は今の時代も同じ気がする。
いつの時代に栄えたかはっきりしない、名前も不明、決定的証拠なき伝説長者です。
2024年12月09日
稲木長者はこの辺か
稲木長者住居地は何処か確認に、地元の方伺うと「あの辺りで発掘をしていた」と聞いたのは新城市稲木地区の県道21号野田川に架かる八幡橋の上流、2つ目の腰廻橋右岸の辺り、看板が有るが山手にある。
看板の手前?の野田川よりか?
<県道21号から北西方向を写す、突き当りに看板ある>

看板に図面などは表示、発掘跡の表示もない。林の中?いや畑になっている手前の所か?

突き当りの手前、右側が跡ようです。
稲木長者は10世紀中から11世紀末ごろに膨大な私有地を持ち裕福な生活をしていたようだ。
しかし、土地は国の物、から武力で取り上げた?居なくなったか。
この辺りは熱田神宮菜地だったようだから違法な荘園は没収されたか?
人物は誰か?はっきりしない、文章がない、依田氏?かは分からないという。
(写真3枚目が容量満タンで記載できず)
看板の手前?の野田川よりか?
<県道21号から北西方向を写す、突き当りに看板ある>
看板に図面などは表示、発掘跡の表示もない。林の中?いや畑になっている手前の所か?
突き当りの手前、右側が跡ようです。
稲木長者は10世紀中から11世紀末ごろに膨大な私有地を持ち裕福な生活をしていたようだ。
しかし、土地は国の物、から武力で取り上げた?居なくなったか。
この辺りは熱田神宮菜地だったようだから違法な荘園は没収されたか?
人物は誰か?はっきりしない、文章がない、依田氏?かは分からないという。
(写真3枚目が容量満タンで記載できず)
2024年12月06日
稲木長者は何処に住んでいた?
少し前に双瀬の長者,持仏長者の事に少し触れましたが新城市稲木に稲木長者がいたという。
長者と云うのは傲慢で発言力があり腕力で抑え込む、百姓を土地で働かせて裕福な生活をしていたようだ。
稲木長者は何処に住んでいたのだろうか?新城教育委員会などの著書を読み判断すると
<稲木・県道21号方向を見る、右に八幡神社の森が写る,県道の北辺りか?

稲木とは稲を刈り置く、倉庫があったから?諸説あるようです
<長者の名は諏訪、又は依田と云う>

長者と云うのは傲慢で発言力があり腕力で抑え込む、百姓を土地で働かせて裕福な生活をしていたようだ。
稲木長者は何処に住んでいたのだろうか?新城教育委員会などの著書を読み判断すると
<稲木・県道21号方向を見る、右に八幡神社の森が写る,県道の北辺りか?
稲木とは稲を刈り置く、倉庫があったから?諸説あるようです
<長者の名は諏訪、又は依田と云う>
2022/06/21
19日のつづきです。 源頼朝公の曾祖母「松御前」の墓(碑)があると云う新城市稲木・豊栄境界辺りの城ケ峰山へ登る。 山頂に頼朝公の座像が鎮座 像は乗本地区の梶村さん贈県道21号三河カントリークラブの北にある城ケ峰山にあると聞く。カントリーの西を車で進むと柵があり開閉赤(図丸)して右に金網柵…