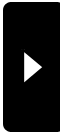2024年10月07日
講演・長篠合戦への途(みち)
記念講演会・長篠城址 会館60周年
のチラシがあった。

会館60年、合戦から来年で450年と節目ですね。
11月2日(土)13:30~15:30
QRコード、オンライン申し込み
80人ほど 先着順
10月18日まで 80人ほど、とあります。
会場は
新城市鳳来総合支所
市民センターほうらい集会室
合戦後の勝頼はどうしたかは?
私の探索し販売している本
まさかの武田敗軍
「勝頼退却の道」を辿る を読んで下さい。
長篠城址史跡保存館・設樂原歴史資料館
道の駅したら
にて販売中
のチラシがあった。
会館60年、合戦から来年で450年と節目ですね。
11月2日(土)13:30~15:30
QRコード、オンライン申し込み
80人ほど 先着順
10月18日まで 80人ほど、とあります。
会場は
新城市鳳来総合支所
市民センターほうらい集会室
合戦後の勝頼はどうしたかは?
私の探索し販売している本
まさかの武田敗軍
「勝頼退却の道」を辿る を読んで下さい。
長篠城址史跡保存館・設樂原歴史資料館
道の駅したら
にて販売中
2024年02月21日
花祭りの歌
東栄町の親戚宅に寄ったんです。
「花祭り歌ぐら」が木板に書かれていた。
歌があるとは知らなかったよ。


「歌ぐら」とは?聞くの忘れてた。
「歌くらべ」ではないですよね?。
長い歌らしいです。
20日 14.7-23,5℃ 晴曇り深夜雨10mm
「花祭り歌ぐら」が木板に書かれていた。
歌があるとは知らなかったよ。

「歌ぐら」とは?聞くの忘れてた。
「歌くらべ」ではないですよね?。
長い歌らしいです。
20日 14.7-23,5℃ 晴曇り深夜雨10mm
2022年07月15日
時代は変われ度、これ美徳?
先日、JA愛知東の文化講座を受講しました。「年中行事と祝いの食事」講師は東三民俗談話会伊東文弘先生でした。
年中行事とは集団で毎年同じ次期に同じ方法で繰り返しおこなう伝統行事をいう。から始まり,農耕社会ですから作物の成長合わせて働き休息し祝いをし、民俗学では働く日を「ケ」といい普通の日とする。祝の日を「ハレ」という。御馳走を食べ晴れ着て行事に参加する。
これらの行事慣習は古代中国から伝わったもので奈良時代、推古天皇の時代、607年聖徳太子が中国へ遣隋使として小野妹子らによって日本に伝わったと言います。箸も伝わったそうです。
酒は「ミキ」ミワといい神と人が交歓、互いに楽しむために飲んだ。酒は粥を女性が嚙み瓶に戻す、主婦の仕事で刀自(とじ)いった。酒造り職人を杜氏(とうじ)という。
箸作法として 握り箸、刺し箸、込み箸、ねぶり箸、涙箸、嚙み箸、寄せ箸、迷い箸、移り箸、探り箸、から箸はしてはいけない事。
頂いた資料から 箱膳いろいろ

私の家は、子供のころは食事は御爺様は一人畳式で箱膳で食事、頭からユゲを出しながら、やかん頭だった。
魚の骨は七輪であぶってコリコリ食べていた御爺様でした。
私らは板の間御座式でカシコマリ食事でした、足が痛かった。
食器茶碗はお茶入れ沢庵で綺麗にして、飲まないと叱られた。
食べ物はすべて残さない、が決まりだったな~あ
サンマの食べ方作法は妻以外は上手にたべます。
この「たくあん作法」を小学生の子供にしました、40才代になった子供が時々するそうです。
これって現代社会では美徳でしょうか?
12日 24.3℃ー26.0℃ 雨 56mm 1人
13日 23.1℃ー32.5℃ 晴れ曇り
14日 24.7℃ー29.7℃ 雲りあめ 40mm
15日 23.5℃ー26.3℃ 雨晴れ間もあったが 60mm
年中行事とは集団で毎年同じ次期に同じ方法で繰り返しおこなう伝統行事をいう。から始まり,農耕社会ですから作物の成長合わせて働き休息し祝いをし、民俗学では働く日を「ケ」といい普通の日とする。祝の日を「ハレ」という。御馳走を食べ晴れ着て行事に参加する。
これらの行事慣習は古代中国から伝わったもので奈良時代、推古天皇の時代、607年聖徳太子が中国へ遣隋使として小野妹子らによって日本に伝わったと言います。箸も伝わったそうです。
酒は「ミキ」ミワといい神と人が交歓、互いに楽しむために飲んだ。酒は粥を女性が嚙み瓶に戻す、主婦の仕事で刀自(とじ)いった。酒造り職人を杜氏(とうじ)という。
箸作法として 握り箸、刺し箸、込み箸、ねぶり箸、涙箸、嚙み箸、寄せ箸、迷い箸、移り箸、探り箸、から箸はしてはいけない事。
頂いた資料から 箱膳いろいろ
私の家は、子供のころは食事は御爺様は一人畳式で箱膳で食事、頭からユゲを出しながら、やかん頭だった。
魚の骨は七輪であぶってコリコリ食べていた御爺様でした。
私らは板の間御座式でカシコマリ食事でした、足が痛かった。
食器茶碗はお茶入れ沢庵で綺麗にして、飲まないと叱られた。
食べ物はすべて残さない、が決まりだったな~あ
サンマの食べ方作法は妻以外は上手にたべます。
この「たくあん作法」を小学生の子供にしました、40才代になった子供が時々するそうです。
これって現代社会では美徳でしょうか?
12日 24.3℃ー26.0℃ 雨 56mm 1人
13日 23.1℃ー32.5℃ 晴れ曇り
14日 24.7℃ー29.7℃ 雲りあめ 40mm
15日 23.5℃ー26.3℃ 雨晴れ間もあったが 60mm
2020年06月16日
まゆ(繭)掻き
蚕が繭を作り始めて一週間、まゆ掻きが行なわれた。

回転繰から繭を取り出す



繭の毛羽も取れてくる

養蚕の神 蚕玉様(こだまさま)萬機姫(よろずはたひめ)

手に桑の葉と繭を持っている
繭から絹糸にするが作業は外注に出す、伊勢神宮に神御衣(かんみそ)として絹糸を献納する
渡来人の秦氏が中国から伝えた養蚕、秦氏は税として絹を朝廷に沢山積み上げた事から、「兎喜麻佐・うつまさ」の姓を賜った。住地を「うつまさ」と呼んだ。いつごらからか「太秦・うずまさ」になった。豊川市の菟足神社、秦氏と関係あるようです。
関連記事 多数あり
16日 晴れ 21℃ - 32℃
回転繰から繭を取り出す
繭の毛羽も取れてくる
養蚕の神 蚕玉様(こだまさま)萬機姫(よろずはたひめ)
手に桑の葉と繭を持っている
繭から絹糸にするが作業は外注に出す、伊勢神宮に神御衣(かんみそ)として絹糸を献納する
渡来人の秦氏が中国から伝えた養蚕、秦氏は税として絹を朝廷に沢山積み上げた事から、「兎喜麻佐・うつまさ」の姓を賜った。住地を「うつまさ」と呼んだ。いつごらからか「太秦・うずまさ」になった。豊川市の菟足神社、秦氏と関係あるようです。
関連記事 多数あり
2015/10/14
今日で掃き立の日から34日め、繭(まゆ)の出荷日です。 奇麗な繭になっています、中には蚕が蛹(さなぎ)になっている。 繭を振るとコツコツ音がする 蛹の事を「ドッチ」と呼んでいます 卵、10g、2万匹を飼育しましたから2万個余りの繭 遅く繭作りした繭は完全な蛹になるまでこのまま 2匹…
2015/10/07
蚕さまの守護神は蚕玉様(こだまさま)と言われ京都の木島(このしま)神社に養蚕神社、蚕社が祀られ萬機姫(よろずはたひめ)が主神。 蚕玉様 左手に桑の葉、右手に繭を持っているようです。 養蚕は他説ありますが「日本書記」に弥生時代に中国から伝承されたと云わり渡来人秦氏は養蚕技術を持った一族であ…
2013/07/03
お糸船出航 伊勢神宮の神御衣(かんみそ)になる絹糸献納へ (乗船前の御祓い) 3日午前、田原市伊良湖フェリー乗り場で、優れた絹糸「三河赤引糸」の修祓式がおこなわれ最も優れた絹糸であることを意味する「大一御用伊勢神宮」の旗を先頭にフェリー船をお糸船にして伊勢神宮へ向かった。 (大一御用…
16日 晴れ 21℃ - 32℃
2020年02月15日
黒倉田楽 設楽町で
設楽町の黒倉田楽が16日、13時から行われます。
室町時代から設楽町平山黒倉地区に農耕作業が田楽として伝承されています。
2018年の写真

日時 2020年2月16日(日) 13時から (15時半ごろまで?気がする)
場所 愛知県北設楽郡設楽町平山字釜ノ沢4
関連記事
15日 7℃ - 15℃ 曇り 暖かいです
室町時代から設楽町平山黒倉地区に農耕作業が田楽として伝承されています。
2018年の写真

日時 2020年2月16日(日) 13時から (15時半ごろまで?気がする)
場所 愛知県北設楽郡設楽町平山字釜ノ沢4
関連記事
15日 7℃ - 15℃ 曇り 暖かいです
2020年01月03日
梵鐘にお参り 初詣は田峯観音様
例年初詣は田峯の観音様へお参りに行っています。三が日にお参りした事はありませんでしたが昨日参拝。


本堂の脇にある梵鐘 災い災難から守る鐘

先の大戦で供出を免れた鐘 重要文化財です
文明13年(1481、538年前)田峯城主・菅沼定信が寄進

甘酒を頂く

鐘楼で打ち鳴らす 打つ木を撞木(しゅもく)と言うそうです

帰りに新東名下りの設樂原㎩に立ち寄る

友人とパッタリ出会う、信長公本陣散歩の方が多いですね。
乗り物姿勢は疲れますから適度な運動に本陣跡探索良いですね。
2日 5℃ - 13℃ 晴れ
本堂の脇にある梵鐘 災い災難から守る鐘
先の大戦で供出を免れた鐘 重要文化財です
文明13年(1481、538年前)田峯城主・菅沼定信が寄進
甘酒を頂く
鐘楼で打ち鳴らす 打つ木を撞木(しゅもく)と言うそうです
帰りに新東名下りの設樂原㎩に立ち寄る
友人とパッタリ出会う、信長公本陣散歩の方が多いですね。
乗り物姿勢は疲れますから適度な運動に本陣跡探索良いですね。
2日 5℃ - 13℃ 晴れ
2019年11月30日
便乗して甲冑を展示します
12月1日から27日まで新城市門谷の愛称:観来館(みにこんかん)、鳳来寺山歴史文化考証館にてダンボールで作製した甲冑を展示することになったんです。
近くの方が観来館に展示観賞に行った時に12月の展示が空いていると聞き自身が描く「石猫」を展示すると決めてきたのです。石猫とは河原に転がっている丸い石に猫を描くものですが石の形によって色々な表情を描いて楽しんでいます。妻の友達であって「石猫だけでは展示スペースが勿体ない」「旦那の手作り甲冑を一緒に展示したら」と妻に話があり急遽、観るに堪えないダンボール手作り甲冑二領を展示することにしました。
館に貼る手作りポスター

館、入り口のポスター台も作る

能書き、甲冑着用して古道で撮った写真も展示する

ガード、写真展示台も作製する

と、言うことで30日午後から観来館で展示準備します。
観来館 0536-35-1494
12月から3月まで 月曜日、火曜日が休館
午前10時から午後3時まで開館です
29日 5.5℃ - 14℃ 快晴無風
近くの方が観来館に展示観賞に行った時に12月の展示が空いていると聞き自身が描く「石猫」を展示すると決めてきたのです。石猫とは河原に転がっている丸い石に猫を描くものですが石の形によって色々な表情を描いて楽しんでいます。妻の友達であって「石猫だけでは展示スペースが勿体ない」「旦那の手作り甲冑を一緒に展示したら」と妻に話があり急遽、観るに堪えないダンボール手作り甲冑二領を展示することにしました。
館に貼る手作りポスター
館、入り口のポスター台も作る
能書き、甲冑着用して古道で撮った写真も展示する
ガード、写真展示台も作製する
と、言うことで30日午後から観来館で展示準備します。
観来館 0536-35-1494
12月から3月まで 月曜日、火曜日が休館
午前10時から午後3時まで開館です
29日 5.5℃ - 14℃ 快晴無風
2019年06月09日
雨も上がってウォーキング 豊川リバーウォーク
8日の土曜日、前日の雨も上がって本年2回目の豊川リバーウォーク、ウォーキングが有りました。今回は新城市の「四谷の千枚田」です。
豊橋鉄道田口行きの定期バスで滝上バス停下車。バス停上の田口線廃線トンネル口にて開会式をしました。

さあ、ウォーキング開始、と脇に立っていたポールの天辺に竹ホウキのような物が有るんです。

何か祭りに使った?物のようです

疑問に思ったのでウォークは出発しましたが近くの民家に聞いたのです。
「風まつり」に使ったもとの事。嵐が来る210日頃に、今でいう台風シーズンに農作物の被害が無いように祈る時に建てたそうです。
上り口に石仏

弘法様 天王様 津島様 猿田彦様、天照様等が祀られています。
19℃ - 22℃ 雨、曇り 雨量約37mm
豊橋鉄道田口行きの定期バスで滝上バス停下車。バス停上の田口線廃線トンネル口にて開会式をしました。
さあ、ウォーキング開始、と脇に立っていたポールの天辺に竹ホウキのような物が有るんです。
何か祭りに使った?物のようです
疑問に思ったのでウォークは出発しましたが近くの民家に聞いたのです。
「風まつり」に使ったもとの事。嵐が来る210日頃に、今でいう台風シーズンに農作物の被害が無いように祈る時に建てたそうです。
上り口に石仏
弘法様 天王様 津島様 猿田彦様、天照様等が祀られています。
19℃ - 22℃ 雨、曇り 雨量約37mm
2019年04月07日
桜を見に行こう 満開です八橋ウバヒガン桜
設楽町、ほゞ満開の「八橋のウバヒガン桜」です。9日までは観賞できそうです。
昨日、午前11時頃に着、観賞に三々五々多くの方が観えます。
名古屋からバイクで、知立市から家族でと様々ですが多いのが豊橋市と浜松市の方でした。


家族でお弁当を広げる方、さくらとワンちゃんを撮影する方と様々ですが「ここはダムで沈まないですか?」の質問が多かったです。
皆さん心配しているようですね。沈みません、ここは町の公園が建設されます。
<国交省の予定図>設楽町八橋字崩沢のウバヒガン桜の位置


境川の右岸県道10号線(津具、長野県根羽村線)が少し高い所に移設されます、そこから境川を跨ぎ桜の真下まで橋が架けられます。
時計を見ると15時近し、4時間も来訪者と説明、世間話をしていました。
約80~100人近くの桜観賞者が来ました、花見団子を売る?


-
昨日、午前11時頃に着、観賞に三々五々多くの方が観えます。
名古屋からバイクで、知立市から家族でと様々ですが多いのが豊橋市と浜松市の方でした。
家族でお弁当を広げる方、さくらとワンちゃんを撮影する方と様々ですが「ここはダムで沈まないですか?」の質問が多かったです。
皆さん心配しているようですね。沈みません、ここは町の公園が建設されます。
<国交省の予定図>設楽町八橋字崩沢のウバヒガン桜の位置
境川の右岸県道10号線(津具、長野県根羽村線)が少し高い所に移設されます、そこから境川を跨ぎ桜の真下まで橋が架けられます。
時計を見ると15時近し、4時間も来訪者と説明、世間話をしていました。
約80~100人近くの桜観賞者が来ました、花見団子を売る?


-
2019年04月05日
今度の日曜日 奥三河パワートレイル大会
茶臼山から湯谷温泉までの山岳道を駆け抜ける「奥三河パワートレイル大会」が7日開催されます。

ドライブするのもカーブが多くて大変です、石がゴロゴロして階段、垂直ハシゴを登ったり下りたりの岩古谷山がコースになっています。
怪我のないよう参加者、応援隊の皆さん頑張って下さい。
私、日曜日は公民館清掃と豊橋市用事がであるもんで応援行けないのです。
4日 5℃ - 16℃ 晴れ
5日 8℃ -
ドライブするのもカーブが多くて大変です、石がゴロゴロして階段、垂直ハシゴを登ったり下りたりの岩古谷山がコースになっています。
怪我のないよう参加者、応援隊の皆さん頑張って下さい。
私、日曜日は公民館清掃と豊橋市用事がであるもんで応援行けないのです。
4日 5℃ - 16℃ 晴れ
5日 8℃ -
タグ :奥三河パワートレイル大会岩古谷山
2019年03月31日
八橋ウバヒガン桜の下で 桜観会
最近の冷えに開花時期が心配された「八橋のウバヒガン桜」、気温6度の八橋、桜は全体に紅色なっていました。三分咲でしょうか。3日後には満開になりそうですね。

集合写真



今年は近年にない懐かしい方との出会いがありました、50年ぶりに逢った、イヤ60年にと顔を見ても誰か解からないのです。可愛かった面影は昔のこと、人伝手に聞き「身元が判明」すると言うことがアッチコッチでありました。
「八橋ウバヒガン桜を愛する会」の方の無料五平餅、焼き肉等のオモテナシがありました。



お爺さんがここに桜の木を植えた遠山さんも奈良県から

画家の遠山唯一さんは叔父さん?だったと思う。
私の婆様は唯一(ただかず)と呼んでいました。叔母がモデルになった「椎茸取り」画があるそうですが拝見した事は有りません、一度観たいものです。
来年も桜観に来れば懐かしい何方に逢えることでしょう。
ダム建設で八橋区全住民は移転した、設楽町長さんが「何年後には町の公園としてこの桜を中心に整備する」との挨拶がありました。
廃村によって電気、携帯中継アンテナも無くなってしまいました。仕事に差し支えるし観光に来ても携帯が使えないなんて・・・町役場も知らない内に山奥環境になったそうです。
関連記事
7℃ - 16℃ 設楽町 曇り小雨
集合写真
今年は近年にない懐かしい方との出会いがありました、50年ぶりに逢った、イヤ60年にと顔を見ても誰か解からないのです。可愛かった面影は昔のこと、人伝手に聞き「身元が判明」すると言うことがアッチコッチでありました。
「八橋ウバヒガン桜を愛する会」の方の無料五平餅、焼き肉等のオモテナシがありました。
お爺さんがここに桜の木を植えた遠山さんも奈良県から
画家の遠山唯一さんは叔父さん?だったと思う。
私の婆様は唯一(ただかず)と呼んでいました。叔母がモデルになった「椎茸取り」画があるそうですが拝見した事は有りません、一度観たいものです。
来年も桜観に来れば懐かしい何方に逢えることでしょう。
ダム建設で八橋区全住民は移転した、設楽町長さんが「何年後には町の公園としてこの桜を中心に整備する」との挨拶がありました。
廃村によって電気、携帯中継アンテナも無くなってしまいました。仕事に差し支えるし観光に来ても携帯が使えないなんて・・・町役場も知らない内に山奥環境になったそうです。
関連記事
7℃ - 16℃ 設楽町 曇り小雨
2019年03月21日
豊橋市図書館の続・ふるさとしろめぐり
17日まで豊橋市中央図書館、資料室にて展示されていた「続・ふるさと城めぐり」展に17日午後に行って来ました。

写真パネルでの岩村城址、犬山城、陣屋等の紹介
吉田城の御殿模型(模型は撮影可、他はだめでした)


こと細かく造られています

左から御白書院、車寄、御広間
新城市の中山砦の写真パネルがありました。
11℃ - 17℃ 小雨 雨量約 17mm
写真パネルでの岩村城址、犬山城、陣屋等の紹介
吉田城の御殿模型(模型は撮影可、他はだめでした)
こと細かく造られています
左から御白書院、車寄、御広間
新城市の中山砦の写真パネルがありました。
11℃ - 17℃ 小雨 雨量約 17mm
2019年02月20日
三遠南信道の佐久間IC~東栄町IC開通記念ウォーキング
長野県飯田市の中央自動車道から浜松市北区の新東名自動車道間、約100kmを結ぶ自動車専用道路、三遠南信自働車道の佐久間IC~東栄IC(6.9km)が3月2日(日)に開通します。プレイベントとして24日(日)1km間の道路を10時~14時ウォーキングできます。

会場は東栄IC 駐車場は東栄小学校北側 無料シャトルバス運行(7分毎運行)

イベントは


地域物産展は東栄小学校駐車場内で開催とあります


駐車場:東栄小学校北側
住所 愛知県北設楽郡東栄町大字本郷字上桜平28-1付近
新東名ウォーキングほどは混まないとは思いますが・・・
問合せは 053-457-2427 平日10時~17時 (土日祝を除く)
浜松市土木部道路企画課
19日 7℃ - 9.5℃ 雨のちはれ 雨量約20mm
20日 10℃ - 20℃ はれ
会場は東栄IC 駐車場は東栄小学校北側 無料シャトルバス運行(7分毎運行)
イベントは
地域物産展は東栄小学校駐車場内で開催とあります
駐車場:東栄小学校北側
住所 愛知県北設楽郡東栄町大字本郷字上桜平28-1付近
新東名ウォーキングほどは混まないとは思いますが・・・
問合せは 053-457-2427 平日10時~17時 (土日祝を除く)
浜松市土木部道路企画課
19日 7℃ - 9.5℃ 雨のちはれ 雨量約20mm
20日 10℃ - 20℃ はれ
2018年11月07日
豊川流域圏を知る 4回の2 東栄町の山林の現状
豊川流域圏を知る4回目の2です。東栄町を訪れています。
食事は東栄町下田の料理旅館・大崎屋さんでジビエ料理を頂きました。

大崎屋さんは創業築ともに130年、建物は現状を維持しようと頑張っているそうです

窓からは振草川が丸見え

この部屋は民俗学者の柳田国男や実業家の渋沢敬三、早川孝太郎、折口信夫諸氏が宿泊した。食事をしながら「ひじり会」の活動を佐々木様から伺う

食後は町内、足込地内の森林管理の状況を鷹氏様から現地説明 間伐をしないと下草が生えない、保水力ナシ、土が流れる

間伐した林 陽射しが注ぐ

明るくて道路も走りやすいですね
間伐は一部の人のためではなく、地域を思うこと、行政や森林組合に任せるのではダメ、県が「あいち森と緑づくろ環境活動・学習事業」を薦めたから地域住民が行動することが大切なのですね。
次回は「木の駅プロジェクト」と豊川用水振草頭首工
つづく
14℃ -23℃ 晴れ (6日の記事を誤って消去した )
)
食事は東栄町下田の料理旅館・大崎屋さんでジビエ料理を頂きました。
大崎屋さんは創業築ともに130年、建物は現状を維持しようと頑張っているそうです
窓からは振草川が丸見え
この部屋は民俗学者の柳田国男や実業家の渋沢敬三、早川孝太郎、折口信夫諸氏が宿泊した。食事をしながら「ひじり会」の活動を佐々木様から伺う
食後は町内、足込地内の森林管理の状況を鷹氏様から現地説明 間伐をしないと下草が生えない、保水力ナシ、土が流れる
間伐した林 陽射しが注ぐ
明るくて道路も走りやすいですね
間伐は一部の人のためではなく、地域を思うこと、行政や森林組合に任せるのではダメ、県が「あいち森と緑づくろ環境活動・学習事業」を薦めたから地域住民が行動することが大切なのですね。
次回は「木の駅プロジェクト」と豊川用水振草頭首工
つづく
14℃ -23℃ 晴れ (6日の記事を誤って消去した
 )
) 2018年11月04日
豊川流域圏を知る 4回の1 東栄町大千瀬川から豊川へ
「あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業」の4回目、最後のコース東栄町へ行く。このコースも定員をオーバーする24人が参加、天候が心配されたが雨は見学終了後にパラパラして来た。
東栄町古戸(ふっと)の「古戸会館」へ行く

東栄町森林組合、古戸ひじり会の青山様から地域、森林について説明

会館内には舞庭(まいど)があり、天上には飾り取付がある、竃(かまど)は田んぼの土を固めて造るという

ひじり会、伊藤さんの案内、「村行の七滝」へ
林に埋れていた滝を整備する 国道151号の脇にある

昔、村人が滝に打たれ浄心、祈願した、上流に全七つある

国道に看板と駐車場がある

県が「あいち森と緑づくり森林整備事業」の説明が平成20年9月20日古戸地区であった。森林は手入れが出来ず困っていた時の話だった。
1 個人では出来ない、負担金無しで森林整備ができる
2 公道沿いの森林整備により視界が良くなる
3 地区内の景観の向上
4 地域の労働力を雇用できる
5 間伐材活用事業ができる
6 森林で埋れたいた自然、滝沢、大木が再発見できる
等、地域の活性化に繋がると思った。願ってもないチャンスと捉え事業の推進組織「森林事業古戸推進会」をその席で立ち上げた。
取り組みは簡単ではなく
県町、森林組合の協力がなかったら出来ない、対象山の調査(字、番地、所有者)、説明、現地の山境界確認、大小1.000筆あり地元の所有者が95%だった事が判明し事業推進活力になった。
古戸ひじり会は古戸地域の散策マップを作製し「花祭りゆかりコース」「願かけ・パワースポット巡り」「景勝地巡りコース」を案内している。
白山神社の索道(ロープウェイ)のことと、神社が花祭りの原形と係わっているという
関連記事
15℃ - 21℃ 曇り PM3時過ぎ雨(東栄町)
東栄町古戸(ふっと)の「古戸会館」へ行く
東栄町森林組合、古戸ひじり会の青山様から地域、森林について説明
会館内には舞庭(まいど)があり、天上には飾り取付がある、竃(かまど)は田んぼの土を固めて造るという
ひじり会、伊藤さんの案内、「村行の七滝」へ
林に埋れていた滝を整備する 国道151号の脇にある
昔、村人が滝に打たれ浄心、祈願した、上流に全七つある
国道に看板と駐車場がある
県が「あいち森と緑づくり森林整備事業」の説明が平成20年9月20日古戸地区であった。森林は手入れが出来ず困っていた時の話だった。
1 個人では出来ない、負担金無しで森林整備ができる
2 公道沿いの森林整備により視界が良くなる
3 地区内の景観の向上
4 地域の労働力を雇用できる
5 間伐材活用事業ができる
6 森林で埋れたいた自然、滝沢、大木が再発見できる
等、地域の活性化に繋がると思った。願ってもないチャンスと捉え事業の推進組織「森林事業古戸推進会」をその席で立ち上げた。
取り組みは簡単ではなく
県町、森林組合の協力がなかったら出来ない、対象山の調査(字、番地、所有者)、説明、現地の山境界確認、大小1.000筆あり地元の所有者が95%だった事が判明し事業推進活力になった。
古戸ひじり会は古戸地域の散策マップを作製し「花祭りゆかりコース」「願かけ・パワースポット巡り」「景勝地巡りコース」を案内している。
白山神社の索道(ロープウェイ)のことと、神社が花祭りの原形と係わっているという
関連記事
15℃ - 21℃ 曇り PM3時過ぎ雨(東栄町)
2018年10月31日
菊の盆栽仕立て
岡崎市の岡崎城によっても「家康館」を見学しようと大手門を潜ると「菊の展覧会」が開かれていました。



こちらのは盆栽? 菊の盆栽仕立てでした


開花するとどのように・・・

楽しみですが観賞する機会があるか、岡崎城跡までまた行く?
10.5℃ - 20℃ はれ
こちらのは盆栽? 菊の盆栽仕立てでした
開花するとどのように・・・
楽しみですが観賞する機会があるか、岡崎城跡までまた行く?
10.5℃ - 20℃ はれ
2018年09月19日
見る・歩く・体感するチャンス 豊川源流と河口、楽ちんウォーク
この機会に豊川河口と豊川の源流・段戸山原生林を歩いてみませんか、詳しい事は「広報しんしろ」9月号24ページに「あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業」として記載されています。
源流 ぶなの木 地元のガイドさん説明 あります


コースは整備されています。

湿原もあります

広報しんしろ 記載内容




コース別詳細






申し込用紙のない方は問い合わせてください
4コースあります、一つのコースでもOK
集合場所からバスで現地に行ける、楽ちんです
源流、河口を見るチャンスです。
私達の生活に欠かせない水、水源と海に注ぐ干潟での役割 環境の大切さを現地で見ては如何。
源流 ぶなの木 地元のガイドさん説明 あります
コースは整備されています。
湿原もあります
広報しんしろ 記載内容
コース別詳細
申し込用紙のない方は問い合わせてください
4コースあります、一つのコースでもOK
集合場所からバスで現地に行ける、楽ちんです
源流、河口を見るチャンスです。
私達の生活に欠かせない水、水源と海に注ぐ干潟での役割 環境の大切さを現地で見ては如何。
2018年09月11日
富永神社 能 よもつきじ~めでたけれまで
新城、富永神社例大祭奉納「祭礼能」 今年は10月5日(金) 午後5時頃から始まる予定です。
日本芸能の一つで歌舞劇なのですが、薬等の効能を書いたのを能書きといいますね。自分の優れた事を並べたてる、自己宣伝する事を能書きをたれる。能と関係あるんですかね?
先日の歴史講座にて新城能楽社の皆様が事細かに説明実技をしていただいた。一度新城文化会館にて観賞したことを思い出しました。

能は謡(うたい) 歌う
面(おもて) 面(めん)のこと
囃子(はやし)は楽器 笛 小鼓(こつづみ) 大鼓(おおつづみ) 太鼓(たいこ) 演奏する

笛は孟宗竹を貼り合わせて作製、始まりと終了は高音などで知らせる役目も持っている。
価格は20万、鉛が入ってバランスを保っている

小鼓 本体は桜木 子牛の腹皮 年季が入るほど高価
麻紐で張る 音色は持っている麻紐を指で握り調整している
肩前で打つ

大鼓 桜木 馬皮 湿気を嫌う 膝上で打つ

太鼓 樫木 縦横紐で張る 牛皮 バチは桧木(ひのき)

能は神事、信仰から発生している
能は無表情で頭を下げない、少しの動作で表現しているようです。
舞台に松の木が描かれているが、その下に神が宿っている
舞はまず、松の木に向くが頭は下げない
受け継がれた理由
神社の例大祭として毎年続けたこと
演ずる人 見る人 支える地元
演能に使用する能装束、能面、能舞台が揃っていた
今後は
後継者の育成
祭礼能の理解と啓蒙をはかる
説明文
新城能の始まりは長篠・設楽原戦の翌年郷が原に新城を築城、奥平信昌が祝い観世与三郎を招き二の丸で能を開いた。
富永神社での能の始まりは
慶安元年(1648)丹波亀山(京都府亀岡市)から菅沼定実が当地に移封され、其の2代後の菅沼定用(さだもち)の家督を祝わって元文元年(1736)の祭礼の時富永神社で祭礼能が行なわれたのが始まり。
20.5℃ → 27.5℃ 曇り時、雨 晴れ
日本芸能の一つで歌舞劇なのですが、薬等の効能を書いたのを能書きといいますね。自分の優れた事を並べたてる、自己宣伝する事を能書きをたれる。能と関係あるんですかね?
先日の歴史講座にて新城能楽社の皆様が事細かに説明実技をしていただいた。一度新城文化会館にて観賞したことを思い出しました。

能は謡(うたい) 歌う
面(おもて) 面(めん)のこと
囃子(はやし)は楽器 笛 小鼓(こつづみ) 大鼓(おおつづみ) 太鼓(たいこ) 演奏する
笛は孟宗竹を貼り合わせて作製、始まりと終了は高音などで知らせる役目も持っている。
価格は20万、鉛が入ってバランスを保っている
小鼓 本体は桜木 子牛の腹皮 年季が入るほど高価
麻紐で張る 音色は持っている麻紐を指で握り調整している
肩前で打つ
大鼓 桜木 馬皮 湿気を嫌う 膝上で打つ
太鼓 樫木 縦横紐で張る 牛皮 バチは桧木(ひのき)
能は神事、信仰から発生している
能は無表情で頭を下げない、少しの動作で表現しているようです。
舞台に松の木が描かれているが、その下に神が宿っている
舞はまず、松の木に向くが頭は下げない
受け継がれた理由
神社の例大祭として毎年続けたこと
演ずる人 見る人 支える地元
演能に使用する能装束、能面、能舞台が揃っていた
今後は
後継者の育成
祭礼能の理解と啓蒙をはかる
説明文
新城能の始まりは長篠・設楽原戦の翌年郷が原に新城を築城、奥平信昌が祝い観世与三郎を招き二の丸で能を開いた。
富永神社での能の始まりは
慶安元年(1648)丹波亀山(京都府亀岡市)から菅沼定実が当地に移封され、其の2代後の菅沼定用(さだもち)の家督を祝わって元文元年(1736)の祭礼の時富永神社で祭礼能が行なわれたのが始まり。
20.5℃ → 27.5℃ 曇り時、雨 晴れ
2018年08月15日
新城3企画展
新城市内の三か所で企画展が開かれています
新城市設楽原歴史資料館 9月14日まで

新城市長篠城祉史跡保存館 8月27日まで

作手歴史民俗資料館 9月30日まで


24.5℃ → 30℃ 雨曇り雨 雨量約 75mm
新城市設楽原歴史資料館 9月14日まで
新城市長篠城祉史跡保存館 8月27日まで
作手歴史民俗資料館 9月30日まで
24.5℃ → 30℃ 雨曇り雨 雨量約 75mm
タグ :新城市3企画展
2018年07月21日
豊川海軍工廠展はじまる 9月2日(日)まで
毎年開催される「豊川海軍工廠展」が今日から豊川市桜ケ丘ミュージアム(豊川市桜ケ丘町)で開催されます。
昭和20年8月7日の米軍B29爆撃機等の空爆により多くの若者が亡くなりました。海軍工廠の歴史と戦争の悲惨さを後世に伝える事、毎年開催されています。


当時、工廠にて体験した方も見学に来られ、行き合えればお話しを伺う事ができます。
貴重なお話を無駄にしないようにしたいものです。
戦争とは何か?戦争によって幸せになるか?
26℃ → 35℃ はれ
昭和20年8月7日の米軍B29爆撃機等の空爆により多くの若者が亡くなりました。海軍工廠の歴史と戦争の悲惨さを後世に伝える事、毎年開催されています。
当時、工廠にて体験した方も見学に来られ、行き合えればお話しを伺う事ができます。
貴重なお話を無駄にしないようにしたいものです。
戦争とは何か?戦争によって幸せになるか?
26℃ → 35℃ はれ