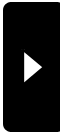2016年12月30日
一年を振り返って・NHKに放送されて
八橋観桜会NHKで全国放送
設楽ダム建設により地区全戸が移転した八橋地区、シンボルのウバヒガン桜(設楽町天然記念物)観桜会が旧住人が集い開かれた。
「ふるさとに残された一本桜」と題してNHKが遥々東京から取材に1月から何回も見えて撮影されていた。
4月13日、朝は全国、夕方は地元放送された



当日の取材


観桜会は来年も4月初期頃開催予定です。
設楽ダム建設により地区全戸が移転した八橋地区、シンボルのウバヒガン桜(設楽町天然記念物)観桜会が旧住人が集い開かれた。
「ふるさとに残された一本桜」と題してNHKが遥々東京から取材に1月から何回も見えて撮影されていた。
4月13日、朝は全国、夕方は地元放送された
当日の取材
観桜会は来年も4月初期頃開催予定です。
2016年12月29日
一年を振り返って・・新東名高速道路開通
2月13日新東名高速道路、浜松いなさJCT⇔豊田東JCT間が開通しました。
下り線長篠設楽原PAで式典がありました。

午後3時開通 30分前から雨が降りだしてPA近く道路北側から写す
下り線、3時24分先導車か通過

上り線、3時37分先導車通過

開通記念品頂きました

あくる日 開通30時間後PA満車でした
上り線PA

下り線PA

新東名高速道路開通により東名高速道路のマンネリ化していた平日渋滞が解消されたそうです。
2℃ → 14℃ はれ
下り線長篠設楽原PAで式典がありました。
午後3時開通 30分前から雨が降りだしてPA近く道路北側から写す
下り線、3時24分先導車か通過

上り線、3時37分先導車通過

開通記念品頂きました
あくる日 開通30時間後PA満車でした
上り線PA

下り線PA

新東名高速道路開通により東名高速道路のマンネリ化していた平日渋滞が解消されたそうです。
2℃ → 14℃ はれ
2016年12月28日
一年を振り返って・・・
今年も走り周りましたが1月は設楽ダム建設により移転した設楽町八橋地区あった旧八橋小学校校舎が6日午後2時から解体が始まった。
卒業生などが集まり「山は緑に水清き」♪校歌を合唱し思い出の校舎に別れを告げた。





今は解体も終了


10年後のダム完成までは校舎、住民はいなくなっても遠くにシンボルの山、知生山が見守っています。
卒業生などが集まり「山は緑に水清き」♪校歌を合唱し思い出の校舎に別れを告げた。
今は解体も終了
10年後のダム完成までは校舎、住民はいなくなっても遠くにシンボルの山、知生山が見守っています。
2016年12月26日
井伊家ゆかりの地 続・柿本城
新城市広報「ほのか}2017年1月号に11月号のつづき「直虎ゆかりの柿本城址」後編が記載されています。
柿本城の鈴木重勝の娘が井伊直平の長男・直満に嫁ぎ亀之丞(直親)が生まれる。
直平の3男が家督を継ぎその子が直盛であり娘、直虎(次郎法師)が生まれる。
井伊家に娘しか生まれなかったため鈴木家の亀之丞(直親)を養子に迎えるため許婚にした。しかし、亀之丞の父親・直満が今川方に殺害され亀之丞も命を狙われたため信州松源寺に身を隠すことになる。
「ほのか」の表紙 鳳来ひなの会の作品

井伊家三人衆もいます
柿本城の事が詳しく描かれています

道の駅・鳳来三河三石にある柿本城案内板の城縄張り

鈴木家は江戸時代になると水戸黄門様で知られる、水戸藩徳川家附家老になり代々仕えた。
城址見学は満光寺から上ると約10分ほどです。
柿本城祉
6℃ → 15℃ 薄曇り晴 風なし
柿本城の鈴木重勝の娘が井伊直平の長男・直満に嫁ぎ亀之丞(直親)が生まれる。
直平の3男が家督を継ぎその子が直盛であり娘、直虎(次郎法師)が生まれる。
井伊家に娘しか生まれなかったため鈴木家の亀之丞(直親)を養子に迎えるため許婚にした。しかし、亀之丞の父親・直満が今川方に殺害され亀之丞も命を狙われたため信州松源寺に身を隠すことになる。
「ほのか」の表紙 鳳来ひなの会の作品
井伊家三人衆もいます
柿本城の事が詳しく描かれています
道の駅・鳳来三河三石にある柿本城案内板の城縄張り
鈴木家は江戸時代になると水戸黄門様で知られる、水戸藩徳川家附家老になり代々仕えた。
城址見学は満光寺から上ると約10分ほどです。
柿本城祉
6℃ → 15℃ 薄曇り晴 風なし
2016年12月25日
お正月飾り、あれこれ
今年もあと7日で新年を迎えます。
お正月を迎える準備に皆さん忙しいと思いますが門松飾りもいろいろな飾り方がありますね。
先日尋ねた「気賀関所」

竹は下から縄で三・五・七巻です

竹は「そぎ切り」ですが先端も切落してある
縄の結び、縁起好い結びとか

先端が何故切り落としてあるか尋ねましたが「知らない」との事。
新居関所は竹を切ったままを使用している、古絵に描かれているそうです


この縄結びも意味があるようです

井伊谷宮は宗良親王を祀っています



縄巻は下から 7.5・3と巻かれている

だいだい(柑橘系果物)が供えられています、代々繁栄するようにの意味
新城の富永神社 縄はしたから七・五・三と巻いてある


節を上手く利用して笑っているようです

地域よって飾り方もちがいますね。
松は年中緑、永遠の命を意味する
竹は成長早く真っ直ぐ伸び強風にも耐え長命、子孫繁栄を意味する
梅は年の始めに咲く
後は南天、なんてん、難を転じて子孫繁栄
千両も同じようです
正月飾りは室町時代から始まったようです。
新年を迎える家の入口、門口に飾ったことから「門松」という。
歳神様を迎える目印になるとか。
注連縄(しめなわ)は天照大神が須佐之男命の乱暴に天岩戸に隠れ世が暗くなった。困って岩戸前で踊り騒いだところ、「何事か?」と天照大神が岩戸を開けた時、縄で戸を縛り閉められないようにした。それが注連縄というようです。
飾りは12月13日からOK、29日は9は苦になるとかで避ける、31日は「一夜飾り」になるから避ける。
竹の上が斜めに切られ「そぎ落し」といいますが調べていると、徳川家康と武田信玄が関係していると書いてあります。
信玄から家康に文がきた、「松(松平)枯れて 竹た(武田)ぐいなき あしたかな」
怒った家康は「松枯れず 武田首無きあしたかな」と返し門松の竹を「そぎ切った」という。
それから「胴切り」竹から「そぎ切り」竹になったという。
ホントでしょうか。
6℃ → 17℃ 晴 風なし
お正月を迎える準備に皆さん忙しいと思いますが門松飾りもいろいろな飾り方がありますね。
先日尋ねた「気賀関所」
竹は下から縄で三・五・七巻です
竹は「そぎ切り」ですが先端も切落してある
縄の結び、縁起好い結びとか
先端が何故切り落としてあるか尋ねましたが「知らない」との事。
新居関所は竹を切ったままを使用している、古絵に描かれているそうです
この縄結びも意味があるようです
井伊谷宮は宗良親王を祀っています
縄巻は下から 7.5・3と巻かれている
だいだい(柑橘系果物)が供えられています、代々繁栄するようにの意味
新城の富永神社 縄はしたから七・五・三と巻いてある
節を上手く利用して笑っているようです
地域よって飾り方もちがいますね。
松は年中緑、永遠の命を意味する
竹は成長早く真っ直ぐ伸び強風にも耐え長命、子孫繁栄を意味する
梅は年の始めに咲く
後は南天、なんてん、難を転じて子孫繁栄
千両も同じようです
正月飾りは室町時代から始まったようです。
新年を迎える家の入口、門口に飾ったことから「門松」という。
歳神様を迎える目印になるとか。
注連縄(しめなわ)は天照大神が須佐之男命の乱暴に天岩戸に隠れ世が暗くなった。困って岩戸前で踊り騒いだところ、「何事か?」と天照大神が岩戸を開けた時、縄で戸を縛り閉められないようにした。それが注連縄というようです。
飾りは12月13日からOK、29日は9は苦になるとかで避ける、31日は「一夜飾り」になるから避ける。
竹の上が斜めに切られ「そぎ落し」といいますが調べていると、徳川家康と武田信玄が関係していると書いてあります。
信玄から家康に文がきた、「松(松平)枯れて 竹た(武田)ぐいなき あしたかな」
怒った家康は「松枯れず 武田首無きあしたかな」と返し門松の竹を「そぎ切った」という。
それから「胴切り」竹から「そぎ切り」竹になったという。
ホントでしょうか。
6℃ → 17℃ 晴 風なし
2016年12月22日
火縄銃の玉の種類は
新城市設楽原歴史資料館20周年記念講演会が8回開催されています。
18日は6回目の講演「戦国鉄炮戦の実像を求めてー常識を破る玉を探る」と題して、日本銃炮史学会理事長、宇田川武久氏(国立歴史民俗資料館名誉教授)の講演がありました。
設楽原歴史資料館

資料の配布がなくパワーポイント説明と説明声がマイクがあるのに聴こえない状態でして理解できませんでした。
メモった
天正10年6月、武蔵八王子城戦いか、城址から鉛青銅の玉、鉄製中空の玉、土玉が出た。
鈴玉=鉄製中空の玉、中が空いている?
土玉=鉛が無い時ねばき土を丸めて2.3回紙を張って干す。泥土と石灰を剛砂を混ぜてかためる。
砲術武芸者は土玉は常識であった。
切玉=鉛を3ミリに切って、固め玉にする、散乱玉?、切玉を紙に包み3個発砲する、散乱玉になろう、地獄玉という。
なぎ玉=玉に穴をあけ三寸おきに紐で結ぶ、玉を3つ繋ぐ。
みだれ玉=小玉を14個入れる.
ほんの玉, 弐ッ玉、三つ玉、さん玉、さい玉、キリ玉、時刻玉など22種類あるそうです。
まだ、玉の話があったのですがようわかりませんでした。
、
6℃ → 18℃ 雨
18日は6回目の講演「戦国鉄炮戦の実像を求めてー常識を破る玉を探る」と題して、日本銃炮史学会理事長、宇田川武久氏(国立歴史民俗資料館名誉教授)の講演がありました。
設楽原歴史資料館
資料の配布がなくパワーポイント説明と説明声がマイクがあるのに聴こえない状態でして理解できませんでした。
メモった
天正10年6月、武蔵八王子城戦いか、城址から鉛青銅の玉、鉄製中空の玉、土玉が出た。
鈴玉=鉄製中空の玉、中が空いている?
土玉=鉛が無い時ねばき土を丸めて2.3回紙を張って干す。泥土と石灰を剛砂を混ぜてかためる。
砲術武芸者は土玉は常識であった。
切玉=鉛を3ミリに切って、固め玉にする、散乱玉?、切玉を紙に包み3個発砲する、散乱玉になろう、地獄玉という。
なぎ玉=玉に穴をあけ三寸おきに紐で結ぶ、玉を3つ繋ぐ。
みだれ玉=小玉を14個入れる.
ほんの玉, 弐ッ玉、三つ玉、さん玉、さい玉、キリ玉、時刻玉など22種類あるそうです。
まだ、玉の話があったのですがようわかりませんでした。
、
6℃ → 18℃ 雨
2016年12月21日
雨樋(とよ)清掃が波板交換になった話
バイク用駐車場ポート雨樋にゴミが溜まり雨が降ると滝の如く漏れまして樋機能していませんでした。
ゴミを取り出そうとしますが狭くて手が入りませんので波板を取り外し清掃したんですよ。
そしたら波板が上部がセット出来なくなり、おまけに下部が割れてしまいました。

バラになっていた中古品を組み立てて約12年ですから劣化していたんですポリ波板(私と同じ )
)
ポートがねじれ曲って入るみたい。
そんな事で新品波板を8枚購入しゴミが溜まった時に作業しやすいように樋部分が取り外せるよう短い波板を設置しました。
なんだこんだと脚立乗り降りを2日間
明日から筋肉痛が心配です。
6℃ → 12℃ 晴
ゴミを取り出そうとしますが狭くて手が入りませんので波板を取り外し清掃したんですよ。
そしたら波板が上部がセット出来なくなり、おまけに下部が割れてしまいました。
バラになっていた中古品を組み立てて約12年ですから劣化していたんですポリ波板(私と同じ
 )
)ポートがねじれ曲って入るみたい。
そんな事で新品波板を8枚購入しゴミが溜まった時に作業しやすいように樋部分が取り外せるよう短い波板を設置しました。
なんだこんだと脚立乗り降りを2日間
明日から筋肉痛が心配です。
6℃ → 12℃ 晴
2016年12月20日
気賀関所が元あった所
気賀は天正15年(1587)本多作左衛門によって宿場と定められたと前回書きましたが宿場の東口に慶長6年(1601)関所が建てられたと言われています。元和元年、慶長17年説もあるようです。
現関所は移転された物で街道筋から離れた所ですね。
元の関所は「気賀四ッ角」信号交差点北にあった

交差点北角に案内板と石碑があります

ポストがあり、細い路地を奥に行くと右に看板がある

個人所有?のようです

少し残っている屋根が見える

話を伺うと昭和35年(1960) まで完全な形で残っていた。
その時には建物完全移転は考えていなかったようです。
NHK大河ドラマ直虎放送によって「ドラマ館」開催 します
2017年1月15日~2018年1月14日 まで
関所入場 無料 にまります。
気賀関所跡
現関所
6℃ → 12℃ 曇り
現関所は移転された物で街道筋から離れた所ですね。
元の関所は「気賀四ッ角」信号交差点北にあった
交差点北角に案内板と石碑があります
ポストがあり、細い路地を奥に行くと右に看板がある
個人所有?のようです
少し残っている屋根が見える
話を伺うと昭和35年(1960) まで完全な形で残っていた。
その時には建物完全移転は考えていなかったようです。
NHK大河ドラマ直虎放送によって「ドラマ館」開催 します
2017年1月15日~2018年1月14日 まで
関所入場 無料 にまります。
気賀関所跡
現関所
6℃ → 12℃ 曇り
2016年12月19日
枡・升・〼の内の一斗升
尺貫法の容量を量る器に「ます・〼・枡・升」があります。
実家から譲り受けた「一斗升・いっとます」です。
かなり使用したようですね。
周りを金属たがを掛け手掛けも金属になっています。

内側に柿の渋が附着しています

渋柿の皮を入れて運んだためです
外側面に「新量器」と焼印

金属を使ってあるから「新量器」なのか
アイ 正 などが印されている

メーカー印か ナンバーか

底外にも焼印がありますが

なんの印かわからない
尺貫法は元は中国かから伝えられ使用地域で変化したようです。
容量の基準になった物は何か
秬黍(くろきび)を笛の管に入れ、入った量(810立方0.5合)が元らしい
重さは衡・コウ・キョウ・はかりと読む質量を表す、また時代によって両(ころ)斤(はかり)と言ったらしい。
この枡は一斗=約18リットルの容量です。
通貨では一匁(もんめ・文)は一銭=3.75g
現行の5円玉は一銭の重さ3.75gだそうです。
今でも一匁(mom)一銭の重さを基準に貨幣製造しているのでしょうか。
一文銭1.000枚で一貫、3.75㎏重いです。
重さ、面積、距離 尺貫法では解りません。
目眩がします~。
5℃ → 17℃ 晴時々曇り
実家から譲り受けた「一斗升・いっとます」です。
かなり使用したようですね。
周りを金属たがを掛け手掛けも金属になっています。
内側に柿の渋が附着しています
渋柿の皮を入れて運んだためです
外側面に「新量器」と焼印
金属を使ってあるから「新量器」なのか
アイ 正 などが印されている
メーカー印か ナンバーか
底外にも焼印がありますが
なんの印かわからない
尺貫法は元は中国かから伝えられ使用地域で変化したようです。
容量の基準になった物は何か
秬黍(くろきび)を笛の管に入れ、入った量(810立方0.5合)が元らしい
重さは衡・コウ・キョウ・はかりと読む質量を表す、また時代によって両(ころ)斤(はかり)と言ったらしい。
この枡は一斗=約18リットルの容量です。
通貨では一匁(もんめ・文)は一銭=3.75g
現行の5円玉は一銭の重さ3.75gだそうです。
今でも一匁(mom)一銭の重さを基準に貨幣製造しているのでしょうか。
一文銭1.000枚で一貫、3.75㎏重いです。
重さ、面積、距離 尺貫法では解りません。
目眩がします~。
5℃ → 17℃ 晴時々曇り
2016年12月18日
井伊家ゆかりの地 長楽寺に堀川城戦の弾痕
浜松市北区瀬戸で会った老夫婦と話をしていると、気賀の長楽寺の白壁に堀川城戦の徳川方が撃った弾痕があるらしいと言う。また、壁に狭間?か穴が開いているともいう。
長楽寺は北区細江町気賀、都田川が浜名湖へ注ぐ河口から北に少し上った所、前に訪れた堀川城跡・全得寺・金地院は近い。

約1200年前、平安初期大同年間(806~809)に弘法大師により開かれ、寺の北にある陽光巨岩を霊地として御堂を建てたのが始まりという。
山門と土べいは室町時代の作

山門の屋根に鷹がいます。

白壁の弾痕?は弾丸痕か、よう解りませんね。
壁の穴は狭間(はざま)か、狭間ではないですね。

覗くと壁厚く視野が狭く敵を狙う事ができないです。
塀を造るのに土を練って長筒状にし乾燥させ積み重ねています。

積み重ねた一本が壊れたみたいです。
伝・小堀遠州作、回遊式庭が綺麗です。

池は浜名湖風景を凝縮している。
満天星の庭 4月に咲くドウダンツツジの花を星に例えたようです。


築山から浜名湖が望めるという。
本尊は馬頭観音、道端の石造馬頭観音とは違い脚を折りたたんだ「伏せ馬」が観音様頭部にあります。
4月の開花と紅葉の庭を観賞したいものです。
2℃ → 17℃ 晴
長楽寺は北区細江町気賀、都田川が浜名湖へ注ぐ河口から北に少し上った所、前に訪れた堀川城跡・全得寺・金地院は近い。
約1200年前、平安初期大同年間(806~809)に弘法大師により開かれ、寺の北にある陽光巨岩を霊地として御堂を建てたのが始まりという。
山門と土べいは室町時代の作
山門の屋根に鷹がいます。
白壁の弾痕?は弾丸痕か、よう解りませんね。
壁の穴は狭間(はざま)か、狭間ではないですね。
覗くと壁厚く視野が狭く敵を狙う事ができないです。
塀を造るのに土を練って長筒状にし乾燥させ積み重ねています。
積み重ねた一本が壊れたみたいです。
伝・小堀遠州作、回遊式庭が綺麗です。
池は浜名湖風景を凝縮している。
満天星の庭 4月に咲くドウダンツツジの花を星に例えたようです。
築山から浜名湖が望めるという。
本尊は馬頭観音、道端の石造馬頭観音とは違い脚を折りたたんだ「伏せ馬」が観音様頭部にあります。
4月の開花と紅葉の庭を観賞したいものです。
2℃ → 17℃ 晴
2016年12月17日
想わぬ出会い・・賛美歌に
浜松市の聖隷病院内の階段を利用してコンサートが開かれていました。
昼の休み時間を利用してのコンサートのようです


聖隷クリストファー学校のみなさん?
院内フロワーに賛美歌が流れていました。
まもなくクリスマスがきますな~
昼の休み時間を利用してのコンサートのようです
聖隷クリストファー学校のみなさん?
院内フロワーに賛美歌が流れていました。
まもなくクリスマスがきますな~
2016年12月16日
忍者?さすが猫さん
浜松市の病院に行ったんです。
通路に掲げてあった展示写真の中の一枚です。

天井に張り付いている「めい」猫ちゃん(=^・・^=)

飼い主さんと遊んでいるのでしょうね。
=^_^=
本物の猫ちゃん?
2℃ → 11℃ 晴
通路に掲げてあった展示写真の中の一枚です。
天井に張り付いている「めい」猫ちゃん(=^・・^=)
飼い主さんと遊んでいるのでしょうね。
=^_^=
本物の猫ちゃん?
2℃ → 11℃ 晴
タグ :忍者猫
2016年12月15日
井伊家ゆかりの地 女城主直虎は男だった!?
今日の中日新聞のP34に「女城主直虎男だった!?」という記事があります。

これは井伊美術館(京都市)が発表したもので資料は井伊家彦根藩家老(寛永17年)であった木俣守安がおばたちから聞き書いたものを江戸中期に子孫の木俣守貞が書き写した。この資料には「直虎」と書いたものはなかったという。
では直虎はだれか、今川家臣・新野親矩(ちかのり)の甥(おい)で関口氏軽の子を井伊谷の領主・井伊次郎として治めさせた、と書かれているという。
地元蜂前神社の古文書に「関口と連名で次郎直虎の名前と花押があることから、関口の息子である井伊次郎が直虎」と考えられるという。 直虎花押は当ブログ、8月2日記載しています。
案内板の説明写真から

直虎花押
祝田郷の徳政令の事が書かれている
拡大すると
永禄十一辰
関口 氏経 花押
十一月九日
次郎
直虎 花押

直虎の右に関口氏軽

次郎法師と井伊次郎は別人で2人いたことは間違いないだろう。
親子の連署と云うことになるが・・・
なぜ許婚と云われる直虎を妻にしなかったか
亀之丞(直親)が信州松源寺から帰郷し時、井伊家後継者であるから許婚の「直虎」が出家していても妻にする事はできた。
信州に妻子・長男を残して長女を連れて来たいたから?許婚とは結婚できなかった。
何が起こるか解らない乱世ですから後継者は多いに超したことはない、信州に長男を預けた。
井伊谷親族に気を使い奥山家から嫁をとった。
直虎は男だった。
推測すればいろいろ出てきます。
歴史は憶測、推理が伴ないロマンがあります。
来年のNHK大河ドラマ放送に「井伊家ゆかりの地」は高揚しています。
これは井伊美術館(京都市)が発表したもので資料は井伊家彦根藩家老(寛永17年)であった木俣守安がおばたちから聞き書いたものを江戸中期に子孫の木俣守貞が書き写した。この資料には「直虎」と書いたものはなかったという。
では直虎はだれか、今川家臣・新野親矩(ちかのり)の甥(おい)で関口氏軽の子を井伊谷の領主・井伊次郎として治めさせた、と書かれているという。
地元蜂前神社の古文書に「関口と連名で次郎直虎の名前と花押があることから、関口の息子である井伊次郎が直虎」と考えられるという。 直虎花押は当ブログ、8月2日記載しています。
案内板の説明写真から

直虎花押
祝田郷の徳政令の事が書かれている
拡大すると
永禄十一辰
関口 氏経 花押
十一月九日
次郎
直虎 花押
直虎の右に関口氏軽
次郎法師と井伊次郎は別人で2人いたことは間違いないだろう。
親子の連署と云うことになるが・・・
なぜ許婚と云われる直虎を妻にしなかったか
亀之丞(直親)が信州松源寺から帰郷し時、井伊家後継者であるから許婚の「直虎」が出家していても妻にする事はできた。
信州に妻子・長男を残して長女を連れて来たいたから?許婚とは結婚できなかった。
何が起こるか解らない乱世ですから後継者は多いに超したことはない、信州に長男を預けた。
井伊谷親族に気を使い奥山家から嫁をとった。
直虎は男だった。
推測すればいろいろ出てきます。
歴史は憶測、推理が伴ないロマンがあります。
来年のNHK大河ドラマ放送に「井伊家ゆかりの地」は高揚しています。
2016年12月14日
井伊家ゆかりの地 今日は直政(虎松)父親・直親の命日
永禄5年(1562)12月14日、今川氏真から呼び出しがあり井伊家23代当主・直親(いいなおちか)は掛川城下の東海道沿いを通ると今川配下、朝比奈泰朝の数百兵に襲われ落命したのが454年前の今日である。法要があると聞き浜松市細江町中川の都田川堤の直親公墓所を訪れた。
直親は幼名亀之丞と言い父親・直満が今川義元に切り殺され亀之丞も命を狙われ信州松源寺に逃れた。井伊直虎は許婚であった。
法要は井伊家菩提寺・龍潭寺さんの都合で朝8時から関係者近隣の方約30人が集まり直親公の墓前にお参りした。



徳川幕府大老になった、井伊家36代直弼(なおすけ)は嘉永4年(1851)直親公の眠る都田川河畔墓石に参じた。燈籠一対を寄進した。昭和49年(1974)7月7日、七夕豪雨に都田川は氾濫し燈籠は流失した。近隣住民が河川を探し宝珠と火袋は見つけた。

河岸改修工事により今の所へ移転した。

直親の徒者は19~20数名と云われるが多勢による攻めに命を落としたが訃報を知った祝田郷蜂前(はちさき)神社神主・荻原家は二男を掛川へ行かせ隙を見て直親公の御首を持ち帰り大藤寺前の都田川河原にて火葬し同所にて龍泰寺(龍潭寺)の南渓和尚が読経焼香し埋葬した。
戒名 大藤寺殿剣峯宗恵大居士
の法号を授かった。
大藤寺は延文元年(1356)創建されたが昭和43年(1968)7月、龍潭寺に併合された。
直親公の墓は当所の他に
龍潭寺、東光院 渋川にある
直親公墓所
山下隆三郎氏説明文から抜粋
直親は幼名亀之丞と言い父親・直満が今川義元に切り殺され亀之丞も命を狙われ信州松源寺に逃れた。井伊直虎は許婚であった。
法要は井伊家菩提寺・龍潭寺さんの都合で朝8時から関係者近隣の方約30人が集まり直親公の墓前にお参りした。
徳川幕府大老になった、井伊家36代直弼(なおすけ)は嘉永4年(1851)直親公の眠る都田川河畔墓石に参じた。燈籠一対を寄進した。昭和49年(1974)7月7日、七夕豪雨に都田川は氾濫し燈籠は流失した。近隣住民が河川を探し宝珠と火袋は見つけた。
河岸改修工事により今の所へ移転した。
直親の徒者は19~20数名と云われるが多勢による攻めに命を落としたが訃報を知った祝田郷蜂前(はちさき)神社神主・荻原家は二男を掛川へ行かせ隙を見て直親公の御首を持ち帰り大藤寺前の都田川河原にて火葬し同所にて龍泰寺(龍潭寺)の南渓和尚が読経焼香し埋葬した。
戒名 大藤寺殿剣峯宗恵大居士
の法号を授かった。
大藤寺は延文元年(1356)創建されたが昭和43年(1968)7月、龍潭寺に併合された。
直親公の墓は当所の他に
龍潭寺、東光院 渋川にある
直親公墓所
山下隆三郎氏説明文から抜粋
2016年12月13日
気賀宿 散策 枡形石垣
浜松市北区細江町気賀、井伊家ゆかりの地を探し散策、東海道本坂通・通称「姫街道」が通り今では国道362号線になっている。
東海道は地震被害に舞阪渡船通行難、姫街道は多少の山道であるが通行しやすかったようです。
天正15年(1587)に本多作左衛門によって「気賀宿」が定められたと説明文にある。
慶長6年(1601)徳川幕府が「気賀関所」を置き、東海道の「新居関」と並び重要な宿場となり栄えた。
姫街道脇に「獄門畷」、東に行くと「枡形石垣、ますがた」と「常夜燈」がある。

枡形石垣は街道をL字型にし敵の侵攻を鈍らせる建造物で石垣の上に土塁を設け門があったという。
燈籠は秋葉山常夜灯、安政4年(1857)40両を地元の若者が集め建立した。
新城市街並みにある「曲尺手・曲手、かねんて」と同じ役目です。
枡形石垣に瓢箪(ひょうたん)が描かれています、何かの意味があるのか?説明はありません。

気賀関所は姫街道に沿ってあるのではなく、姫街道より南に下りた所にあります。
黒丸は枡形石垣

赤矢印は気賀関所
当時は河原?街道から関所まで下りて街道を通行していたのでしょう。
「犬くぐり道」という地元も方が関所通らない道があったそうです。
6.5℃ → 10℃ 小降り雨
東海道は地震被害に舞阪渡船通行難、姫街道は多少の山道であるが通行しやすかったようです。
天正15年(1587)に本多作左衛門によって「気賀宿」が定められたと説明文にある。
慶長6年(1601)徳川幕府が「気賀関所」を置き、東海道の「新居関」と並び重要な宿場となり栄えた。
姫街道脇に「獄門畷」、東に行くと「枡形石垣、ますがた」と「常夜燈」がある。
枡形石垣は街道をL字型にし敵の侵攻を鈍らせる建造物で石垣の上に土塁を設け門があったという。
燈籠は秋葉山常夜灯、安政4年(1857)40両を地元の若者が集め建立した。
新城市街並みにある「曲尺手・曲手、かねんて」と同じ役目です。
枡形石垣に瓢箪(ひょうたん)が描かれています、何かの意味があるのか?説明はありません。
気賀関所は姫街道に沿ってあるのではなく、姫街道より南に下りた所にあります。
黒丸は枡形石垣
赤矢印は気賀関所
当時は河原?街道から関所まで下りて街道を通行していたのでしょう。
「犬くぐり道」という地元も方が関所通らない道があったそうです。
6.5℃ → 10℃ 小降り雨
2016年12月12日
井伊家ゆかりの地 堀川城の戦い・獄門畷
堀川城での徳川軍との戦いは気賀衆老若男女を含め2000人が立て籠もった。
徳川軍3000の攻撃に永禄12年(1569)3月27日落城した、城は中洲のような所にあったのでしょう。
気賀、姫街道(国道362号線)呉石バス停の脇に「獄門畷」の案内板と石碑がある。

徳川軍は落城しても逃げた村民を探しだし捕え、700人の首を9月9日に討った。

その首を小川の堤にさらしたので「獄門畷・ごくもんなわて」と言った。
小川はどこか?尋ねたが「改修整備され元の川岸も解らなくなっている」とのこと。
姫街道の南であったことは確かのようだ。津波が3回押寄せて来たようです、明応7年(1498)8月25日、宝永4年(1707)10月4日、安政元年(1854)11月と津波の被害に川岸も変化したでしょう。
碑文 堀川城将士最期之地
天竜浜名湖鉄道の線路も元は河川敷だったようです。
頂いた気賀宿歴史散策マップの一部分

東西に堀川が流れ、川岸を埋め立てと区切っていた人工川のようでした。
姫街道より南の街は近年開発発展された街並です、低い所ですから津波が心配ですね。
獄門畷 碑
畷とは、畦道(あぜみち) 長い真っ直ぐな道
2℃ → 14.5℃ 曇り時々晴れ
徳川軍3000の攻撃に永禄12年(1569)3月27日落城した、城は中洲のような所にあったのでしょう。
気賀、姫街道(国道362号線)呉石バス停の脇に「獄門畷」の案内板と石碑がある。
徳川軍は落城しても逃げた村民を探しだし捕え、700人の首を9月9日に討った。
その首を小川の堤にさらしたので「獄門畷・ごくもんなわて」と言った。
小川はどこか?尋ねたが「改修整備され元の川岸も解らなくなっている」とのこと。
姫街道の南であったことは確かのようだ。津波が3回押寄せて来たようです、明応7年(1498)8月25日、宝永4年(1707)10月4日、安政元年(1854)11月と津波の被害に川岸も変化したでしょう。
碑文 堀川城将士最期之地
天竜浜名湖鉄道の線路も元は河川敷だったようです。
頂いた気賀宿歴史散策マップの一部分
東西に堀川が流れ、川岸を埋め立てと区切っていた人工川のようでした。
姫街道より南の街は近年開発発展された街並です、低い所ですから津波が心配ですね。
獄門畷 碑
畷とは、畦道(あぜみち) 長い真っ直ぐな道
2℃ → 14.5℃ 曇り時々晴れ
2016年12月11日
空を見上げれば・・・忙しいようですね
今朝はこの冬一番の冷え込みでしたです。
庭に出ていると飛行機音がよく聞こえます。
見上げると

引っ切り無しに次から次と

西方向へ飛んでいます、この上空は西空路なんでしょうか
毎日こんなに飛行機が飛んではいないですよね
今日は日曜日だからかん?
飛行機は総重量何トン? 重い物がよく飛びますね。
2℃ → 13.5℃ 快晴
庭に出ていると飛行機音がよく聞こえます。
見上げると
引っ切り無しに次から次と
西方向へ飛んでいます、この上空は西空路なんでしょうか
毎日こんなに飛行機が飛んではいないですよね
今日は日曜日だからかん?
飛行機は総重量何トン? 重い物がよく飛びますね。
2℃ → 13.5℃ 快晴
2016年12月10日
2016年12月10日
2016年12月09日
井伊家ゆかりの地 堀川城主はだれ?瀬戸方久か
浜松市北区細江町気賀の堀川城跡を訪ねる。弱体した井伊家の三人衆・近藤康用(やすもち)・鈴木重時・菅沼忠久を味方にした徳川氏は今川方支配の遠江へ軍を進めた。気賀の今川方土豪村民は掘方城に立て籠り抵抗した。刑部城落城し永禄12年徳川兵3000が堀川城を包囲し猛攻するが激しく抵抗、3月民兵1000人をなぜ切にし、なおも探索し生け捕った村人約700の首をはねたという。斬首した首を晒(さら)した堤を「獄門畷(ごくもんなわて」と地元では言伝えている。
堀川城は誰が主になっていたか、浜松市教育委員会が建てた案内板には誰とも書いてない。

全得寺の瀬戸方久墓の案内板に、堀川城主新田善斉(よしあき・きさい・方久)大永5年(1525)~慶長11年(1606)まで、新田義貞の末裔(まつえい)であって井伊家の家臣、気賀の領民に尽した武将(商)でもあった、落城後に訴訟に関与し、責任をとって気賀の代官・石川半三郎によって刑死となる。慶長11年(1606)8月、82歳の生涯を終える、とある。
別の物には、城将・山村修理、徳川氏侵攻に今川方が築城し家臣と地元住民で籠城、斎藤為義らと村民が築いたとある。
堀川城落城、3月25日近藤康用、秀用、鈴木重路、菅沼忠久、菅沼定盈らが堀江城攻めが始まったという。

左に塚がある


南側から見る

墓のある全得寺から写す 矢印が堀川城跡

屋根は全得寺 高台から見ると平坦な所に築城した事が解る。
城と言うよりも「砦」のような建物だったのではないかと想う。
どの様な規模だったか、遺構は残っていないという。
井伊家と係わりのあった瀬戸方久の詳しいことは解らない。
堀川城主なら徳川氏に敵対した事になる、が慶長まで生きている。
謎の多い瀬戸方久です。
6.5℃ → 16.5℃ 晴 夕方曇り
堀川城は誰が主になっていたか、浜松市教育委員会が建てた案内板には誰とも書いてない。
全得寺の瀬戸方久墓の案内板に、堀川城主新田善斉(よしあき・きさい・方久)大永5年(1525)~慶長11年(1606)まで、新田義貞の末裔(まつえい)であって井伊家の家臣、気賀の領民に尽した武将(商)でもあった、落城後に訴訟に関与し、責任をとって気賀の代官・石川半三郎によって刑死となる。慶長11年(1606)8月、82歳の生涯を終える、とある。
別の物には、城将・山村修理、徳川氏侵攻に今川方が築城し家臣と地元住民で籠城、斎藤為義らと村民が築いたとある。
堀川城落城、3月25日近藤康用、秀用、鈴木重路、菅沼忠久、菅沼定盈らが堀江城攻めが始まったという。
左に塚がある
南側から見る
墓のある全得寺から写す 矢印が堀川城跡
屋根は全得寺 高台から見ると平坦な所に築城した事が解る。
城と言うよりも「砦」のような建物だったのではないかと想う。
どの様な規模だったか、遺構は残っていないという。
井伊家と係わりのあった瀬戸方久の詳しいことは解らない。
堀川城主なら徳川氏に敵対した事になる、が慶長まで生きている。
謎の多い瀬戸方久です。
6.5℃ → 16.5℃ 晴 夕方曇り