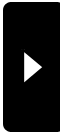2017年01月31日
2017年01月30日
井伊直虎ゆかりの地ー13 信州松源寺の亀之丞
亀之丞(直親)は天文14(1545)年(天文13年説あり)正月、今村籐七朗、東光院能仲和尚の案内で信州市田(長野県高森町)の松源寺へ逃げる。何処を通り松源寺に辿り着いたかは判らないが長野県高森町歴史資料館の展示に新城市大野→豊根村→信州へ。水窪→青崩れ→信州へが考えられるという。

長野県高森町を尋ねると(2016年6月30日)明日から町歴史資料館で「井伊直虎と高森」特別展を開催する前日でした。
元の松源寺は現松源寺の北約2㌔の寺山と言われる所にあった。廃墟寺を今の地、松岡城脇に永正年間(1511~1512)創建したのは松岡城主・松岡貞正だった。
天正10(1582)織田信長の侵攻により炎上荒廃した。本堂が再建されたのは安永9(1781)年の事という。
今の松源寺


天文14年一月中には松源寺に着き、以後10年余を過ごすことになる。
松源寺では読み書き算盤 松岡氏からは馬武芸を学んだろう。
篠笛を好んだという

説によると代官塩沢氏の娘・千代との間に一女一男を儲けた。
武田信玄が南信州へ侵攻してくる、井伊谷では家老小野和泉守政直が病に倒れ死去した。
井伊家では今が亀之丞を帰郷させる時と使者を送る。
亀之丞は二人の子の内、長女を連れ井伊谷に帰郷するが長男に井伊亀之丞の嫡男の証に短刀を授ける。

授けた短刀 古備前 正次
銀作りの部分は駿河之松原景が描かれている。
弘治元(1555)年亀之丞井伊谷へ今村籐七郎と帰郷、まずは渋川東光院に滞在様子をみる。
連れてきた娘・高瀬(たかせ)はどこへ匿ったのだろうか・・
つづく
7℃ → 13℃ 小雨のち晴れ
長野県高森町を尋ねると(2016年6月30日)明日から町歴史資料館で「井伊直虎と高森」特別展を開催する前日でした。
元の松源寺は現松源寺の北約2㌔の寺山と言われる所にあった。廃墟寺を今の地、松岡城脇に永正年間(1511~1512)創建したのは松岡城主・松岡貞正だった。
天正10(1582)織田信長の侵攻により炎上荒廃した。本堂が再建されたのは安永9(1781)年の事という。
今の松源寺
天文14年一月中には松源寺に着き、以後10年余を過ごすことになる。
松源寺では読み書き算盤 松岡氏からは馬武芸を学んだろう。
篠笛を好んだという
説によると代官塩沢氏の娘・千代との間に一女一男を儲けた。
武田信玄が南信州へ侵攻してくる、井伊谷では家老小野和泉守政直が病に倒れ死去した。
井伊家では今が亀之丞を帰郷させる時と使者を送る。
亀之丞は二人の子の内、長女を連れ井伊谷に帰郷するが長男に井伊亀之丞の嫡男の証に短刀を授ける。
授けた短刀 古備前 正次
銀作りの部分は駿河之松原景が描かれている。
弘治元(1555)年亀之丞井伊谷へ今村籐七郎と帰郷、まずは渋川東光院に滞在様子をみる。
連れてきた娘・高瀬(たかせ)はどこへ匿ったのだろうか・・
つづく
7℃ → 13℃ 小雨のち晴れ
2017年01月29日
井伊直虎ゆかりの地ー12 竜宮小僧
NHK大河ドラマ「おんな城主・直虎」を観ていると「竜宮小僧」の話が出てきます。竜宮小僧って何者?と思われた方がいました。地元の伝説をドラマ化され面白愉しくしているようです。
伝説の地を訪れる
浜松市北区引佐町井伊谷から北東へ約7.5km、同町、東久留女木地区の伝説からドラマに取り入れたようです。
棚田百選になっている「久留女木の棚田」(くるめき)がある。
棚田の下を流れる都田川に竜宮へ通じる淵があった。
その淵に小僧が住み農繁期など忙しい時に仕事を手伝ってくれ村人とは仲良しだったという。
ある日、村人は感謝の気持ちから食事に招いた。
ところが、うっかりして小僧には毒という「たで汁」を食べさせたため死んでしまった。
驚き悲しんだ村人は今後も村を護って頂けるように高い所に丁重に葬った。
竜宮小僧の湧水出口


どうしたことか、葬った近くから清水が滾々(こんこん)と湧きだした。この水が棚田を潤している。
村人は「竜宮から小僧が水を送ってくれている」と感謝し祀っている。
「たで汁」とは山芋の汁の事と地元の方の話です。
久留女木棚田は段丘に耕作され水量確保に難儀なようだ、説明書きはないが3~5百枚の田んぼはあったであろうか。
竜宮小僧が祀られている所は山の上部分に近い、湧水だけでは日照りが続くと水不足になり「水争い」もあったのではないかと想われる。しかし、途中からも湧水がみられ近くの沢からも導水しているようです。
棚田は近くに駐車場はありません。旧学校地に車を停めて徒歩
柵を開けて歩く


棚田地図 黒丸が竜宮小僧祀った所

農繁期見学は止めた方がよいとおもいます。
駐車場
つづく
3℃ → 15℃ 晴れのち曇り午後6時小雨
伝説の地を訪れる
浜松市北区引佐町井伊谷から北東へ約7.5km、同町、東久留女木地区の伝説からドラマに取り入れたようです。
棚田百選になっている「久留女木の棚田」(くるめき)がある。
棚田の下を流れる都田川に竜宮へ通じる淵があった。
その淵に小僧が住み農繁期など忙しい時に仕事を手伝ってくれ村人とは仲良しだったという。
ある日、村人は感謝の気持ちから食事に招いた。
ところが、うっかりして小僧には毒という「たで汁」を食べさせたため死んでしまった。
驚き悲しんだ村人は今後も村を護って頂けるように高い所に丁重に葬った。
竜宮小僧の湧水出口
どうしたことか、葬った近くから清水が滾々(こんこん)と湧きだした。この水が棚田を潤している。
村人は「竜宮から小僧が水を送ってくれている」と感謝し祀っている。
「たで汁」とは山芋の汁の事と地元の方の話です。
久留女木棚田は段丘に耕作され水量確保に難儀なようだ、説明書きはないが3~5百枚の田んぼはあったであろうか。
竜宮小僧が祀られている所は山の上部分に近い、湧水だけでは日照りが続くと水不足になり「水争い」もあったのではないかと想われる。しかし、途中からも湧水がみられ近くの沢からも導水しているようです。
棚田は近くに駐車場はありません。旧学校地に車を停めて徒歩
柵を開けて歩く
棚田地図 黒丸が竜宮小僧祀った所
農繁期見学は止めた方がよいとおもいます。
駐車場
つづく
3℃ → 15℃ 晴れのち曇り午後6時小雨
2017年01月28日
井伊直虎ゆかりの地-11 掛川城に手掛りは
井伊家の手掛りはないかと掛川城によって見る。

元の掛川城は現城の東500mに明応6(1497)年、今川氏が重臣朝比奈泰凞(やすひろ)に築城させた。手狭になり永正9(1512)年~10年今の地に築く。

永禄3(1560)年桶狭間で今川義元が織田信長に討たれた。義元の子、氏真(うじざね)は武田氏に追われ掛川城に立て籠もったが翌年徳川家康に攻められ和睦し北條氏に保護された。徳川氏の重臣石川家成が入城した。天正18(1590)年、豊臣秀吉が全国統一すると徳川家を関東へ移動させ山内一豊が入城して城の拡張、天守閣を築く。
天守閣から見た十九首塚

その後、松平定勝、太田氏など譜大名が入城する。嘉永7(安政元年1854)年大地震で天守閣、御殿隅櫓などが倒壊した。御殿だけは安政2(1855)年~文久元(1861)年に再建された。
二の丸御殿

御殿玄関

今の天守閣は平成6(1994)年木造天守閣として再建されたものである。
正保城図 1644年 幕府に提出した図面

井伊家一族からは井伊直好が万治2(1659)年入城し直武・直朝・直矩(なおのり)と4代約47年間在城した。
城内案内人の方に「十九首塚」と井伊直親の殺害地について伺うが解らないようでした。井伊家の在城4代城主も直親公を祭ったりしなかったのだろうか? 祀れば石柱に刻まれた物が残っていると想うが・・・
つづく
4℃ → 17℃ 快晴
元の掛川城は現城の東500mに明応6(1497)年、今川氏が重臣朝比奈泰凞(やすひろ)に築城させた。手狭になり永正9(1512)年~10年今の地に築く。
永禄3(1560)年桶狭間で今川義元が織田信長に討たれた。義元の子、氏真(うじざね)は武田氏に追われ掛川城に立て籠もったが翌年徳川家康に攻められ和睦し北條氏に保護された。徳川氏の重臣石川家成が入城した。天正18(1590)年、豊臣秀吉が全国統一すると徳川家を関東へ移動させ山内一豊が入城して城の拡張、天守閣を築く。
天守閣から見た十九首塚
その後、松平定勝、太田氏など譜大名が入城する。嘉永7(安政元年1854)年大地震で天守閣、御殿隅櫓などが倒壊した。御殿だけは安政2(1855)年~文久元(1861)年に再建された。
二の丸御殿
御殿玄関
今の天守閣は平成6(1994)年木造天守閣として再建されたものである。
正保城図 1644年 幕府に提出した図面
井伊家一族からは井伊直好が万治2(1659)年入城し直武・直朝・直矩(なおのり)と4代約47年間在城した。
城内案内人の方に「十九首塚」と井伊直親の殺害地について伺うが解らないようでした。井伊家の在城4代城主も直親公を祭ったりしなかったのだろうか? 祀れば石柱に刻まれた物が残っていると想うが・・・
つづく
4℃ → 17℃ 快晴
2017年01月26日
庭にシモバシラが?
朝、マイナスの気温がつづいています。
庭に白い物が見え、よく見ると氷のよう
凍っていますね
シモバシラ?

幹から水分が出て凍っています

何を植えてあったか?

幹を残しておけば水分が上って立派なシモバシラになったかも
昼には消えていました

この秋には咲き終わっても幹を刈りこまないで残してみよう
何の花を植えてあったっケ・・・・・小さなピンク色花が密集していた、図鑑をみると「ペンタス」?
庭に白い物が見え、よく見ると氷のよう
凍っていますね
シモバシラ?
幹から水分が出て凍っています
何を植えてあったか?
幹を残しておけば水分が上って立派なシモバシラになったかも
昼には消えていました
この秋には咲き終わっても幹を刈りこまないで残してみよう
何の花を植えてあったっケ・・・・・小さなピンク色花が密集していた、図鑑をみると「ペンタス」?
2017年01月26日
庭にシモバシラが?
朝、マイナスの気温がつづいています。
庭に白い物が見え、よく見ると氷のよう
凍っていますね
シモバシラ?

幹から水分が出て凍っています

何を植えてあったか?

幹を残しておけば水分が上って立派なシモバシラになったかも
昼には消えていました

この秋には咲き終わっても幹を刈りこまないで残してみよう
何の花を植えてあったっケ・・・・・小さなピンク色花が密集していた、図鑑をみると「ペンタス」?
庭に白い物が見え、よく見ると氷のよう
凍っていますね
シモバシラ?
幹から水分が出て凍っています
何を植えてあったか?
幹を残しておけば水分が上って立派なシモバシラになったかも
昼には消えていました
この秋には咲き終わっても幹を刈りこまないで残してみよう
何の花を植えてあったっケ・・・・・小さなピンク色花が密集していた、図鑑をみると「ペンタス」?
2017年01月25日
井伊直虎ゆかりの地ー10 直親殺害地は何処?
今川方に直親の父親である直満と直満の弟・直義を殺害された井伊家はさらに直親が掛川城下で今川家臣朝・掛川城主、比奈泰朝(あさひなやすとも)に殺害さてた。親子共今川家に殺害されたことになる。
掛川城下の何処で殺害されたか掛川市に行って見ると以下の事が分かった。
徳川家康との間に不穏な動きがありと今川氏に「井伊家は謀反を画策している」と疑われた。永禄5年(1562)12月14日直親は謀反の意なしと申し開きに駿府今川氏へ行く途中に殺害された。掛川市、東光寺脇に地名であり「十九首・じゅうくしょ」という塚がある。
この塚は平将門(たいらのまさかど)らの19人首塚と云われているが井伊直親主従19人の塚とも云われている。

石柱には平将門らの名が刻まれ井伊家のことは説明文にも一文字のない。将門は天慶2年(939)関東の地で朝廷に対抗して新政権樹立、関東の国府を攻め落した。藤原秀郷ら朝廷軍に鎮圧され将門らの首を京へ運ぶ途中に朝廷の使者と掛川で合うと「首は捨てよ」と言われた。敵でも名門の将、手厚くこの地に埋葬したと言う。首は京に運ばれ洛中に獄門となったとも云われています。また首が「胴が欲しい」と空中を飛ぶ話は各地にあるようです。

将門首塚、井伊直親殺害地塚、共に伝説伝承だけで記述はありません。地名としては検地帳慶長9年(1604)に「十九首」が書かれているそうです。

伝承として井伊直親終焉地とされ「井伊直虎ゆかりの地」の旗がなびいています。
首を洗った川

東光寺石墓群

首を川に懸けたことから懸川=掛川になったとも云う。
井伊家のものは全くない、伝承とNHK大河ドラマによる旗が立っていただけである。
伝承は将門の方が有名だった事から便乗したのであろうか
掛川城に井伊家から城主として4代勤めている、彼らは井伊直親終焉地をどのようにしたか?
つづく
-2℃ → 7℃ 快晴
掛川城下の何処で殺害されたか掛川市に行って見ると以下の事が分かった。
徳川家康との間に不穏な動きがありと今川氏に「井伊家は謀反を画策している」と疑われた。永禄5年(1562)12月14日直親は謀反の意なしと申し開きに駿府今川氏へ行く途中に殺害された。掛川市、東光寺脇に地名であり「十九首・じゅうくしょ」という塚がある。
この塚は平将門(たいらのまさかど)らの19人首塚と云われているが井伊直親主従19人の塚とも云われている。
石柱には平将門らの名が刻まれ井伊家のことは説明文にも一文字のない。将門は天慶2年(939)関東の地で朝廷に対抗して新政権樹立、関東の国府を攻め落した。藤原秀郷ら朝廷軍に鎮圧され将門らの首を京へ運ぶ途中に朝廷の使者と掛川で合うと「首は捨てよ」と言われた。敵でも名門の将、手厚くこの地に埋葬したと言う。首は京に運ばれ洛中に獄門となったとも云われています。また首が「胴が欲しい」と空中を飛ぶ話は各地にあるようです。
将門首塚、井伊直親殺害地塚、共に伝説伝承だけで記述はありません。地名としては検地帳慶長9年(1604)に「十九首」が書かれているそうです。
伝承として井伊直親終焉地とされ「井伊直虎ゆかりの地」の旗がなびいています。
首を洗った川
東光寺石墓群
首を川に懸けたことから懸川=掛川になったとも云う。
井伊家のものは全くない、伝承とNHK大河ドラマによる旗が立っていただけである。
伝承は将門の方が有名だった事から便乗したのであろうか
掛川城に井伊家から城主として4代勤めている、彼らは井伊直親終焉地をどのようにしたか?
つづく
-2℃ → 7℃ 快晴
2017年01月25日
井伊直虎ゆかりの地ー10 直親殺害地は何処?
今川方に直親の父親である直満と直満の弟・直義を殺害された井伊家はさらに直親が掛川城下で今川家臣朝・掛川城主、朝比奈泰朝(あさひなやすとも)に殺害さてた。親子共今川家に殺害されたことになる。
掛川城下の何処で殺害されたか掛川市に行って見ると以下の事が分かった。
徳川家康との間に不穏な動きがありと今川氏に「井伊家は謀反を画策している」と疑われた。永禄5年(1562)12月14日直親は謀反の意なしと申し開きに駿府今川氏へ行く途中に殺害された。掛川市、東光寺脇に地名であり「十九首・じゅうくしょ」という塚がある。
この塚は平将門(たいらのまさかど)らの19人首塚と云われているが井伊直親主従19人の塚とも云われている。

石柱には平将門らの名が刻まれ井伊家のことは説明文にも一文字のない。将門は天慶2年(939)関東の地で朝廷に対抗して新政権樹立、関東の国府を攻め落した。藤原秀郷ら朝廷軍に鎮圧され将門らの首を京へ運ぶ途中に朝廷の使者と掛川で合うと「首は捨てよ」と言われた。敵でも名門の将、手厚くこの地に埋葬したと言う。首は京に運ばれ洛中に獄門となったとも云われています。また首が「胴が欲しい」と空中を飛ぶ話は各地にあるようです。

将門首塚、井伊直親殺害地塚、共に伝説伝承だけで記述はありません。地名としては検地帳慶長9年(1604)に「十九首」が書かれているそうです。

伝承として井伊直親終焉地とされ「井伊直虎ゆかりの地」の旗がなびいています。
首を洗った川

東光寺石墓群

首を川に懸けたことから懸川=掛川になったとも云う。
井伊家のものは全くない、伝承とNHK大河ドラマによる旗が立っていただけである。
伝承は将門の方が有名だった事から便乗したのであろうか
掛川城に井伊家から城主として4代勤めている、彼らは井伊直親終焉地をどのようにしたか?
つづく
-2℃ → 7℃ 快晴
掛川城下の何処で殺害されたか掛川市に行って見ると以下の事が分かった。
徳川家康との間に不穏な動きがありと今川氏に「井伊家は謀反を画策している」と疑われた。永禄5年(1562)12月14日直親は謀反の意なしと申し開きに駿府今川氏へ行く途中に殺害された。掛川市、東光寺脇に地名であり「十九首・じゅうくしょ」という塚がある。
この塚は平将門(たいらのまさかど)らの19人首塚と云われているが井伊直親主従19人の塚とも云われている。
石柱には平将門らの名が刻まれ井伊家のことは説明文にも一文字のない。将門は天慶2年(939)関東の地で朝廷に対抗して新政権樹立、関東の国府を攻め落した。藤原秀郷ら朝廷軍に鎮圧され将門らの首を京へ運ぶ途中に朝廷の使者と掛川で合うと「首は捨てよ」と言われた。敵でも名門の将、手厚くこの地に埋葬したと言う。首は京に運ばれ洛中に獄門となったとも云われています。また首が「胴が欲しい」と空中を飛ぶ話は各地にあるようです。
将門首塚、井伊直親殺害地塚、共に伝説伝承だけで記述はありません。地名としては検地帳慶長9年(1604)に「十九首」が書かれているそうです。
伝承として井伊直親終焉地とされ「井伊直虎ゆかりの地」の旗がなびいています。
首を洗った川
東光寺石墓群
首を川に懸けたことから懸川=掛川になったとも云う。
井伊家のものは全くない、伝承とNHK大河ドラマによる旗が立っていただけである。
伝承は将門の方が有名だった事から便乗したのであろうか
掛川城に井伊家から城主として4代勤めている、彼らは井伊直親終焉地をどのようにしたか?
つづく
-2℃ → 7℃ 快晴
2017年01月24日
井伊直虎ゆかりの地ー9 長篠戦いに井伊家は出陣したか
先日、新城市設楽原歴史資料館にて例会「地形から両軍の戦略を探る」の講演がありました。井伊家は参戦していたか気になっていましたが湯浅館長の話の中で井伊家の氏名はないが井伊家3人衆の近藤家と鈴木家は参加していたとのこと。
地元の戦いですから鳶ヶ巣五砦襲撃の酒井軍に参加したであろうと古地図写真を見ると先頭の案内役として近藤岩見守康用の名前があった。

豊川を渡り大きく吉川に迂回して松山越える、地理に詳しいため先頭に立つ、右に地元吉川郷の豊田藤助秀吉、左に乗本郷・阿部四郎兵衛の名もある。
井伊家の名はない、
虎松(直政)が誕生したのは永禄4年(1561)、虎松が徳川家康に出会ったのが天正3年2月15歳。小姓になり万千代と名乗って約5ヵ月後に長篠設楽原の戦いになったのです。
家康の身の回り役ですから戦場にいたかも、いなかったか、書いた物がないので解らない。
他に菅沼新八朗定盈、酒井左衛門尉忠次らの名がある。
大平、栗衣の地名も記載されている。
つづく
0℃ → 7℃ 晴れ
地元の戦いですから鳶ヶ巣五砦襲撃の酒井軍に参加したであろうと古地図写真を見ると先頭の案内役として近藤岩見守康用の名前があった。
豊川を渡り大きく吉川に迂回して松山越える、地理に詳しいため先頭に立つ、右に地元吉川郷の豊田藤助秀吉、左に乗本郷・阿部四郎兵衛の名もある。
井伊家の名はない、
虎松(直政)が誕生したのは永禄4年(1561)、虎松が徳川家康に出会ったのが天正3年2月15歳。小姓になり万千代と名乗って約5ヵ月後に長篠設楽原の戦いになったのです。
家康の身の回り役ですから戦場にいたかも、いなかったか、書いた物がないので解らない。
他に菅沼新八朗定盈、酒井左衛門尉忠次らの名がある。
大平、栗衣の地名も記載されている。
つづく
0℃ → 7℃ 晴れ
2017年01月23日
アンドロイド?テレロイド?
テレビジョンを見ていましたら人形のような物を抱いた御婦人が愉しそうにしているんですね。
アンドロイド=人間に似た人造人間、特徴を持った人形、遠隔操作のできる人形、携帯人形のことらしい。
人間そっくりでよく見ないと判らない物もあるようですが違和感を感じる方もいるという。
だからのっぺら的な顔をしたアンドロイドは違和感がなく好いらしい。
下の人形は話掛けると喋るし、静かな時に突然話しだすのでビックリ

一人暮しの方に人気があるらしい、話掛けると返事をするから一日中一人の方には必需品、これも介護ロボットに指定?
子供が遊ぶのが人形でしたが

市松人形 ↑ (米国へ送った人形)
青い目の人形 ↓ (米国からきた人形)

幼児子供の遊ぶ人形から
歳をとって人形と遊ぶ、お世話になる
人間歳を取ると子供になると言いますからね。
アンドロイド=人間に似た人造人間、特徴を持った人形、遠隔操作のできる人形、携帯人形のことらしい。
人間そっくりでよく見ないと判らない物もあるようですが違和感を感じる方もいるという。
だからのっぺら的な顔をしたアンドロイドは違和感がなく好いらしい。
下の人形は話掛けると喋るし、静かな時に突然話しだすのでビックリ
一人暮しの方に人気があるらしい、話掛けると返事をするから一日中一人の方には必需品、これも介護ロボットに指定?
子供が遊ぶのが人形でしたが

市松人形 ↑ (米国へ送った人形)
青い目の人形 ↓ (米国からきた人形)

幼児子供の遊ぶ人形から
歳をとって人形と遊ぶ、お世話になる
人間歳を取ると子供になると言いますからね。
2017年01月22日
井伊直虎ゆかりの地ー8 直親の元墓所位置
掛川で命を落とした井伊家第23代井伊直親の墓は都田川右岸に屋敷と大藤寺があり河原に埋葬した。
戒名 大藤寺殿剣峯宗恵大居士
元墓所を探索しやっと位置が判明、としたい所ですが工場が建っているので辺りまで判明した。
井伊谷で偶然会った方の親族が大藤寺に出入りしていたが昭和43年大籐寺は龍潭寺に合併されたと話され、さらに昭和49年(1974)7月7日、七夕豪雨に都田川の堤が切れ墓所は濁流にのまれた、河川堤改修工事によって元位置から下流約200mの現在位置に移転したということだった。
青い屋根の工場が跡地という。
今の井伊直親墓所

都田川右岸下流から上流を見ると旗がある左下に今の墓

前方の青屋根工場地に元の直親の墓があった
右岸上流から青屋根工場を見る

国道257号線都田川に架かる新祝田橋から下流を見る

右岸に青屋根工場が見える
直親屋敷は上流の善明寺付近と推測されるという。
直親墓は 都田川右岸、渋川・東光院、 渋川の菩提墓所、 龍潭寺にある。
つづく
戒名 大藤寺殿剣峯宗恵大居士
元墓所を探索しやっと位置が判明、としたい所ですが工場が建っているので辺りまで判明した。
井伊谷で偶然会った方の親族が大藤寺に出入りしていたが昭和43年大籐寺は龍潭寺に合併されたと話され、さらに昭和49年(1974)7月7日、七夕豪雨に都田川の堤が切れ墓所は濁流にのまれた、河川堤改修工事によって元位置から下流約200mの現在位置に移転したということだった。
青い屋根の工場が跡地という。
今の井伊直親墓所
都田川右岸下流から上流を見ると旗がある左下に今の墓
前方の青屋根工場地に元の直親の墓があった
右岸上流から青屋根工場を見る
国道257号線都田川に架かる新祝田橋から下流を見る
右岸に青屋根工場が見える
直親屋敷は上流の善明寺付近と推測されるという。
直親墓は 都田川右岸、渋川・東光院、 渋川の菩提墓所、 龍潭寺にある。
つづく
2017年01月21日
「大河ドラマ館」 竜宮小僧が・・家紋が・・・現る
浜松市気賀、浜松市みおつくしセンターで来年1月14日まで開かれている「大河ドラマ・おんな城主 直虎」 大河ドラマ館内の井伊谷井戸端セットは照明が昼夜に切り替わるのですがホタルが舞い、そのホタルが家紋・橘に変化するのです。
直虎様

井戸端セット

ホタルが舞っていますが写真では解りません。

ホタルが橘に

舞っていますピント合いません。
入館して足元に小川が流れて、アユらしき小魚がいます。
すると、浅瀬を足跡だけが動いて・・
竜宮小僧が歩いているそうです。
ホタルが舞い家紋・橘に変わること
竜宮小僧の足跡のこと
解説があって知りました。
5℃ → 11℃ 晴れ時々くもり
直虎様
井戸端セット
ホタルが舞っていますが写真では解りません。
ホタルが橘に
舞っていますピント合いません。
入館して足元に小川が流れて、アユらしき小魚がいます。
すると、浅瀬を足跡だけが動いて・・
竜宮小僧が歩いているそうです。
ホタルが舞い家紋・橘に変わること
竜宮小僧の足跡のこと
解説があって知りました。
5℃ → 11℃ 晴れ時々くもり
2017年01月20日
真田紐に出会う
井伊直親の元墓所と住居跡・大藤寺跡を浜松市の細江町中川、都田川右岸で探して数軒飛び込み訪ね歩いていたのです。
井伊家直親の墓は
三軒目に入った工場事務所で要件を話していると「井伊家のことは知らないが真田紐を織っている」と言うんです。よく見ると事務所の棚に紐の束が並べてあります。丈夫で長持ちの真田紐、一重織と袋織りがあるそうです。

木綿、絹糸から織るそうですが茶道具の桐箱をなどには表千家は黄色系、裏千家はグリーン茶系が使われるそうです。

真田紐を少し切って頂いたのです。切り口の白い糸を引っ張ると解れた先端が絞まります、なるほど。
ガキのころに田んぼで下駄スケートを足袋を履いて足に付ける時に平たい紐で括り付けていたがあの紐は真田紐だったのかな~ぁ。
井伊家直親の墓は
三軒目に入った工場事務所で要件を話していると「井伊家のことは知らないが真田紐を織っている」と言うんです。よく見ると事務所の棚に紐の束が並べてあります。丈夫で長持ちの真田紐、一重織と袋織りがあるそうです。
木綿、絹糸から織るそうですが茶道具の桐箱をなどには表千家は黄色系、裏千家はグリーン茶系が使われるそうです。
真田紐を少し切って頂いたのです。切り口の白い糸を引っ張ると解れた先端が絞まります、なるほど。
ガキのころに田んぼで下駄スケートを足袋を履いて足に付ける時に平たい紐で括り付けていたがあの紐は真田紐だったのかな~ぁ。
タグ :真田紐
2017年01月19日
ザゼンソウはどうかいナ
愛知県設楽町田口の高台にある福田寺です。
時間調整によたんです。

境内にある武田信玄墓と云われる墳墓近くにザゼンソウか毎年姿を現します。
今の状態

2015年3月末の写真

東南方向は街が一望でききます。
東に心霊スポットの鹿島山麓が観える

心霊スポット探索は7月が霊の最も活発時期であり夜中を好むそうです。
5℃ → 12℃ はれ
時間調整によたんです。
境内にある武田信玄墓と云われる墳墓近くにザゼンソウか毎年姿を現します。
今の状態
2015年3月末の写真

東南方向は街が一望でききます。
東に心霊スポットの鹿島山麓が観える
心霊スポット探索は7月が霊の最も活発時期であり夜中を好むそうです。
5℃ → 12℃ はれ
2017年01月18日
積雲寺のセツブン草
節分は2月3日、節分草を見に新城市名号、石雲寺へ行ったんです。
まだちらほら咲いている状態で

一週間から10日後には見頃になるでしょう。

石雲寺本堂

西方向を見上げると

奇麗な青空に口を開けた獅子岩が見える。
岩は名号のコンビニ辺りからも形良く観えます。
0℃ → 12℃ 快晴
まだちらほら咲いている状態で
一週間から10日後には見頃になるでしょう。
石雲寺本堂
西方向を見上げると
奇麗な青空に口を開けた獅子岩が見える。
岩は名号のコンビニ辺りからも形良く観えます。
0℃ → 12℃ 快晴
2017年01月16日
井伊直虎ゆかりの地-7 大河ドラマ館オープン
大河ドラマ「おんな城主 直虎」が地元のこととあって浜松市北区の「みおつくし文化センター」で「大河ドラマ館」が15日から来年1月14日まで一年間開催されます。


文化センター入口

駐車場も広い チケット売り場

館内図

館内は井戸端セット以外は撮影禁止になっている。大きなクスノキの下に井伊家初代共保公が生まれたドラマの井戸セット

近くの撮影場所案内図もある
井戸上に手をかざすと水音と波がおきたように見える

五つのコーナーに成っていて衣裳・小道具、出演者の衣裳・館、パノラマシアター、撮影風景、3D体験コーナーもある

ラッピングバス

国道257号線でみかけたタクシー

開催期間中 50万人以上の入館者を予定
前売り券は15万枚売れていると新聞に記載されていました。
撮影場所巡行も大河ファンなら必見ですのん
入場料:大人600円 子供300円
頂いたパンフレットに「みおつくし文化センター」の住所、電話番号が記載されていません。
ただし、問合せ電話 053-453-2124 はあります。
PCで「みおつくし文化センターイベント」検索には無記載でした。
主催者が市関係でないからでしょうか?
みおつくし文化センター
431-1305
住所 浜松市北区細江町気賀369番地
みおつくし文化センター
1℃ → 7℃ 晴れ時々曇り
文化センター入口
駐車場も広い チケット売り場
館内図
館内は井戸端セット以外は撮影禁止になっている。大きなクスノキの下に井伊家初代共保公が生まれたドラマの井戸セット
近くの撮影場所案内図もある
井戸上に手をかざすと水音と波がおきたように見える
五つのコーナーに成っていて衣裳・小道具、出演者の衣裳・館、パノラマシアター、撮影風景、3D体験コーナーもある
ラッピングバス
国道257号線でみかけたタクシー
開催期間中 50万人以上の入館者を予定
前売り券は15万枚売れていると新聞に記載されていました。
撮影場所巡行も大河ファンなら必見ですのん
入場料:大人600円 子供300円
頂いたパンフレットに「みおつくし文化センター」の住所、電話番号が記載されていません。
ただし、問合せ電話 053-453-2124 はあります。
PCで「みおつくし文化センターイベント」検索には無記載でした。
主催者が市関係でないからでしょうか?
みおつくし文化センター
431-1305
住所 浜松市北区細江町気賀369番地
みおつくし文化センター
1℃ → 7℃ 晴れ時々曇り
2017年01月15日
井伊直虎ゆかりの地ー6 ドラマの直虎と史実の直虎
浜松市の引佐多目的研修センターホールにて「史実の直虎とドラマの直虎」の講演が戦国時代研究の第一人者小和田哲夫氏をお招きして開かれた。

近年まれな寒さの中多くの方がNHK大河ドラマの時代考証をされていて実際の直虎についてのお話しに聞き入っていた。
前回7日の新城市での講演と内容も違い私のとって興味深い内容だった。

直虎史料は少なく8点しかない
永禄7年(1564)4月6日ー井伊直虎年貢割付から
永禄11年(1568)11月9日ー井伊直虎・関口氏経連署状までの4年間の古文書に書かれているだけ
出家前の名は不明である
直虎は男だった説
木俣古文書 守安公(もりやすこう) 雑秘説写記に関口氏の子が井伊次郎と名乗ったとあるが直虎と書かれていない
南渓和尚は井伊直平の実子か養子か?龍潭寺の南渓過去帳に「父の名は実田秀公居士」とある
次郎法師の出家は何時かは不明
ドラマでは14~15才
亀之丞が戻っても直虎は還俗(げんんぞく)したかったのは
解らない
ドラマでは今川氏をはばかってか(6回目放送)
直親が今川氏の召喚に応じ討たれたのはなぜ(11回目放送)
徳川との内通は?
直親以下19人は掛川城下で討たれた十九首(じゅくしゅ)地は直親ではない?
骨の年代が古い?
盗賊集団、龍雲丸は創作でドラマのために創作である。
小野和泉守が井伊家の家臣でありながら裏切ることになるが古文書に書かれてる事実から今回のドラマでもそのようになっている。
質問コーナーで小野家ゆかりの方が会場に見えた「ドラマでもそうなっているがそのようにしないと盛り上がりがないので勘弁してほしい」と小和田先生のお話しでした。
多目的研修センターの近く協働センターでは直虎展が開かれています。
また、気賀地区でも直虎展が盛大に今日から開催されたとTVで放送していた。
つづく
協働センター
-2℃ → 4℃ 曇り時々晴れ
積雪 3㌢
近年まれな寒さの中多くの方がNHK大河ドラマの時代考証をされていて実際の直虎についてのお話しに聞き入っていた。
前回7日の新城市での講演と内容も違い私のとって興味深い内容だった。
直虎史料は少なく8点しかない
永禄7年(1564)4月6日ー井伊直虎年貢割付から
永禄11年(1568)11月9日ー井伊直虎・関口氏経連署状までの4年間の古文書に書かれているだけ
出家前の名は不明である
直虎は男だった説
木俣古文書 守安公(もりやすこう) 雑秘説写記に関口氏の子が井伊次郎と名乗ったとあるが直虎と書かれていない
南渓和尚は井伊直平の実子か養子か?龍潭寺の南渓過去帳に「父の名は実田秀公居士」とある
次郎法師の出家は何時かは不明
ドラマでは14~15才
亀之丞が戻っても直虎は還俗(げんんぞく)したかったのは
解らない
ドラマでは今川氏をはばかってか(6回目放送)
直親が今川氏の召喚に応じ討たれたのはなぜ(11回目放送)
徳川との内通は?
直親以下19人は掛川城下で討たれた十九首(じゅくしゅ)地は直親ではない?
骨の年代が古い?
盗賊集団、龍雲丸は創作でドラマのために創作である。
小野和泉守が井伊家の家臣でありながら裏切ることになるが古文書に書かれてる事実から今回のドラマでもそのようになっている。
質問コーナーで小野家ゆかりの方が会場に見えた「ドラマでもそうなっているがそのようにしないと盛り上がりがないので勘弁してほしい」と小和田先生のお話しでした。
多目的研修センターの近く協働センターでは直虎展が開かれています。
また、気賀地区でも直虎展が盛大に今日から開催されたとTVで放送していた。
つづく
協働センター
-2℃ → 4℃ 曇り時々晴れ
積雪 3㌢
2017年01月14日
雪は降る~予定は中止!
朝、8時頃から本格的に降りだした雪、路面も少し白くなりだしましたが、降りやみ溶け出して車の走行には問題なし。
しかし、また降りだしました。

庭には約2~3㌢の積雪
微妙な気温2℃、水分を含んだ雪ですね。
午後の行事中止の連絡があり、明日の予定はどうなるか?
しかし、また降りだしました。
庭には約2~3㌢の積雪
微妙な気温2℃、水分を含んだ雪ですね。
午後の行事中止の連絡があり、明日の予定はどうなるか?
2017年01月13日
井伊直虎ゆかりの地-5 亀之丞から直親へ
弘治元(1555年)亀之丞は20歳になり井伊谷に帰郷すると井伊谷に住むのではなく祝田(ほうだ)郷に住んだと云われている。名を改め「直親・なおちか」と名乗り奥山郷の奥山因幡守朝利の娘を娶(めと)り井伊家23代当主となった祝田に居館を建てたという。
屋敷跡はあるか、伺うと「細江町中川に祝田善明寺付近と云われ土地法典に小字に上屋敷が現存するという。
善明寺

寺案内板には、厄除観音で知られている臨済宗方広寺派、寺伝によると1200年まえ、行基菩薩により始まった後、廃寺になったが約500年前黙巌禅師が中興し禅寺になったという。明治初年、北に光西寺、西に恵雲庵があったか廃仏稀釈によって廃寺になった。その後善明寺だけ再興し今日になっている、とあります。直親の事は書いてありませんが近くであれば何か関係があったでしょう。
都田川にかかる瀬戸橋から右岸を写す

直親の墓も寺近くにあったが現地に移転した
かって、洪水によって氾濫し堤防等改修、工場が進出し昔の面影はないという

田畑から工場地帯になっている
位置図
赤丸=直親墓 黒丸=今の善明寺

宝林寺や蜂前神社も近い
国道257号線に近く直親の墓には行きやすい。
つづく
浜松市北区細江町中川
屋敷跡はあるか、伺うと「細江町中川に祝田善明寺付近と云われ土地法典に小字に上屋敷が現存するという。
善明寺
寺案内板には、厄除観音で知られている臨済宗方広寺派、寺伝によると1200年まえ、行基菩薩により始まった後、廃寺になったが約500年前黙巌禅師が中興し禅寺になったという。明治初年、北に光西寺、西に恵雲庵があったか廃仏稀釈によって廃寺になった。その後善明寺だけ再興し今日になっている、とあります。直親の事は書いてありませんが近くであれば何か関係があったでしょう。
都田川にかかる瀬戸橋から右岸を写す
直親の墓も寺近くにあったが現地に移転した
かって、洪水によって氾濫し堤防等改修、工場が進出し昔の面影はないという
田畑から工場地帯になっている
位置図
赤丸=直親墓 黒丸=今の善明寺
宝林寺や蜂前神社も近い
国道257号線に近く直親の墓には行きやすい。
つづく
浜松市北区細江町中川