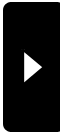2017年02月28日
井伊直虎ゆかりの地は賑やかです
26日、日曜日に井伊谷の龍潭寺へお墓の確認に午後2時ごろ行ったんです。
お寺さん入口


廊下も満員です

土曜日日曜日は凄い観光客のようで、案内人の知人は声を嗄らしていましたよ。
お寺さん入口
廊下も満員です
土曜日日曜日は凄い観光客のようで、案内人の知人は声を嗄らしていましたよ。
2017年02月27日
井伊直虎ゆかりの地-26 家老小野家つづき
井伊家の家老であった小野家の続編です。
図書館で小野家を書いたものは遠州小野一族、家老小野一族などがある。
前回と重複するが記しておく。
小野篁(たかむら)の子、小野俊生は承和5年(838)頃に遠江国赤狭地方に移った?渡来人系・東漢氏(やまとあや)一族の桧前(ひのくま)人が多く住んでいた。ひのくま、引馬地区の麁玉川(あらたまかわ・天竜川)があり河原の荒い石がゴロゴロした荒地であった、山から石灰岩が迫り狭まった所だったようです。陸地は今より狭く海水が押寄せていたようだ。
従三位の位を賜った篁は52歳で仁寿2年(852)12月22日生涯を終えた。
俊生は翌年父の遺骨を遠江国赤狭郡小野村に移す。
浜北区尾野地区を高根神社拝殿から見る

井伊家の小野氏は小野村、小野兵庫助を最初として和泉守正成、子の但馬守政次とその子兵衛をもって井伊谷で処刑、お家断絶になる。兵庫助の子と思われる政成に兄弟があり今川義元と共に桶狭間で討死している。井伊家の跡取り男子が虎松だけになり鳳来寺に逃げた。井伊谷は小野但馬守政次が治めることになるが井伊家乗っ取りと視なされる。徳川軍に井伊谷三人衆が加わり井伊谷に攻め込むと小野は逃げ隠れるが捕まり処刑される。親戚兄弟は今川氏をたよるが今川氏も徳川氏に敗れ北條氏をたよった。武士を止め高畑村土着、浪人になった。小野玄蕃朝直の子、小野朝之は井伊直政に仕え家康と共に転戦し井伊家の家臣千石になったという。
政直ー但馬守政次 処刑
太兵衛 高畑郷下所(おりど)の小野家
七郎右衛門朝之 井伊直勝に仕える
八朗正賢 高畑郷鐘鋳場小野家
利左衛門兵蔵 金指近藤家仕える
井伊家内のことであったからか親兄弟親戚すべてが刑罰の対象なったのではないようです。
時は戦国 元亀3年12月、家康は三方ハ原で信玄に敗れ浜松城へ駆け込む時に乗っていた馬が木の根につまずき倒れる。
その時高根神社の長家播磨守がいた、長家は自分の馬を差出と家康は礼を言い「馬と馬具は与える」と言い走り去った。高根神社には木造馬頭観世音菩薩を彫り祀った。明治になり大宝寺の十三堂に祭った。
尾野地区から見る高根神社拝殿

また、家康の馬が倒れた時に小野氏がいた、乗馬9頭の内から家康好みの馬を替え馬として献上、馬、馬具一切と御書付を小野は受け取る。文禄3年(1594)高根神社に馬頭観音として合祀、今は大宝寺境内に観音堂としてある。天正3年、大久保忠世軍に小野貞次も加わって二俣城を攻めている。領主が近藤岩見守なると公私の家系、上下差違をもって鈴木姓にせよ、小野村2村ありよって、井小野と尾野に改めた。
橘逸勢の記載があったので載せます。
小野俊生の時代
その頃、橘逸勢(たちばなのはやなり)が無実の罪で伊豆国へ流罪になり遠江国板築(ほうつき)駅(都築?)で病死する。娘の妙仲は後を追ってきたて死地に弔う。浜松市北区三ヶ日町日比沢に神社としてあるが大正14年、海軍医・戸塚氏が出土した鏡をもって橘逸勢の遺跡と決めた。
橘逸勢関連記事
つづく
4℃ → 14℃ 晴れ
図書館で小野家を書いたものは遠州小野一族、家老小野一族などがある。
前回と重複するが記しておく。
小野篁(たかむら)の子、小野俊生は承和5年(838)頃に遠江国赤狭地方に移った?渡来人系・東漢氏(やまとあや)一族の桧前(ひのくま)人が多く住んでいた。ひのくま、引馬地区の麁玉川(あらたまかわ・天竜川)があり河原の荒い石がゴロゴロした荒地であった、山から石灰岩が迫り狭まった所だったようです。陸地は今より狭く海水が押寄せていたようだ。
従三位の位を賜った篁は52歳で仁寿2年(852)12月22日生涯を終えた。
俊生は翌年父の遺骨を遠江国赤狭郡小野村に移す。
浜北区尾野地区を高根神社拝殿から見る
井伊家の小野氏は小野村、小野兵庫助を最初として和泉守正成、子の但馬守政次とその子兵衛をもって井伊谷で処刑、お家断絶になる。兵庫助の子と思われる政成に兄弟があり今川義元と共に桶狭間で討死している。井伊家の跡取り男子が虎松だけになり鳳来寺に逃げた。井伊谷は小野但馬守政次が治めることになるが井伊家乗っ取りと視なされる。徳川軍に井伊谷三人衆が加わり井伊谷に攻め込むと小野は逃げ隠れるが捕まり処刑される。親戚兄弟は今川氏をたよるが今川氏も徳川氏に敗れ北條氏をたよった。武士を止め高畑村土着、浪人になった。小野玄蕃朝直の子、小野朝之は井伊直政に仕え家康と共に転戦し井伊家の家臣千石になったという。
政直ー但馬守政次 処刑
太兵衛 高畑郷下所(おりど)の小野家
七郎右衛門朝之 井伊直勝に仕える
八朗正賢 高畑郷鐘鋳場小野家
利左衛門兵蔵 金指近藤家仕える
井伊家内のことであったからか親兄弟親戚すべてが刑罰の対象なったのではないようです。
時は戦国 元亀3年12月、家康は三方ハ原で信玄に敗れ浜松城へ駆け込む時に乗っていた馬が木の根につまずき倒れる。
その時高根神社の長家播磨守がいた、長家は自分の馬を差出と家康は礼を言い「馬と馬具は与える」と言い走り去った。高根神社には木造馬頭観世音菩薩を彫り祀った。明治になり大宝寺の十三堂に祭った。
尾野地区から見る高根神社拝殿
また、家康の馬が倒れた時に小野氏がいた、乗馬9頭の内から家康好みの馬を替え馬として献上、馬、馬具一切と御書付を小野は受け取る。文禄3年(1594)高根神社に馬頭観音として合祀、今は大宝寺境内に観音堂としてある。天正3年、大久保忠世軍に小野貞次も加わって二俣城を攻めている。領主が近藤岩見守なると公私の家系、上下差違をもって鈴木姓にせよ、小野村2村ありよって、井小野と尾野に改めた。
橘逸勢の記載があったので載せます。
小野俊生の時代
その頃、橘逸勢(たちばなのはやなり)が無実の罪で伊豆国へ流罪になり遠江国板築(ほうつき)駅(都築?)で病死する。娘の妙仲は後を追ってきたて死地に弔う。浜松市北区三ヶ日町日比沢に神社としてあるが大正14年、海軍医・戸塚氏が出土した鏡をもって橘逸勢の遺跡と決めた。
橘逸勢関連記事
つづく
4℃ → 14℃ 晴れ
2017年02月27日
2017年02月26日
井伊直虎ゆかりの地-25 亀之丞が帰郷の時、休憩所伝
信州市田郷の松源寺から井伊谷へ帰郷の時、亀之丞と娘の高瀬、家臣の今村藤七郎が腰を下ろし休んだと云われる所があると聞き訪れる。
亀之丞が信州へ逃れた時に通ったと思われる山道、鳳来寺参道古道と同じであろうか、浜松市北区引佐町渋川地区県道298号線、右近次郎殺害現場に近い岡保(おかぼー)地区だった。
県道から林道を上った所
桜地蔵大菩薩とある

林道が建設されたためか高台になった所に祀られている

刻印は定かではないが、長山弥平建之 明治00と読めるが?、近くの方が建てたと思われる
桜の木があったか?倒木がある

林道左上に祀られていた

この上部に古道があるが渋川郷に通じていれば「坂田峠」であったかもしれない。
往路復路に使用した道ならば「坂田峠」はこの辺りであろう。
つづく
2℃ → 15℃ 薄曇りのち晴
亀之丞が信州へ逃れた時に通ったと思われる山道、鳳来寺参道古道と同じであろうか、浜松市北区引佐町渋川地区県道298号線、右近次郎殺害現場に近い岡保(おかぼー)地区だった。
県道から林道を上った所
桜地蔵大菩薩とある
林道が建設されたためか高台になった所に祀られている
刻印は定かではないが、長山弥平建之 明治00と読めるが?、近くの方が建てたと思われる
桜の木があったか?倒木がある
林道左上に祀られていた
この上部に古道があるが渋川郷に通じていれば「坂田峠」であったかもしれない。
往路復路に使用した道ならば「坂田峠」はこの辺りであろう。
つづく
2℃ → 15℃ 薄曇りのち晴
2017年02月26日
2017年02月25日
井伊直虎ゆかりの地ー24 先祖は小野妹子、小野氏の後
井伊家の筆頭家老でありながら家中で孤立する小野政直と嫡男・政次、二男・玄蕃の一族、小野家の生き様はどうであったか?
小野家の御先祖様に小野妹子(おののいもこ)がいたようです。聖徳太子に中国へ遣隋使として手紙を預かり届ける使者になった人物です。
中国へ渡るのは命掛けのこと、出航して嵐によって流浪の旅、海低に消え魚の餌になるなどの覚悟が必要だった。小野篁(たかむら)も使者に選ばれたが渡船が壊れているから交換してと頼むが拒否され中国行きを拒む。と、隠岐へ流刑になる。篁の子・俊生(20歳)は前途悲観し近江から遠江国赤狭郷に巡り着く。篁は承和8年7月15日、嵯峨上皇の皇后・橘嘉知子の助力により都にもどる。文章漢詩和歌共に優れた才能があり文徳天皇に認められたが53歳で亡くなった。
俊生は遺言により仁寿3年(853)2月、遺骨を遠江国へ移す。赤狭の地を小野と変えた。小野篁神社を建立→多賀神社ー高根山観音か? 延喜19年(919)小野朝臣を賜った。朝臣(あそん・あそみ)=八種の姓(かばね)の第2位、5位以上の人の姓名に付けた尊敬語。
大宝寺を開き菩提寺にする。
豊田郡小野村から分家?井伊家、家老職になり細江の小野村に屋敷を与えられた。3代井伊家に仕えたが徳川家康の命により小野一族は斬首になる。井伊直虎の大河ドラマと同時代、何処まで放送するだろうか。
時は流れ徳川時代になる
井伊家3人衆の近藤康用の孫が慶長7年(1602)領地を賜わった。小野篁の子孫27代、小野源右衛門定次が従二位の位で住んでいる。近藤秀用は三千石の旗本、従五位以下である。
領民の位が高いとは上下転倒である、近藤家は面白くない。秀用は家臣に勅書、勅賜、宝刀等、また家康に貰った馬具、書付も取り上げた。小野姓から鈴木姓の換えよ、小野村を井小野村に、地名、小野を尾野に改めよと言った、姓を鈴木に改めた。
次の領主・用常は文化元年(1804)40代鈴木茂七に宝物を献上させ覚書出し七両を与え買い取った形にした。
9代是用は41代鈴木鶴丸に家宝を出させ5両を与えた。
今の細江町小野

井伊谷川の清水橋から上流を写す
徳川幕府から明治になると43代鈴木長作は小野姓」に改姓願いを明治5年に裁判所にだす。返事がないので明治9年に再度だす。しかし返事がないばかりか屋敷内の墓と神社がありそれが「神社領没収令が明治4年(1871)1月5日出て国有地である」と知り驚き地裁に出頭し過去の経緯を説明、地裁に訴え明治31年勝訴した。複姓は明治32年(1899)、16代、296年ぶりの小野姓に戻り先祖の霊に報いた。
つづく
3℃ → 13℃ 晴れ
小野家の御先祖様に小野妹子(おののいもこ)がいたようです。聖徳太子に中国へ遣隋使として手紙を預かり届ける使者になった人物です。
中国へ渡るのは命掛けのこと、出航して嵐によって流浪の旅、海低に消え魚の餌になるなどの覚悟が必要だった。小野篁(たかむら)も使者に選ばれたが渡船が壊れているから交換してと頼むが拒否され中国行きを拒む。と、隠岐へ流刑になる。篁の子・俊生(20歳)は前途悲観し近江から遠江国赤狭郷に巡り着く。篁は承和8年7月15日、嵯峨上皇の皇后・橘嘉知子の助力により都にもどる。文章漢詩和歌共に優れた才能があり文徳天皇に認められたが53歳で亡くなった。
俊生は遺言により仁寿3年(853)2月、遺骨を遠江国へ移す。赤狭の地を小野と変えた。小野篁神社を建立→多賀神社ー高根山観音か? 延喜19年(919)小野朝臣を賜った。朝臣(あそん・あそみ)=八種の姓(かばね)の第2位、5位以上の人の姓名に付けた尊敬語。
大宝寺を開き菩提寺にする。
豊田郡小野村から分家?井伊家、家老職になり細江の小野村に屋敷を与えられた。3代井伊家に仕えたが徳川家康の命により小野一族は斬首になる。井伊直虎の大河ドラマと同時代、何処まで放送するだろうか。
時は流れ徳川時代になる
井伊家3人衆の近藤康用の孫が慶長7年(1602)領地を賜わった。小野篁の子孫27代、小野源右衛門定次が従二位の位で住んでいる。近藤秀用は三千石の旗本、従五位以下である。
領民の位が高いとは上下転倒である、近藤家は面白くない。秀用は家臣に勅書、勅賜、宝刀等、また家康に貰った馬具、書付も取り上げた。小野姓から鈴木姓の換えよ、小野村を井小野村に、地名、小野を尾野に改めよと言った、姓を鈴木に改めた。
次の領主・用常は文化元年(1804)40代鈴木茂七に宝物を献上させ覚書出し七両を与え買い取った形にした。
9代是用は41代鈴木鶴丸に家宝を出させ5両を与えた。
今の細江町小野
井伊谷川の清水橋から上流を写す
徳川幕府から明治になると43代鈴木長作は小野姓」に改姓願いを明治5年に裁判所にだす。返事がないので明治9年に再度だす。しかし返事がないばかりか屋敷内の墓と神社がありそれが「神社領没収令が明治4年(1871)1月5日出て国有地である」と知り驚き地裁に出頭し過去の経緯を説明、地裁に訴え明治31年勝訴した。複姓は明治32年(1899)、16代、296年ぶりの小野姓に戻り先祖の霊に報いた。
つづく
3℃ → 13℃ 晴れ
2017年02月24日
甲冑を牛乳パックで制作
浜松市北区役所二階に井伊家甲冑をモチーフに牛乳パックなどの厚紙で制作し展示してあります。


約300個のパーツを毛糸、布テープで繋ぎ

実物大に作る

着用しても軽い、雨降りも大丈夫とか
大将クラスは牛乳パック80個使う
市内の長山さん、10年ほど前から約100領製作したそうです。
約300個のパーツを毛糸、布テープで繋ぎ
実物大に作る
着用しても軽い、雨降りも大丈夫とか
大将クラスは牛乳パック80個使う
市内の長山さん、10年ほど前から約100領製作したそうです。
タグ :甲冑製作
2017年02月23日
井伊直虎ゆかりの地ー23 奥山氏
井伊家の家臣に奥山家がある。井伊家8代辺りで分家し奥山郷(浜松市北区引佐町奥山)に居を構えていた。
館跡?城址とは思えない


みかん畑になっている
県道303号線 奥山神社に奥山城跡の石碑

代々井伊家に仕え一族と親戚関係を結んでいる。
亀之丞が元服し妻に迎えたのが奥山朝利(ともとし)の娘、おひよである。また、新野左馬助の妻は朝利の妹とされている。
奥山朝利は今川義元の命により井伊家の家臣として息子・孫一郎と共に井伊家当主・井伊直盛に属し桶狭間で織田信長軍の奇襲に遇い今川義元、井伊家22代直盛・奥山朝利戦死した。その時、井伊直盛が奥山孫一郎に遺言する。嫡男・直親、井伊家一族に「井伊家は家臣・中野越後守直由に預けよ」と言い、「これまでの命、自刃する孫一郎、介錯せよ」と命を絶った。首をもって孫一郎は井伊谷に帰る。
龍潭寺にある奥山3代の墓

奥山10代 親朝、11代 朝利、12代 朝宗
龍潭寺の記録では永禄3年(1560)10月22日、12月22日小野政次に討たれた。
井伊年譜には同年12月22日小野政次に討たれたとあるという。
井伊家の墓

正面右 初代 共保
左 22代 直盛
永禄4年(1561)2月9日虎松生まれる
奥山家からは新野左馬助の妻に朝利の妹が嫁ぐ
井伊直盛の妻に新野左馬助の娘が嫁ぎ直虎(次郎法師)が生まれる
井伊直盛の養子に直親(亀之丞)が入り
奥山因幡守朝利の娘が直親と結婚し虎松(直政)永禄4年(1561)2月9日うまれる。
つづく
7℃ → 17℃ 雨のち曇り晴
館跡?城址とは思えない
みかん畑になっている
県道303号線 奥山神社に奥山城跡の石碑
代々井伊家に仕え一族と親戚関係を結んでいる。
亀之丞が元服し妻に迎えたのが奥山朝利(ともとし)の娘、おひよである。また、新野左馬助の妻は朝利の妹とされている。
奥山朝利は今川義元の命により井伊家の家臣として息子・孫一郎と共に井伊家当主・井伊直盛に属し桶狭間で織田信長軍の奇襲に遇い今川義元、井伊家22代直盛・奥山朝利戦死した。その時、井伊直盛が奥山孫一郎に遺言する。嫡男・直親、井伊家一族に「井伊家は家臣・中野越後守直由に預けよ」と言い、「これまでの命、自刃する孫一郎、介錯せよ」と命を絶った。首をもって孫一郎は井伊谷に帰る。
龍潭寺にある奥山3代の墓
奥山10代 親朝、11代 朝利、12代 朝宗
龍潭寺の記録では永禄3年(1560)10月22日、12月22日小野政次に討たれた。
井伊年譜には同年12月22日小野政次に討たれたとあるという。
井伊家の墓
正面右 初代 共保
左 22代 直盛
永禄4年(1561)2月9日虎松生まれる
奥山家からは新野左馬助の妻に朝利の妹が嫁ぐ
井伊直盛の妻に新野左馬助の娘が嫁ぎ直虎(次郎法師)が生まれる
井伊直盛の養子に直親(亀之丞)が入り
奥山因幡守朝利の娘が直親と結婚し虎松(直政)永禄4年(1561)2月9日うまれる。
つづく
7℃ → 17℃ 雨のち曇り晴
2017年02月21日
新聞を見て
今日の中日新聞に「森の石松は新城生まれ」の記事があります。
地元の伊田さんの調査研究され出版されたようです。

言葉の伝承から書物に書き残した事が大切です。
関連記事
地元の伊田さんの調査研究され出版されたようです。
言葉の伝承から書物に書き残した事が大切です。
関連記事
2013/08/03
♪清水港の・・・浪曲・旅ゆけば~「東海遊狭伝」や「正伝清水次郎長」などの出版本と浪曲師・2代目広沢虎造により有名になった「清水次郎長」。その子分「森の石松」は新城市富岡の生まれであると伝えられ墓もあります。 八名小学校の近く、堀切で生まれ親は山本助治・母かな(作手大和田の生まれ)で名主も務め…
2017年02月20日
文化講座・日本一幸せな従業員をつくる!
19日第41回新城市民文化講座が新城文化会館であった。
赤字ホテル運営のドキュメンタリー映画が上映されました(文部科学省選定)。内容は目頭があつくなる、客席からすすり泣きが聴こえた内容でした。
信頼関係が大切
会社の経営方針、資産状態などは公開する
人生の生き方=貴方の働き方である 貴方の性格人格が出る
高い賃金や休みを増やしたではなく
会社と従業員の信頼関係ができるとお客様との信頼ができる
お客様の満足度を得た
地域ナンバー1になった

講師プロフィールから
柴田秋雄 氏
「奇跡体験!アンビリバボー」(フジテレビ)、tedなど多数のメディアで取り上げられた、ホテルアソシア名古屋ターミナル、その総支配人としてホテルをV字回復させたのが柴田秋雄氏とそこで働く従業員でした。4期連続赤字、負債額8億円を抱えたホテルに導いた手法は、財務や戦略論ではなく「人」でした。お客様はもちろんのこと、従業員やその家族までをも優しさと思いやりで包み、暖かさが半端ない「民宿」のような居心地の良さを感じてリピーターが続出。稼働率が95%という驚異的なホテル、それがホテルアソシア名古屋ターミナルでした。
誰もがとりこになる柴田理事長の笑顔、心が温かくなって、生きていることが幸せだと感じられる、自分が大好きになれる、そんな優しさを感じて頂ければ幸いです。
とありました。
柴田先生は体調不良とか、病院から講演にこられたと言い、上演後、舌が回らないからかホテル再建の話はなしでした。
買い物に入った時の従業員の服装会話、態度、清掃状態でその店(会社)の教育が判りますよね。
赤字ホテル運営のドキュメンタリー映画が上映されました(文部科学省選定)。内容は目頭があつくなる、客席からすすり泣きが聴こえた内容でした。
信頼関係が大切
会社の経営方針、資産状態などは公開する
人生の生き方=貴方の働き方である 貴方の性格人格が出る
高い賃金や休みを増やしたではなく
会社と従業員の信頼関係ができるとお客様との信頼ができる
お客様の満足度を得た
地域ナンバー1になった
講師プロフィールから
柴田秋雄 氏
「奇跡体験!アンビリバボー」(フジテレビ)、tedなど多数のメディアで取り上げられた、ホテルアソシア名古屋ターミナル、その総支配人としてホテルをV字回復させたのが柴田秋雄氏とそこで働く従業員でした。4期連続赤字、負債額8億円を抱えたホテルに導いた手法は、財務や戦略論ではなく「人」でした。お客様はもちろんのこと、従業員やその家族までをも優しさと思いやりで包み、暖かさが半端ない「民宿」のような居心地の良さを感じてリピーターが続出。稼働率が95%という驚異的なホテル、それがホテルアソシア名古屋ターミナルでした。
誰もがとりこになる柴田理事長の笑顔、心が温かくなって、生きていることが幸せだと感じられる、自分が大好きになれる、そんな優しさを感じて頂ければ幸いです。
とありました。
柴田先生は体調不良とか、病院から講演にこられたと言い、上演後、舌が回らないからかホテル再建の話はなしでした。
買い物に入った時の従業員の服装会話、態度、清掃状態でその店(会社)の教育が判りますよね。
2017年02月19日
井伊直虎ゆかりの地ー22 隠し里隠し田・久留女木の棚田
竜宮小僧の伝説で訪れた浜松市北区東久留女木の棚田です。
日本の棚田百選にも選ばれた陽当りの良い斜面にあります。何時ごろから耕作が始まったかの説明文がなく判りませんが段丘に張り付くように棚田に造成されている
中腹にある案内板

棚田の最上部にある伝説の竜宮小僧を奉った所

清水が湧いている
地元の農家が先祖代々額の汗して耕してきた棚田
いつごろからの田んぼか解りませんがここが今川家の検地の時、隠し田であったか?





県道299号線から見た棚田
棚田各所にある案内図

井伊谷から直線で約7.5㎞離れています。
つづく
4℃ → 13℃ 晴れ
日本の棚田百選にも選ばれた陽当りの良い斜面にあります。何時ごろから耕作が始まったかの説明文がなく判りませんが段丘に張り付くように棚田に造成されている
中腹にある案内板
棚田の最上部にある伝説の竜宮小僧を奉った所
清水が湧いている
地元の農家が先祖代々額の汗して耕してきた棚田
いつごろからの田んぼか解りませんがここが今川家の検地の時、隠し田であったか?
県道299号線から見た棚田
棚田各所にある案内図
井伊谷から直線で約7.5㎞離れています。
つづく
4℃ → 13℃ 晴れ
2017年02月18日
井伊直虎ゆかりの地ー21 新野左馬助墓所
左馬武神社
左馬助墓について「小笠郡誌」に井伊氏に客家老新野氏ありて主家を助けた、祖先墳墓をの地を尋ねて新野村に来たり探究する所あり、山の中腹の墳墓見つけ、石棺に紋章があり新野家なり、石棺内に五輪の塔ありその先人大いに喜び懇(ねんごろ)に弔い祭り去ったという、是安政年間の事なりしと伝ふ。
このことから井伊直弼が大老になったのは安政5年である、よって井伊大老の兄・中守が探索にきて発見したのであろう。
今は左馬武神社として祀られているが地元では祟りがあるから近寄るな、と言われていたという。
社殿は明治28年頃に造られたがその後は荒れていた。昭和49年9月今の社殿落成した
石棺は石廟のことか
石廟の中に五輪塔があったと言い大変珍しいことのようです
新野氏の居城があった舟ヶ谷の城山
墓は城山を望むように建っていた。
新野左馬助が今川氏真に叛いた飯尾連竜(いのおつらたつ)を攻め浜松引馬城戦(永禄7年1564)で戦死。
龍潭寺の左馬助墓
新野家は今川家臣であったから子・甚五郎は今川氏真に仕え、後、小田原北條氏の家臣になったが豊臣の小田原城攻めで戦死したという。
また、八王子新野家には五郎道氏は今川氏真と共に小田原北條家に逃れ北條氏の家臣になったが天正18年(1590)6月23日八王子城で討つ死、その子・荒五郎は逃れ八王子新野家の祖になったという。名主や八日町宿本陣を務めた。
つづく
7℃ → 13℃ 曇り晴
2017年02月17日
井伊直虎ゆかりの地ー20 新野佐馬助の墓
今川家の家臣に属していた新野左馬助親矩(にいのさまのすけちかのり)は今川・井伊家の和睦の条件として井伊家目付役家老となり井伊家にきた。井伊家の本拠地、新野はどんな所か訪れる。
東名高速菊川インターがら新野観光案内所(御前崎市新野963)「よってかまいか」へ向かう。案内所のご婦人達に「左馬助さんのお墓はどこ?あの鳥居がそうですか」と近くに見えた鳥居を指すと「あれは違うよ、みんな間違える」と駐車場から道路に出て教えて頂く。「その前に左馬助展示館へよって、歩いて数分の所、無料だから」左馬助展示館があるとは知らなかった。館の前に立って思った事は「これはアメリカコロニアルスタイルだな」大正時代の洋風建築じゃない?昭和8年(1933)建築という。

2階建て外壁は板張り
この建物は親子2代続いた元鈴木医院であり亡くなられた東洋医師(88歳)は左馬武(さまたけ)神社、佐馬助墓所の荒廃を嘆き地元有志と「新野左馬助公遺跡保存会」を創設し墓所の改築をし、さらに顕彰会に発展させた経緯から使用されなくなった医院をお借りして「左馬助展示館」にしている.
左馬助の妻は奥山因幡守の妹 左馬助の妹が井伊直盛の妻

直虎は左馬助の姪になる、井伊家とは深い親戚関係だった
新野辺りの図 新野左馬助の墓は⇒

左馬助は永禄7年(1564)引馬城(浜松城の前城)攻めで戦死する。
案内冊子に井伊谷周辺地図があった 上部が井伊城

赤丸が新野家住宅 向が対立する小野家
直盛が桶狭間の戦い(永禄3年1560)戦死すると井伊家筆頭家老小野但馬が「養子に迎えた直親が徳川と内通している」と今川氏真に讒言(ざんげん・うそを言う)する。左馬助は直親に異心ないと今川家に申し立てる。直親自身が釈明に駿府へ行く途中、掛川で斬殺される。直親の子・虎松(直政)2歳を誅殺命令がでる。左馬助は懸命に虎松の助命を嘆願しようやく許され左馬助宅に保護された。
左馬助が命に代える努力により井伊家は途絶えることなく継承できた。井伊家は左馬助の忠節を歴代語り伝えたが幕末に井伊直弼が新野本家が分からなくなっていたので兄・井伊中守に新野家の名跡を相続再興する。
井伊中守は新野村で左馬助の墳墓を探す。
左馬助の墓へ行く
つづく
左馬武神社 近くの高源寺駐車場に駐車する
5℃ → 9℃ 曇り雨晴
東名高速菊川インターがら新野観光案内所(御前崎市新野963)「よってかまいか」へ向かう。案内所のご婦人達に「左馬助さんのお墓はどこ?あの鳥居がそうですか」と近くに見えた鳥居を指すと「あれは違うよ、みんな間違える」と駐車場から道路に出て教えて頂く。「その前に左馬助展示館へよって、歩いて数分の所、無料だから」左馬助展示館があるとは知らなかった。館の前に立って思った事は「これはアメリカコロニアルスタイルだな」大正時代の洋風建築じゃない?昭和8年(1933)建築という。
2階建て外壁は板張り
この建物は親子2代続いた元鈴木医院であり亡くなられた東洋医師(88歳)は左馬武(さまたけ)神社、佐馬助墓所の荒廃を嘆き地元有志と「新野左馬助公遺跡保存会」を創設し墓所の改築をし、さらに顕彰会に発展させた経緯から使用されなくなった医院をお借りして「左馬助展示館」にしている.
左馬助の妻は奥山因幡守の妹 左馬助の妹が井伊直盛の妻
直虎は左馬助の姪になる、井伊家とは深い親戚関係だった
新野辺りの図 新野左馬助の墓は⇒
左馬助は永禄7年(1564)引馬城(浜松城の前城)攻めで戦死する。
案内冊子に井伊谷周辺地図があった 上部が井伊城
赤丸が新野家住宅 向が対立する小野家
直盛が桶狭間の戦い(永禄3年1560)戦死すると井伊家筆頭家老小野但馬が「養子に迎えた直親が徳川と内通している」と今川氏真に讒言(ざんげん・うそを言う)する。左馬助は直親に異心ないと今川家に申し立てる。直親自身が釈明に駿府へ行く途中、掛川で斬殺される。直親の子・虎松(直政)2歳を誅殺命令がでる。左馬助は懸命に虎松の助命を嘆願しようやく許され左馬助宅に保護された。
左馬助が命に代える努力により井伊家は途絶えることなく継承できた。井伊家は左馬助の忠節を歴代語り伝えたが幕末に井伊直弼が新野本家が分からなくなっていたので兄・井伊中守に新野家の名跡を相続再興する。
井伊中守は新野村で左馬助の墳墓を探す。
左馬助の墓へ行く
つづく
左馬武神社 近くの高源寺駐車場に駐車する
5℃ → 9℃ 曇り雨晴
2017年02月16日
代官屋敷と三河から焼き雛が伝えられた
静岡県菊川市を走行中看板を見てよった黒田家住宅です。
国指定重要文化財の代官様の屋敷です。代官所ではありません。
足利下野守義次のとき、越前黒田荘に住し、遠江には永禄年間(1558~70)住んだ。今川氏の高天神城を守ったが落城後は武田、徳川いずれにも与さず帰農する。旗本・本多助久の支配(4千石)になると代官に任命される。
長屋門 茅葺

周りを濠を巡らしている

米蔵、西蔵、東蔵母屋などがある

米蔵

お雛様 焼き雛

明治の初期に農閑期の収入を得るため三河から製法を学び多量生産販売したという。
地域色豊かな雛人形は素朴な願いがこもったもの。暮しが豊かになると焼き雛が見なれなくなったが「静岡雪だるまの会」のみなさんが製法を継承しています。黒田家代官屋敷梅まつり会場にて3月5日まで「焼きびな」展を開催中です。
1haはある広い敷地は大官に成る前から代々住したからか
長屋門の風格は2千石旗本に値するそうです。
1℃ → 16℃ 快晴
国指定重要文化財の代官様の屋敷です。代官所ではありません。
足利下野守義次のとき、越前黒田荘に住し、遠江には永禄年間(1558~70)住んだ。今川氏の高天神城を守ったが落城後は武田、徳川いずれにも与さず帰農する。旗本・本多助久の支配(4千石)になると代官に任命される。
長屋門 茅葺
周りを濠を巡らしている
米蔵、西蔵、東蔵母屋などがある
米蔵
お雛様 焼き雛
明治の初期に農閑期の収入を得るため三河から製法を学び多量生産販売したという。
地域色豊かな雛人形は素朴な願いがこもったもの。暮しが豊かになると焼き雛が見なれなくなったが「静岡雪だるまの会」のみなさんが製法を継承しています。黒田家代官屋敷梅まつり会場にて3月5日まで「焼きびな」展を開催中です。
1haはある広い敷地は大官に成る前から代々住したからか
長屋門の風格は2千石旗本に値するそうです。
1℃ → 16℃ 快晴
2017年02月15日
松山観音堂 哀れ 弘法大師像
浜松市北区井平地区でウォーキングイベント開催中、元小学校辺りが賑やかだったもんで其方へ吸い寄せられ行く。
目的は松山聖観音と馬頭観音様
地名が松山、以前は松の木が多かったが松食い虫にヤラレタという。
明治22年に村人、方広寺が中心になって四国八十八ケ所、弘法大師像を寄進した。

首が折れ、紛失など哀れな状態です
子供が遊んでこのようなことに?・・・・

馬頭観音

江戸後期の物、ハスの花を持ちやさしいお顔です
石の聖観音

「観音の里いだいら」 と書いてありましたが、まだ他にも奉座されているようです。
2℃ → 13℃ 晴れ
目的は松山聖観音と馬頭観音様
地名が松山、以前は松の木が多かったが松食い虫にヤラレタという。
明治22年に村人、方広寺が中心になって四国八十八ケ所、弘法大師像を寄進した。
首が折れ、紛失など哀れな状態です
子供が遊んでこのようなことに?・・・・
馬頭観音
江戸後期の物、ハスの花を持ちやさしいお顔です
石の聖観音
「観音の里いだいら」 と書いてありましたが、まだ他にも奉座されているようです。
2℃ → 13℃ 晴れ
2017年02月14日
井伊直虎ゆかりの地ー19 仏坂十一面観世音菩薩と戦い
前にも記載した事のある浜松市北区引佐町伊平の竹馬寺にある仏坂十一面観音様が昨年、33毎の御開帳だったが今年は特別に12日御開帳をするという。
元正天皇の霊亀年間(715~16)行基がこの地で五仏を四方浄土に建立した。
竹馬寺 霊気陽光か

四方浄土
東の川名 薬師如来
西の的場 阿弥陀如来
北の別所 釈迦如来
南の井平 十一面観音(当地)
安置したという。
この観音様について地元が直虎関連資料物語として書いた物がある。
元亀3年1573)10月武田軍山県昌景隊が5千の兵を奥三河から山吉田、柿本城を落し井伊谷に攻め込む。仏坂は国境であるため殺戮放火の激戦が予想された。直虎が山県昌景と掛け合い十一面観音を避難させてくれるよう頼んだ。無事に気賀の観行院に移されたとあった。
イメージをふくらませた物語と記してありました。
この戦いは「仏坂の戦い」として伝承され井平城主の井平飛騨守直成ら88人が戦死した。峠道に戦死者を祀った御墓「ふろんぼ様」と云う墓が木立の中に数ヵ所ある。
ふろんぼさま 古坊様

元亀2年10月22日 井伊飛騨守と書いた物もある、また山吉田の鈴木重時の弟・重俊は柿本城から退きこの地で防戦するが鉄砲に撃たれ即死した遺骸は仏坂に埋葬した、墓は満光寺、龍潭寺にも墓碑位牌ある重時の家臣は甲、頬宛脇差取り退いたという。子孫は苗字帯刀を許され天竜市只来(ただらい)に住んでいる。
その後 暫く観音様は気賀から帰らなかった。
武田氏は滅亡し江戸時代になると近藤家が領主になり家老の今泉兵左衛門正成が寛文11年(1671)石の聖観音を寄進した。
石の聖観音様

観行院に避難していた十一面観音様を仏坂に複座されたい願望が近郷に高まり、天明9年(1789)伊平村役人が観音様返還を申し出る。再び仏坂に観音様が戻り郷人は喜び長興寺12世鉄源和尚による盛大な鎮座供養が行われた。
御開帳式





嘉永4年(1851)江戸城西の丸が全焼すると仏坂の大杉伐採命令が下る、郷人は霊木であるからと伐採免除を申し立てるが却下され大杉120本が伐採られた。
翌年あたりから7年にかけて疫病が流行したという。
明治になると明治政府の諸佛併合、廃仏毀釈があり十一面観音など仏像は長興寺に仮安置した。
明治12年松山観音堂が新築されると竹馬寺でなく松山に還座した。大正時代に悪病火災があり元の仏坂竹馬寺に十一面観音様を還座し今になっているという。
十一面観音様
桧木 一本作り 像高 164cm
つづく
0℃ → 11℃ 晴れ
元正天皇の霊亀年間(715~16)行基がこの地で五仏を四方浄土に建立した。
竹馬寺 霊気陽光か
四方浄土
東の川名 薬師如来
西の的場 阿弥陀如来
北の別所 釈迦如来
南の井平 十一面観音(当地)
安置したという。
この観音様について地元が直虎関連資料物語として書いた物がある。
元亀3年1573)10月武田軍山県昌景隊が5千の兵を奥三河から山吉田、柿本城を落し井伊谷に攻め込む。仏坂は国境であるため殺戮放火の激戦が予想された。直虎が山県昌景と掛け合い十一面観音を避難させてくれるよう頼んだ。無事に気賀の観行院に移されたとあった。
イメージをふくらませた物語と記してありました。
この戦いは「仏坂の戦い」として伝承され井平城主の井平飛騨守直成ら88人が戦死した。峠道に戦死者を祀った御墓「ふろんぼ様」と云う墓が木立の中に数ヵ所ある。
ふろんぼさま 古坊様

元亀2年10月22日 井伊飛騨守と書いた物もある、また山吉田の鈴木重時の弟・重俊は柿本城から退きこの地で防戦するが鉄砲に撃たれ即死した遺骸は仏坂に埋葬した、墓は満光寺、龍潭寺にも墓碑位牌ある重時の家臣は甲、頬宛脇差取り退いたという。子孫は苗字帯刀を許され天竜市只来(ただらい)に住んでいる。
その後 暫く観音様は気賀から帰らなかった。
武田氏は滅亡し江戸時代になると近藤家が領主になり家老の今泉兵左衛門正成が寛文11年(1671)石の聖観音を寄進した。
石の聖観音様
観行院に避難していた十一面観音様を仏坂に複座されたい願望が近郷に高まり、天明9年(1789)伊平村役人が観音様返還を申し出る。再び仏坂に観音様が戻り郷人は喜び長興寺12世鉄源和尚による盛大な鎮座供養が行われた。
御開帳式
嘉永4年(1851)江戸城西の丸が全焼すると仏坂の大杉伐採命令が下る、郷人は霊木であるからと伐採免除を申し立てるが却下され大杉120本が伐採られた。
翌年あたりから7年にかけて疫病が流行したという。
明治になると明治政府の諸佛併合、廃仏毀釈があり十一面観音など仏像は長興寺に仮安置した。
明治12年松山観音堂が新築されると竹馬寺でなく松山に還座した。大正時代に悪病火災があり元の仏坂竹馬寺に十一面観音様を還座し今になっているという。
十一面観音様
桧木 一本作り 像高 164cm
つづく
0℃ → 11℃ 晴れ
2017年02月13日
シャンシャンうまっこ
浜松市北区引佐町伊平で観ました。この伊平地区は井伊家から分家して井平家を名乗り、昔は井平と言っていた。鳳来寺詣での街道であり鍛冶屋の街だったそうです。井伊家20代直平、22代直宗の妻は井平家の生まれです。
直虎の祖父母の地ですから遊びに来たことでしょう。
松山聖観世音様の祭礼でした。



井平地区

井平氏住居跡

道脇の馬頭観音を見かけますが馬は農耕運搬にと手足になって働いてくれました。
感謝をこめてのシャンシャン馬っこ奉りでしょう。
松山には立派な馬頭観音様が祀られていた。
直虎の祖父母の地ですから遊びに来たことでしょう。
松山聖観世音様の祭礼でした。
井平地区
井平氏住居跡
道脇の馬頭観音を見かけますが馬は農耕運搬にと手足になって働いてくれました。
感謝をこめてのシャンシャン馬っこ奉りでしょう。
松山には立派な馬頭観音様が祀られていた。
2017年02月12日
長篠設楽原の戦い 鈴木金七郎重政が百姓になった訳
長篠城の戦い(1575)で城から鳥居強右衛門と脱出した鈴木金七郎重政は作手・大田代で百姓になった。
新城市郷土研究会の月例会
「鈴木金七郎の再評価活動」

金七郎の生家(新城市富永川上)に伝承話には何代後に子孫が訪れ「金七郎は川上に戻りたい」と言っていた事から生家の近くに祠を建て祀った。また、家族は妻、長男、娘2人だったが「我が子を戦場に立たせたくない、娘2人を在所に残したいから宜しく頼む」と長男を連れ田代に住み百姓になったと云う。
長篠戦いの2年後、生家近くの「白山社正月祭礼宮座の覚え」に

田代村 氏子
金七郎の名がある。
子を戦場に送りたくない、親心は今も変わらない。
平和な日々を望んでのことでしょう。
新城市郷土研究会の月例会
「鈴木金七郎の再評価活動」
金七郎の生家(新城市富永川上)に伝承話には何代後に子孫が訪れ「金七郎は川上に戻りたい」と言っていた事から生家の近くに祠を建て祀った。また、家族は妻、長男、娘2人だったが「我が子を戦場に立たせたくない、娘2人を在所に残したいから宜しく頼む」と長男を連れ田代に住み百姓になったと云う。
長篠戦いの2年後、生家近くの「白山社正月祭礼宮座の覚え」に
田代村 氏子
金七郎の名がある。
子を戦場に送りたくない、親心は今も変わらない。
平和な日々を望んでのことでしょう。