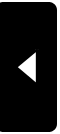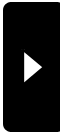2010年11月21日
火縄銃
先日 JA文化講座「鉄砲入門」のお話を伺いました
新城市設楽原歴史資料館の日本銃砲史学会会員でもある 湯浅大司先生の講演でした

火縄銃の歴史から 火縄銃構造 火縄銃の撃ち方 火縄銃のいろいろ等
興味ある話に感動しました 天正3年(1575年)5月21日、旧暦ですから現在、平成23年は6月22日になります 梅雨時です 3,000丁の火縄銃の3段撃ち「設楽原の戦い」で威力を見せつけた火縄銃 戦い方を変えた戦具でした 当日、雨でしたら戦いの行方はどうなったでしょう?
設楽原歴史資料館 新城市竹広


火薬が日本で使われた記録は平安時代、承安2年(1172)「伊豆の島に見慣れぬ者が船で来て脇から火を出し畑や辺りを焼き逃げた」 文永11年(1274)元軍が博多湾で火薬玉に火をつけ投石機では発射 初めての火薬にビックリした事でしょう 種子島での造り方の苦労 筒底の止め方はネジの造り方を知らない為大変だったようです
新城市設楽原歴史資料館
新城市設楽原歴史資料館の日本銃砲史学会会員でもある 湯浅大司先生の講演でした
火縄銃の歴史から 火縄銃構造 火縄銃の撃ち方 火縄銃のいろいろ等
興味ある話に感動しました 天正3年(1575年)5月21日、旧暦ですから現在、平成23年は6月22日になります 梅雨時です 3,000丁の火縄銃の3段撃ち「設楽原の戦い」で威力を見せつけた火縄銃 戦い方を変えた戦具でした 当日、雨でしたら戦いの行方はどうなったでしょう?
設楽原歴史資料館 新城市竹広


火薬が日本で使われた記録は平安時代、承安2年(1172)「伊豆の島に見慣れぬ者が船で来て脇から火を出し畑や辺りを焼き逃げた」 文永11年(1274)元軍が博多湾で火薬玉に火をつけ投石機では発射 初めての火薬にビックリした事でしょう 種子島での造り方の苦労 筒底の止め方はネジの造り方を知らない為大変だったようです
新城市設楽原歴史資料館
2010年11月20日
豊川に架かる橋 3
松戸橋 上流から3番目の橋です
標高約360m 左岸下流より 旧田口線三河田口駅から約500m上流の橋です 設楽ダム建設で水没します
旧田口線三河田口駅から約500m上流の橋です 設楽ダム建設で水没します
左岸より右岸方向を見る 左 松戸地区へ 右は東海自然歩道、元森林鉄道跡

左岸 町営バス停です

右岸から見る

橋上より上流を見る 左が本流大名倉地区へ 右は境川 源流は津具地区の「古町高山」(ふるまちたかやま、)標高1055mです

橋上より下流を見る 左岸の建物は製材所跡

東海自然歩道です 元は段戸山の伐採木を田口駅まで運送する森林鉄道でした

下流川原から橋を見る

右岸に旧道?らしき道がありました

8月 橋の下で昼食中

松戸橋 設楽町道 昭和33年6月竣工 長さ39.6m 幅 4.4m
松戸橋
標高約360m 左岸下流より
左岸より右岸方向を見る 左 松戸地区へ 右は東海自然歩道、元森林鉄道跡
左岸 町営バス停です
右岸から見る
橋上より上流を見る 左が本流大名倉地区へ 右は境川 源流は津具地区の「古町高山」(ふるまちたかやま、)標高1055mです
橋上より下流を見る 左岸の建物は製材所跡
東海自然歩道です 元は段戸山の伐採木を田口駅まで運送する森林鉄道でした
下流川原から橋を見る
右岸に旧道?らしき道がありました
8月 橋の下で昼食中
松戸橋 設楽町道 昭和33年6月竣工 長さ39.6m 幅 4.4m
松戸橋
2010年11月20日
2010年11月19日
豊川に架かる橋 2
大名倉橋
設楽町大名倉地区の橋です 設楽ダム建設で水没します 民家の移転が始まりました
南高台から

左岸より見る

右岸から見る

上流から見る

橋上から上流を見る

橋上から下流を見る

近くに「炭焼き窯」の跡が有りました

右岸の袂
設楽町道 長さ 21.9m 幅 4.7m 昭和42年1月 竣工
前回の「豊川上流端」石碑文字が解る写真を載せます

大名倉橋
設楽町大名倉地区の橋です 設楽ダム建設で水没します 民家の移転が始まりました
南高台から
左岸より見る
右岸から見る
上流から見る
橋上から上流を見る
橋上から下流を見る
近くに「炭焼き窯」の跡が有りました
右岸の袂
設楽町道 長さ 21.9m 幅 4.7m 昭和42年1月 竣工
前回の「豊川上流端」石碑文字が解る写真を載せます
大名倉橋
2010年11月18日
豊川に架かる橋 1
清流公園歩道橋 1
橋の前に
豊川とは 国土交通省が定めた三河湾河口から約77km上流の設楽町宇連地区にある「一級河川上流端石碑」までを言います 豊川石碑の所で本谷川と澄川に分かれます
県道33号線の脇、澄川橋袂にある石碑 右の白い柱


澄川橋 豊川に架かる橋では有りません

左は本谷川 手前右が澄川です

豊川「一級河川上流端石碑」から1.7km下流 設楽町「清流公園」に架かる橋です

清流公園歩道橋 豊川最上流の橋です 上流から1番目の橋
設楽町の管理橋 平成2年愛知県観光施設整備事業 で平成3年3月竣工
長さ 40m 幅 1m 吊橋 です
清流公園歩道橋
橋の前に
豊川とは 国土交通省が定めた三河湾河口から約77km上流の設楽町宇連地区にある「一級河川上流端石碑」までを言います 豊川石碑の所で本谷川と澄川に分かれます
県道33号線の脇、澄川橋袂にある石碑 右の白い柱
澄川橋 豊川に架かる橋では有りません
左は本谷川 手前右が澄川です
豊川「一級河川上流端石碑」から1.7km下流 設楽町「清流公園」に架かる橋です
清流公園歩道橋 豊川最上流の橋です 上流から1番目の橋
設楽町の管理橋 平成2年愛知県観光施設整備事業 で平成3年3月竣工
長さ 40m 幅 1m 吊橋 です
清流公園歩道橋
2010年11月18日
今日の紅葉は
快晴 でも風強し また紅葉散策
設楽町岩古谷山へ 神田地区からの写真です 9:40

仏坂を通りましたので 千枚田を一枚 10:00

新城総合公園に寄ると 10:30

綺麗ですね 風が吹きと 葉がパラパラ
四谷千枚田
設楽町岩古谷山へ 神田地区からの写真です 9:40
仏坂を通りましたので 千枚田を一枚 10:00
新城総合公園に寄ると 10:30
綺麗ですね 風が吹きと 葉がパラパラ
四谷千枚田
2010年11月17日
2010年11月16日
すげー! 岩古谷山
1500万年前、奥三河は激しい火山活動があり、3000m級の火山が有ったと言われています その名残が噴出した石英安山岩が主の岩古谷山です

紅葉の岩古谷山です 写真が続きます

振り返ると

まもなく山頂

休憩 砦があった所 1570年代の話

見下ろせば神田地区

続いて見下ろすと 和市地区

割れ石 岩がはがれています

岩に添って根がー なが~いです

岩のトンネル

コウモリ穴 キクカシラこうもり、コキクカシラこうもりが確認されたとか カジカカエルもいたそうです

滝には水はなし

余談ですが 近くの田口鉱山産のルビーに似た「パイロクスマンガン石」がアポロ11号が持ち帰った「パイクロス鉱石」に似ていた事で話題になりました 田口鉱山産が結晶、美しさが他を寄せ付けない素晴らしい物だと聞いています 登山道の足元に転がっているかも?
紅葉の岩古谷山です 写真が続きます
振り返ると
まもなく山頂
休憩 砦があった所 1570年代の話
見下ろせば神田地区
続いて見下ろすと 和市地区
割れ石 岩がはがれています
岩に添って根がー なが~いです
岩のトンネル
コウモリ穴 キクカシラこうもり、コキクカシラこうもりが確認されたとか カジカカエルもいたそうです
滝には水はなし
余談ですが 近くの田口鉱山産のルビーに似た「パイロクスマンガン石」がアポロ11号が持ち帰った「パイクロス鉱石」に似ていた事で話題になりました 田口鉱山産が結晶、美しさが他を寄せ付けない素晴らしい物だと聞いています 登山道の足元に転がっているかも?
2010年11月16日
捨てなくて好かった
3日前から皇帝ダリアが咲き出しました
越冬させたダリア ダメだろうと捨てるつもりで庭の隅に植えた物です 背丈も2.5m程に成長 4本共蕾が有り 凄い生命力ですね

秋になるにつれて成長

名前の分らない花です

越冬させたダリア ダメだろうと捨てるつもりで庭の隅に植えた物です 背丈も2.5m程に成長 4本共蕾が有り 凄い生命力ですね
秋になるにつれて成長
名前の分らない花です
2010年11月16日
2010年11月15日
堤石トンネル
名勝 岩古谷山の真下にある「堤石トンネル」について
子供の頃「岩古谷のお祭り」があり 田口側トンネル入り口のトラック台上で演劇等が行われていました
今でも記憶している事は「マムシに噛まれてもこの練り薬を塗れば大丈夫」と実際に蛇に指を噛ませて薬を塗る、剣で腕を切り、薬を塗ると血は止まり傷痕も無い、「すごい薬だ~」と驚いた事です 今になればー。

平成12年に災害防止工事が行われ、入口が手前になり、トンネルの長さも600mに。 右側に旅館がありました 登山道入口は左側で少し上ると「熊」が飼われていました 昔の事ですが;;
トンネル内部 昭和9年に開通 真っ暗な内部で徒競争をしました、今は明るいですね

国道473号線ですがトンネルが無い時代は「堤石峠」を越えて田口ー東栄を歩いていたのです
設楽町神田側です

新しいトンネルを掘っています 設楽町神田側


設楽町和市側工事現場です

堤石トンネル
子供の頃「岩古谷のお祭り」があり 田口側トンネル入り口のトラック台上で演劇等が行われていました
今でも記憶している事は「マムシに噛まれてもこの練り薬を塗れば大丈夫」と実際に蛇に指を噛ませて薬を塗る、剣で腕を切り、薬を塗ると血は止まり傷痕も無い、「すごい薬だ~」と驚いた事です 今になればー。
平成12年に災害防止工事が行われ、入口が手前になり、トンネルの長さも600mに。 右側に旅館がありました 登山道入口は左側で少し上ると「熊」が飼われていました 昔の事ですが;;
トンネル内部 昭和9年に開通 真っ暗な内部で徒競争をしました、今は明るいですね
国道473号線ですがトンネルが無い時代は「堤石峠」を越えて田口ー東栄を歩いていたのです
設楽町神田側です
新しいトンネルを掘っています 設楽町神田側
設楽町和市側工事現場です
堤石トンネル
タグ :岩古谷山
2010年11月15日
2010年11月14日
紅葉は?
岩古谷山の紅葉
愛知県設楽町の岩古谷山(いわごや799m)に登りました。 登山道は2ルート有ります
和市(わいち)登山口は登りやすいです 堤石トンネル登山口からは登りの連続で大変です。
山頂から

和市登山口

堤石峠 和市から約40分

山頂まで登り下りが続きます



山頂です 約70分

眼下に和市地区が見えます

曇り空でした 晴れていたら最高でした~のに!
4歳の子供も登っていました。和市から山頂へ 堤石トンネルへ下山が好いと思います
愛知県設楽町の岩古谷山(いわごや799m)に登りました。 登山道は2ルート有ります
和市(わいち)登山口は登りやすいです 堤石トンネル登山口からは登りの連続で大変です。
山頂から
和市登山口
堤石峠 和市から約40分
山頂まで登り下りが続きます
山頂です 約70分
眼下に和市地区が見えます
曇り空でした 晴れていたら最高でした~のに!
4歳の子供も登っていました。和市から山頂へ 堤石トンネルへ下山が好いと思います
2010年11月14日
2010年11月14日
昨日の火災は
昨日の黒煙は民家火災とTV,新聞で報道していました
豊川ウォーキング中、豊川放水路管理所で昼食時間でした

火災の多い季節です 注意したいですね 火災は豊橋市下条西町でした
又 10日の車両火災はお年寄りの方が亡くなられたとか、体調不良だったのでしょうか

豊川放水路管理所
豊川ウォーキング中、豊川放水路管理所で昼食時間でした
火災の多い季節です 注意したいですね 火災は豊橋市下条西町でした
又 10日の車両火災はお年寄りの方が亡くなられたとか、体調不良だったのでしょうか
豊川放水路管理所
2010年11月13日
木地師て なあ~に?2
再び 木地師について
滋賀県東近江市永源寺地区は良質森林があったことから「ろくろ」で木製品製造が始まった
足ぶみ ろくろ 面の木ビジターセンターの写真です 新しい物
良木を求めて全国移動した木地師のため高松御所、筒井八幡神社は氏子の証明、木地師免許、往来手形等をあたえ、そのかわり奉加金を徴収 集金人を「氏子狩人」と言ったようです 免許の更新も兼ねていたとか
面の木ビギターセンター
木地師は全国の山に自由に入れ、8合目以上は木材を自由に伐採できたが明治になり地租改革により伐採許可が必要になり現在では伝統工芸の維持等で活躍しています
津具の木地師家屋図

伐採道具
木地師家屋 復元地
滋賀県東近江市永源寺地区は良質森林があったことから「ろくろ」で木製品製造が始まった
足ぶみ ろくろ 面の木ビジターセンターの写真です 新しい物
良木を求めて全国移動した木地師のため高松御所、筒井八幡神社は氏子の証明、木地師免許、往来手形等をあたえ、そのかわり奉加金を徴収 集金人を「氏子狩人」と言ったようです 免許の更新も兼ねていたとか
面の木ビギターセンター

木地師は全国の山に自由に入れ、8合目以上は木材を自由に伐採できたが明治になり地租改革により伐採許可が必要になり現在では伝統工芸の維持等で活躍しています
津具の木地師家屋図

伐採道具
木地師家屋 復元地
2010年11月13日
2010年11月12日
木地師て なあ~に?
愛知県設楽町津具地区 茶臼山高原道路にある「面の木ビジターセンター」の南側に
「木地師住居跡」の案内板が有りました 300m程下りた所です
「木地師 きじし」 木地屋とも言われたようです 山地に入りお椀、お盆、こけし等木から物を造る職人、集団を言います
面の木の木地師家屋 復元
木地師の里 滋賀県東近江市(旧永源寺町)君ヶ畑地区が始まりとされています 今から約1100年前55代文徳天皇の代1皇子惟喬(これたか)親王が天皇継承に敗れ旧永源寺町に住む ある日、親王は法華経の巻物を引くと軸が回転ことから「轆轤 ろくろ」を考案
つづく
「木地師住居跡」の案内板が有りました 300m程下りた所です
「木地師 きじし」 木地屋とも言われたようです 山地に入りお椀、お盆、こけし等木から物を造る職人、集団を言います
面の木の木地師家屋 復元

木地師の里 滋賀県東近江市(旧永源寺町)君ヶ畑地区が始まりとされています 今から約1100年前55代文徳天皇の代1皇子惟喬(これたか)親王が天皇継承に敗れ旧永源寺町に住む ある日、親王は法華経の巻物を引くと軸が回転ことから「轆轤 ろくろ」を考案
つづく
2010年11月12日
天狗だ~!
茶臼山高原道路「面の木ビジターセンター」に天狗の像があります
この近くには「碁盤石山、風越」等 天狗伝説が多くあります
大天狗 小天狗 烏天狗(木葉天狗)が住んでいたとか

天狗はなぜ鼻が高いの? 鼻が高いのが天狗?か

説明です

この近くには「碁盤石山、風越」等 天狗伝説が多くあります
大天狗 小天狗 烏天狗(木葉天狗)が住んでいたとか
天狗はなぜ鼻が高いの? 鼻が高いのが天狗?か
説明です
タグ :天狗伝説面の木ビジターセンター
2010年11月11日
茶臼山は
昨日 午後 愛知県豊根村茶臼山へ行ってみました
雲が山頂に掛かり小雨が降り冬模様です

午後3時気温は0℃ 雪が舞っても可笑しくないです

紅葉も終わっています

でも 高原道路は綺麗です


先日の大風で紅葉が飛んでしまったようです
紅葉も海抜1000m以下になってきました
雲が山頂に掛かり小雨が降り冬模様です
午後3時気温は0℃ 雪が舞っても可笑しくないです
紅葉も終わっています
でも 高原道路は綺麗です
先日の大風で紅葉が飛んでしまったようです
紅葉も海抜1000m以下になってきました


 天候曇り空、設楽町の岩古谷山、山頂にいます。 紅葉最高ですよ。
天候曇り空、設楽町の岩古谷山、山頂にいます。 紅葉最高ですよ。 今、豊川放水路右岸にいます。豊川左岸の林の向こうから煙りが上がっています。
今、豊川放水路右岸にいます。豊川左岸の林の向こうから煙りが上がっています。